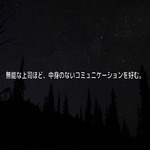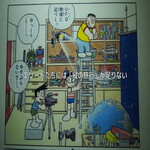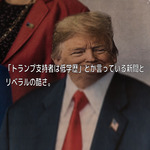拙著「頭のいい人が話す前に考えていること」の影響で、以前より「コミュニケーション能力」について話したり、書いたりすることが多くなった。
「考えていること」というタイトルにもかかわらず、「コミュニケーション」がメインのコンテンツになることを不思議に思う方もいるかもしれない。
が、コミュニケーション能力は、「人間の知性の本質」である。
IQや論理的能力などの「測れる知能」はその副産物に過ぎない。
太古から、人間は他者の考えることを正確に類推し、仲間を多く集められる人間が、富を得て社会的な成功を収めた。
以前にも書いたように、要は他者を動かす能力こそ、人間がサルから進化する時に得た、猿と人類を分かつ強力な能力であり、だからこそ、企業は採用試験で「コミュニケーション能力」に非常に高い価値を置く。
つまり、コミュニケーション能力の高い人=賢い人、なのである。
であるがゆえに、他の多くのコミュニティでも、コミュニケーション能力の低い人間は仲間に入れてもらえない。
それが「コミュニティに不利益をもたらす」ことが予想できるからだ。
*
しかし、問題もある。
「コミュニケーション能力」
に関して、まだかなり多くの誤解があるのだ。
例えば、「コミュニケーション能力を鍛えること」を、性格を変えることである、と認識している人が少なくない。
でも、これは大きな勘違いだ。
これも前に書いたが、例えば「明るい人であること」と「コミュニケーション能力がある」ことは、直接的な関係はない。
むしろ、明るいだけで、コミュニケーション能力のない奴は、
「単なるバカ」
と認識されてしまう恐れすらある。
では、「コミュニケーション能力を高めたい」という人は、どのような認識を持てばよいのだろうか。
これについては、ピーター・ドラッカーの言葉を引用したい。
人間関係に優れた才能をもつからといって、よい人間関係がもてるわけではない。
自らの仕事や人との関係において、貢献に焦点を合わせることにより、初めてよい人間関係がもてるのである。こうして、人間関係は生産的なものとなる。
まさに生産的であることが、よい人間関係の唯一の定義である。
「貢献に焦点」
「生産的」
と述べられているが、要はこれは「お互いが、お互いにとってプラスになる関係」と考えてよい。
生産的であることが、良い人間関係の唯一の定義、というのは非常に優れた洞察だ。
これはつまり、性格を変えたり、明るくふるまったり、「陽キャ」を目指したりと、「コミュニケーションのためのコミュニケーションを積極的に行う人物」が理想ではないという事を意味している。
いや、むしろそれは仕事上は「とりつくろい」であるとドラッカーは言う。
仕事に焦点を合わせた関係において成果が何もなければ、温かな会話や感情も無意味である。
とりつくろいにすぎない。
逆に、関係者全員にとって成果をもたらす関係であるならば、失礼な言葉があっても人間関係を壊すことはない。
「成果が何もなければ、温かな会話や感情も無意味」は、皆、心の中でそう思っているだろう。
人当たりがいいだけで、自分の給与を上げてくれない上司は、迷惑だ。
優しいけど、成果を追求させない上司は、結局役に立たない。
言ってみれば、無能な上司ほど、中身のないコミュニケーションを好むと言っても良い。
それが、彼の唯一の強み、処世術だからだ。
しかし、それは遠からず破綻する。
私はコンサルティング会社にいたとき、
「非常にとっつきやすく、明朗な上司」と、「とっつきにくく、厳しい上司」の両方に仕えたことがある。
当然ではあるが、まわりから見たら、前者の方が「部下になりたい」という人が多かった。
しかしその実、前者は自分が嫌われたくない、という一心で、部下に優しい態度をとっていただけだった。
長期的に周囲から尊敬をされたのは、結局「好かれた上司」ではなく「部下に成果をあげさせる上司」であることは間違いない。
煙たがられる上司も、部下に成果さえ上げさせれば、5年後には「人を良く育てた」と評価される。
*
つまり「コミュニケーション能力」を向上させようと思ったら、表面的な言葉や会話のやり取りから一歩進めて、「成果」や「貢献」に、より焦点をあてなければならない。
これが最大のポイントである。
「言葉よりも成果」なのだ。
上司が何を求めているのか。
顧客が何を求めているのか。
友達が何を求めているのか。
家族が何を求めているのか。
ご近所さんが何を求めているのか。
それを理解するために話し、動く。
また、そういうことを理解するためのプロセスを含めた、関わり方すべてが、
「コミュニケーション能力」の発揮のしどころとなる。
もちろん、「明朗・快活」であることは仕事の一つの助けになるとは言える。
が、そこは全く本質ではないし、「仕事しない陽キャ」と「貢献度の高い陰キャ」であれば、後者の方がよほどコミュニケーション能力が高いと言っても良い。
そう考えていくと、「会話が苦手だから仕事ができない」「根暗だから営業が苦手」などの言説は、的外れであることがわかる。
問題はそこではない。
あえてはっきり言えば、「成果」や「貢献」をきちんと理解しておらず、成果を差し置いて、言葉で取り繕おうとしたり、役に立たない媚ばかり売ってくるから、嫌われるのだ。
人間関係が良いから仕事がうまくいくのではない。
仕事がうまくいっているから人間関係が良くなる。
この因果関係が理解できるかどうかで、その人が発揮できる「コミュニケーション能力」は大きく変わる。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者プロフィール】
安達裕哉
生成AI活用支援のワークワンダースCEO(https://workwonders.jp)|元Deloitteのコンサルタント|オウンドメディア支援のティネクト代表(http://tinect.jp)|著書「頭のいい人が話す前に考えていること」65万部(https://amzn.to/49Tivyi)|
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯note:(生成AI時代の「ライターとマーケティング」の、実践的教科書)
Photo:Ben Arthur