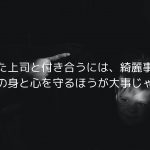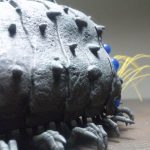「質問がヘタな人」が、世の中には数多くいる。
例えば、こんな感じだ。
*
後輩 「先輩、昨日のお客さんの件で、いまお時間いただいていいですか?」
先輩 「うん。」
後輩 「今後、どういう作戦がいいかと思いまして。」
先輩 「……?何の話?営業の話?それとも提案資料について?」
後輩 「えー、追いかけるべきかどうかです。」
先輩 「……ああ、今はまだ、ちゃんと営業したほうがいいんじゃないかな。」
後輩 「あ、じゃ、ご案内したほうがいいですよね?」
先輩 「……?何を?カタログ?会社案内?」
後輩 「次回の営業セミナーです。」
先輩 「ああ、営業セミナーか、そうだね、ん-、ま、ご案内したほうがいいかな。」
後輩 「わかりました。あ、どっちがいいですかね?」
先輩 「どっちって……?何の話?セミナー何種類もあったっけ?」
後輩 「いえ、セミナーをメールでご案内するか、直接会ってご案内するかです。」
先輩 「……単なる連絡の話?……連絡は早いほうが良さそうなのでメールで……ねえ。」
後輩 「はい?」
先輩 「もうちょっと、考えてから質問してくれないかな……。」
*
こういう類の質問のしかたは、回答者を無用に迷わせるので
「ヘタな質問」に属する。
先輩がいい人だったり、「そういうものだ」と割り切って、辛抱強く付き合ってくれる人もいると思うが、先輩が忙しかったり、短気な人だとイラっとされて、
「もうすこし考えてから、質問してくれないかな。」
と冷たく言われてしまうこともあるかもしれない。
では、これはどのように質問すればよかったのかというと、次のようになる。
*
「先輩、昨日のお客さんの件で、お時間いいですか?」
「うん。」
「質問が3つあるのですが、一つ目は、昨日のお客さんは、営業案件としてきちっと追いかけたほうがいいでしょうか?私は追いかけるべきだと思っていますが……。」
「追いかけるべきだろうね。」
「わかりました。二つ目は、そういうことなら、次回の営業セミナーをご案内したほうがよいでしょうか?」
「ん-、まあ、そうだね。」
「わかりました。三つめは、来週またお客さんに訪問するので、セミナーはその時に案内しようかと思いますがどうでしょう?」
「セミナーなら、早めに連絡したほうがいいと思うんで、事前にメールでもご案内してもらえるかな。」
「わかりました。」
前提条件が不明だと、なにを回答してよいかわからない
この差はいったいどこにあるのか?
それは、質問者が「前提条件を提示しているかどうか」にある。
例えば、パートナーから「何食べたい?」と質問されたとする。
こちらが「ん-、(今は)アイスが食べたいかな」と返したら、
「いや、(今じゃなくて)夕飯の話。」
と、後づけの条件を加えられたことがある人、いるのではないだろうか。
このように、回答にあたって「それを先に言ってくれよ」と思うような条件。
「それを踏まえて」答えなければならない条件。
それが、質問の「前提条件」だ。
仕事でも「条件によって回答が変わるので答えづらい」という質問をもらうことは多いだろう。
「今後の見通しはどうですか?」とか。
「やったほうがいいことはありますか?」とか。
「何か対策はありますか?」とか。
特に上のような「予測」に関する質問は、前提によって大きく回答が変わってくるので、答えるのがとても難しい。
にもかかわらず、「質問がヘタな人」は、こうした前提条件をすっ飛ばして、「自分が聞きたいことだけ聞いてくる」。
だから、「それは場合によるけど……」と、回答に苦慮することもしばしばある。
もちろん、できる先輩は、「前提条件」を推測し、後輩の言語化して先回りして答えてくれる。
「こういう場合は、こう。別の場合なら、こう。あるいは、このケースなら、こう。」と。
実際、冒頭の先輩は
「今後、どういう作戦がいいか?」
という質問に対して、次のように言った。
「……?何の話?営業の話?それとも提案資料について?」
これは先輩が、前提条件を文脈から推定してくれたのだ。
だが、このやり取りは、「質問される側に、時として多大な負荷がかかる」。
だから、親切な先輩であっても、何度もこのような質問をされ、改善の気配がないと、徐々に
「あいつの質問、答えるのが面倒なんだよなあ」
という評価を下すようになる。
*
だから、質問がヘタで、相手をイライラさせてしまったことのある人は、質問の前に
「どのような情報を与えれば、相手が質問に答えやすいか?」
を、少し考えてみると、状況が改善する。
たいていの場合は
・質問をしようと思った経緯を説明する
・聞くだけではなく、自分の意見を言ってから質問する
・主語(~が)や目的語(~を)を省略しない
だけで、「質問上手くなったね」と言われるくらい、かなり良くなる。
「面倒だな」と思わず、回答者の負担を少しでも減らしてあげよう。
*
4月19日に”頭のいい人が話す前に考えていること” という本を出しました。
ここには、「働く上で知っておくと得すること」を盛り込みました。
マネジメントやコミュニケーションの摩擦が、「本来注力すべき仕事」の邪魔をするという事はよくあります。
こうした「人間関係の摩擦」を最小限にする、という事を一つの目的として書いた本です。
ぜひ、お手に取ってみてください。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
安達裕哉
元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)
image:Tachina Lee