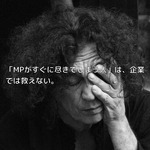多分人と話すとMPが回復していく生き物と、人と話すとMP削れていく生き物は根本的に分かり合えないのだと思う。
— 前島賢(大樹連司) (@MAEZIMAS) August 30, 2024
ゲームカルチャーが広く知られるようになったことで、「MP」とか「HP」といった比喩をよく見かけるようになりました。
このbooks&appsでも、3月には「「MPがすぐに尽きてしまう人」は、企業では救えない。」という記事がバズっていました。
ネットスラングとして、MPという比喩は市民権を得るに至っている、と考えて間違いではないでしょう。
で、冒頭のツイートです。「世の中には人と話すとMPが回復する人と消耗する人がいて、両者はわかりあえない」といった内容のものですが。
ここでいわれるMPとは、精神力のことと読み取れば良いでしょうか。であれば、前島賢さんは「人と話して精神力が回復するかどうかは人それぞれで、回復する人と消耗する人では溝が大きい」となるでしょうか。
でも実際はどうでしょう? 実体験、精神科臨床、友人談などを総合すると、事態はもっと複雑であるよう思われます。そのあたりについて、もう少し細かく紹介してみたいと思います
ほとんどの人は「人と話すと精神力が回復することも、消耗することももある」
これは、前島賢さんも承知のうえでおっしゃっていたのでしょうけど、実際には、人と話すと精神力(MP)が回復したと感じることもあれば、消耗したと感じることもあります。
たとえば私がオフ会で顔見知りのメンバーと再会する時、私はコミュニケーションをとおして精神力が回復したと感じます。
精神力が回復したと感じる背景には、承認欲求や所属欲求といった社会的欲求がみたされている一面があるでしょうし、インスピレーションが得られたとか、興味深い話を聞いて感心したとか、面白い話を聞いて笑ったとか、そういう一面もあるでしょう。
それらの総合として、勝手知った者同士のオフ会に参加した後には精神力がチャージされたような感覚をおぼえるのが常です。
その正反対は、精神医療の場面で診療面接をハードに続けることでしょうか。
ハードに診療面接を続けていると、私は精神力がすり減っていく思いがします。人数だって多いし、メッセージが伝わらないこともあるし、事態は計画や期待どおりにはそうそう進行しません。泥をかきわけるような診療面接を長時間続けると、精神力をすっかり消耗してしまい、その日は他の活動などできっこない、といった状態に陥ることもが多いものです。
つまり私という一個人だけで見ても、人と話すことをとおして精神力(MP)が回復すこともあれば、消耗することもあるのです。
精神力が回復する対人コミュニケーションも消耗する対人コミュニケーションもある、と言い換えることもできるでしょう。
人間は太古の昔から社会的生物で、コミュニケーションをとりあいながら生きてきました。それを踏まえるなら、きわめて特別な人を除いて、こうしたことは誰しも経験したことがあるのではないでしょうか。
会いたい人と会いたい時に会い、好きな話に興じるぶんには、たいていの人は精神力が回復するものです。反対に、会いたくもない人と会い、しゃべりたくない話を余儀なくされれば精神力を消耗するのが常ですし、タフなコミュニケーション、緊張が過度なコミュニケーションでも消耗しやすいでしょう。
後で触れますが、こうしたことには肉体的疲労も影響するので事態はもっと複雑です。
が、ともあれ、MPにたとえられる精神力は、誰とどんなコミュニケーションをやったのか(あるいは、どんな業務をどんな具合にやったのか)によって大きく左右されるのが常でしょう。
もちろん個人差も無視できない
そこに、冒頭の引用ツイートにもあったような個人差の問題が加わります。
たとえば世の中には、「一人でいる時間がとても大切」と感じる人もいれば、「なるべく人といたほうが楽しい」「一人でいるのは不得手」な人もいます。
一人でいる時間がとても大切な人の場合、より多くの対人コミュニケーションが「精神力を消耗する」と感じられ、「精神力が回復すると感じられる対人コミュニケーション」の割合は少ないでしょう。あるいは、「精神力が回復すると感じられる対人コミュニケーションがないわけではないが、一人でいるほうがずっと精神力回復の効率が高い」ことだってあるかもしれません。
後者の場合、どうせ精神力を回復させるなら一人でいるほうが手っ取り早いので、いつも一人でいる行動様式を発展させがちがちです。
一方、なるべく人といたほうが楽しく、対人コミュニケーションにも慣れている人の場合は、より広範囲の対人コミュニケーションをとおして精神力を回復できるでしょう。そういう人であれば、仕事上の対人コミュニケーション(の一部)からも精神力を回復させることもあるかもしれません。
こうした個人差は、もともとの性格や気質にも左右されますが、対人コミュニケーションへの慣れや社会的経験の多寡、立場の違い、容姿なども含めた魅力の違いなどによっても左右されるかと思います。
MP(=精神力)だけでなくHP(=体力)の問題もある
こんな具合に、対人コミュニケーションが超得意な人と超苦手な人の両極端はともかく、その中間の幅広い人においては、人と会って話すことが精神力の回復に寄与するのか、消耗するのかは一意に定まらない、と思っておいたほうが無難です。
それからもうひとつ。
体力の影響に触れないわけにはいきません。
ネットスラングでいうMP、つまり精神力は、ネットスラングでいうHP、つまり体力によって回復しやすさが大きく左右されます。言い換えれば、精神力(MP)を回復させる際の変数として私たちは自分の体力(HP)のことを常に考えておかなければならないってことです。
精神力の回復/消耗に、体力がどのようにかかわるか、ちょっと考えてみてください。
たとえば人付き合いに慣れた人でも、疲弊しきっている時に友人から遊びに行こうと誘われた時には億劫になってしまうものです。そのような時に無理して再会し、居酒屋あたりで会話をしても、会話をとおして精神力を回復するのも難しいのではないでしょうか。
これは、精神医療における心理療法などにも言えることだと思います。心理療法は、ときにクライアントにとって疲れる部分を含んでいたりしますから、体力が消耗しきっている時にやるのはうまくありません。
重症度の高い抑うつ状態、それこそ食事も睡眠もまともにとれないような状態では、心理療法はうまくクライアントに入っていかないでしょう。体力という原資がなければ、うまくいくものもうまくいかないのです。
ですから、ゲームに登場する架空のキャラクターたちとは異なって、現実の人間の精神力(MP)は体力(HP)に大きく左右される、控えめに言ってもHPとMPは関連している、と考えておくべきでしょう。
体力を消耗している時には、ふだんなら精神力を回復させられるような対人コミュニケーションでさえ、失敗に終わってしまうかもしれません。
この、体力と精神力の関連について考えると、いかに病気が大きなハンディとなってしまうのかが、わかろうというものです。
病気によって慢性的に体力が乏しい状態が続くと、対人コミュニケーションをとおして精神力を回復することも難しくなり、対人コミュニケーションに消極的な気持ちにしかなれないでしょう。すると、精神力の回復手段が減ってしまうのに加えて、人間関係や社交関係もやせ細ってしまい、社会関係資本もガタガタになってしまいます。
うつ病などを経験した人が人間関係や社交関係を喪失してしまう理由の一端は、対人コミュニケーションをとおして精神力を回復できる度合いが病前よりも低くなってしまい、かえって精神力を消耗しやすくなってしまうせいもあるかと思います。
体力が尽きている時、精神力はどう回復させるべきか
そうしたわけで、体力が尽きかけている時に私たちがすべきことは、「休息」だと私は思います。寝ろ、食べろ、休め、ということですね。
まるでうつ病の治療のような話ですが、どんな人にも適用できて、体力に加えて精神力も一定程度回復できる安全牌的選択は休息です。
もともと対人コミュニケーションが好きな人、承認欲求や所属欲求を充たさないと気が済まず、そのためにSNSに張り付きたいと思っている人でも、休息こそが無難な選択肢です。
なかには「休息なんてしていられない」という人もいるでしょう。気持ちはわかるのですが、体力が回復していない状況で無理をするのはおすすめできません。
一応、体力を前借りする方法もあります。たとえばカフェインを適量摂取すれば、疲労がつのっている状況下でも集中力を取り戻し、対人コミュニケーションをとおして精神力を回復しやすい状況を一時的につくれるかもしれません。
仕事などでも、カフェインのおかげで集中でき、結果的に精神的に充実した結果を得た……といった経験のある人はいるでしょう。
しかし、カフェインなどの作用はあくまで一時的で、その実態は、交感神経の亢進や強心作用などをとおして体力を前借りするものでしかありません。カフェインを摂取して元気を前借りした後には一層疲労がたまってしまうのが常です。
そして世の中には、そのどっと疲れた自分自身にもっともっとカフェインなどを投入する危なっかしい人もいたりします。
たかがカフェイン、されどカフェイン。カフェインをとりすぎれば中毒症状をきたすことがあり、特にカフェインサプリメントを異常な量まで飲めば命の危険にさえ直面することがあります。
加えてカフェイン依存という問題もありますから、そういった元気の前借りを日常化してしまうのはやめましょう。
それとはまた別に、承認欲求や所属欲求をみたさずにいられないために休息をおろそかにしてしまう人もいます。仕事なのか、SNSなのか、それ以外の社交関係なのかは色々ですが、世の中には承認欲求や所属欲求をみたしたいニーズが高く、それがために体力の低下をおしてでも出かけてしまう、頑張ってしまう人もいます。
さきほど書いたように、体力が低下していれば対人コミュニケーションをとおして精神力を回復するのは難しくなるので、そういう人こそ、体力が低下している時は休息を心がけ、たとえばSNSなど放置しておくべきなのですが、えてしてそういう人はブレーキがきかなかったりします。
そういう人には、「あなたは体力が減っているから、まずは体力を回復させるのが先ですよ」と言ってくれる人(そして、この人の助言だったら受け入れられるという信頼関係)が大切なのだと思います。
まとめ
今日の話を三つのセンテンスでまとめましょう。
・人と話すと精神力(MP)が増えるか減るかは、話す内容。状況によって左右される
・もちろん、その人の性質や気質によっても左右される
・体力によっても左右される。その体力の一番無難な回復法は「休息」
このように、対人コミュニケーションをとおして精神力が回復するか否かを左右する因子はいろいろあり、その前提で考えてみると良いように思います。
そして体力が低下すると、精神力の回復に限らずいろいろなハンディがついてまわるので、疲弊している時には無理は禁物です。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【プロフィール】
著者:熊代亨
精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。
通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(イースト・プレス)など。
twitter:@twit_shirokuma
ブログ:『シロクマの屑籠』

Photo:Glen Bledsoe