企業は従業員に対して、労働力の対価として、報酬を払っています。
しかし中には報酬を受け取りながら
「依頼された仕事を、一向にやらない人」
も事実として、存在しています。
「クビにすればいい」という方もいるでしょうが、企業は彼らを雇った責任がありますし、人を活かすという社会的な役割もあります。
企業は決して、人を解雇するのが好きな訳ではありません。
しかも、日本では法律的にも倫理的にも「解雇してしまう」というのは本当に最後の手段ですから、あの手この手で、彼らを戦力化しようとするのが常です。
そういうとき、企業はまず注意をしたり、叱ったり、責任感に訴えたりします。
実際、「言うだけ」でなんとかなるケースもあります。
しかし、そうではないケースのほうがむしろ多数です。
その場合、企業は「仕組み」からアプローチして、なんとかしようとします。
教育。
配置転換。
他の社員によるアシスト。
ですが、たいてい徒労に終わります。
そうして「本当にやらない人は、何をやっても、どう助けても、結局やらないし、それは直らない」ことが、周りの人間に、徐々にわかってくるのです。
「依頼された仕事をやらない人」に対して、仕事をやらせるために
・タスク管理ツールの導入
・進捗の細かなチェック
・積極的なヘルプの申し出
・仕事の負荷の調整をしたとしても、大体は「結局やらない」。
やらない人は、何をやっても、どう助けても
結局やらないし、それは直らない。— 安達裕哉 (@Books_Apps) March 8, 2024
一体なぜ、このようになってしまうのかについては、以前に書いたことがあります。
「依頼された仕事をやらない人」は、なぜあれほど言われても、仕事をしないのか
「依頼された仕事をやらない人」は、なぜ仕事をしないのか。それは、知性の欠如でも、努力ができないわけでも、意欲がないわけでもない。
単に「色々考えるのが嫌」という、もう少し根の深い部分に、課題がある。
彼らの仕事が進まない理由には、本当に様々な理由があります。
ですが、突き詰めて言うと彼らは「頭を使うのがきらい」なのです。
運動がきらいな人、歌うのがきらいな人、人前で喋るのがきらいな人。
彼らと同じくらい、「頭を使うのがきらいな人」は、数多くいます。
だから、誤解を招かないように申し上げたいのですが、これは「頭が悪い」とは全く違います。
仕事ができなくても、頭の良い人はたくさんいます。
そうではなく「頭を使うのがきらい人」は、正確に言えば「頭を駆動させるのがきらい」なのです。
なぜかと言えば、頭を使うと、彼らはすぐに疲弊してしまうから。
つまり精神的なリソース、いわゆるMPをすぐに使い切ってしまう人々なのです。
だから、教育やツールなどの仕組みでも解決できません。
配置転換も無意味なことが多いです。
彼ら自身が「好きで自分に合っている仕事です」と言っても、多少面倒なことが起きると、もう彼らは仕事をしません。
MPが尽きてしまうからです。
「MPを消費しない仕事」しか、やらせることができない
このような話は、故小田嶋隆さんが、「アルコール依存症の自分」について書いたコラムで、とても解像度高く紹介しています。
「お前はとにかく死ぬまでこの単語帳を丸暗記するんだ」という課題を外部から与えられると、案外できたりします。
私は受験勉強も結局、高校に通っていた間は丸三年間一瞬たりとも勉強しないで、それはそれはひどい状態になっていた。
浪人して、ある日、「さあ始めるぞ」ってなことになって勉強を始めたら、その日から一日に一三時間勉強するみたいな勢いで丸暗記に励みました。それでダーっと成績が上がって、大学に合格すると、とたんにこれがまた勉強しなくなってしまう。
なぜそういうふうに極端に振れるのかというと、別に私が極端な人間だからではなくて、自分の暮らし方だとか生き方についてその都度その場面に沿ったカタチで考えることがとにかく大嫌いだったから。
要するに、ある種人工的だったり習慣的だったりする指針に従うほうが本人としては楽だったということです。
酒を飲むという行為は、そういう立案を嫌う人間が依存しやすい生き方だと思います。
いろんなときに「ま、とにかく飲んじゃおうよ」というのがいいプランに見えたんだと思うんですね。私にかぎらず、人間は「人生を単純化したい」というかなり強烈な欲望を抱いています。たとえば念仏とかも、単純化の極みじゃないですか。
・「1日13時間、死ぬまで単語帳を丸暗記」はできる
・人工的だったり習慣的だったりする指針に従うほうが楽
・念仏のように人生を単純化したい
こうした特性は、いずれも「依頼された仕事を、一向にやらない人」という特性に良く合致します。
つまり彼らには、本質的には「MPをあまり消費しない仕事」しか、やらせることができない。
わずかなMP消費で、クリエイティブなことをやってのける一部の天才もいますが、大抵は転記作業、定型的な反復動作、マニュアル通りの応対など、「考えさせたらダメ」だと思って、仕事を割り振らねばなりません。
ただ、「そんな仕事、多くないよ」と思う方は多いでしょう。
「それなら社員ではなく、アルバイトで十分」と考える経営者もいるでしょう。
まさに、それが現代社会の大きな課題の一つです。
昔は、MPを使わない仕事がそれなりにありました。
高度経済成長時は、「作れば売れる」のだから、余計なことを考えずに、目の前の仕事をとにかくこなせば、何とかなりましたし、サービスも単純だった。
ところが現在は違います。
消費者の欲求を満たすために、現代の仕事は複雑、かつコミュニケーション気を配る必要があり、「稼げる仕事」は、大量にMPを必要とする仕事ばかりです。
私もMPは特に高い方ではないので、「とにかくやれば終わる仕事」をやる時には本当に気が楽です。
経理や数字のチェック、大量の封入の作業、エクセルの入力などは、とにかく手を付けさえすれば「終わる」ので、救いがある。
しかし、企画をつくったり、提案をつくったり、論理を組んだり、アイデアを必要とする仕事は、時間をかけたからといって、「終わる保証」が全くないのです。
試行錯誤を必要とするこれらの仕事は、MP消費量がが全く違うので、ツラい仕事です。
*
先日、Youtubeを見ていたところ、岡田斗司夫氏の「ベーシックインカム」に関する言及が目に留まりました。
Amazon創業者の、ジェフ・ベゾスはベーシックインカム推進派です。
良いことのようにも思えますが、その真の理由は
「ビジネスは有能な者たちとAIだけでやるから、お前ら(無能)は面倒くさいから社会に出てくるな」
だと、彼は言います。
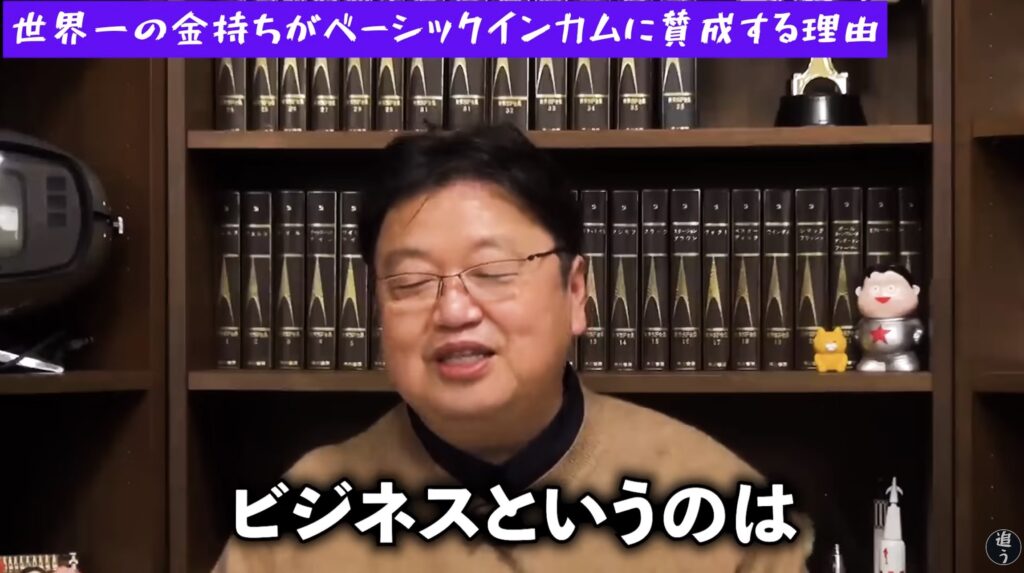
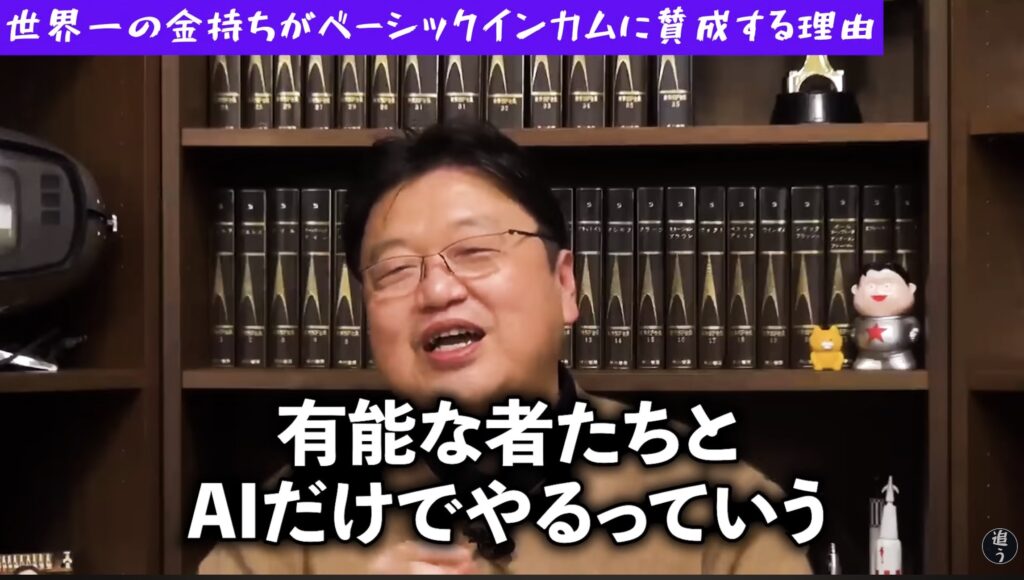
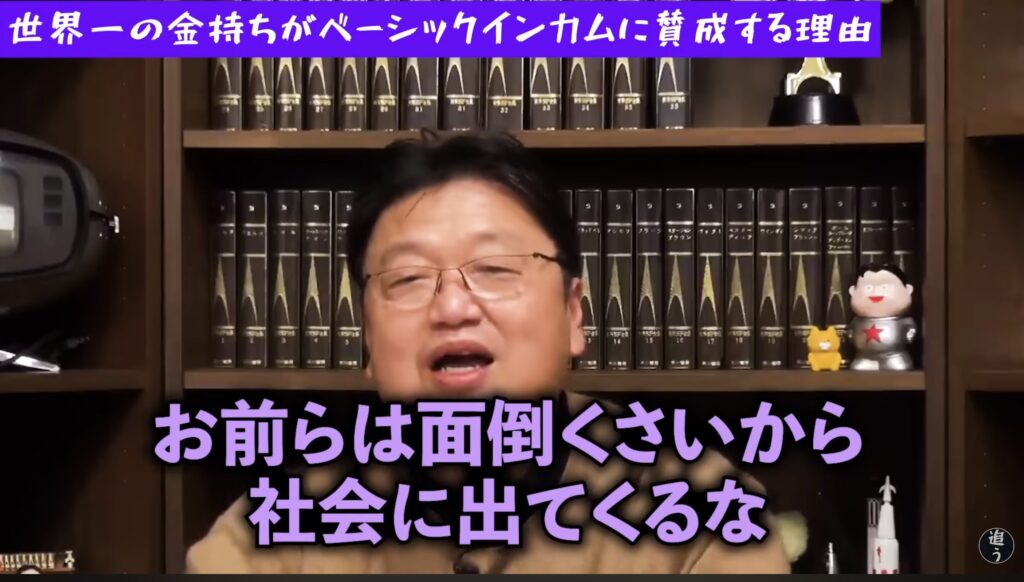
これはある意味、「仕事ができない人を、企業が救う事は無理」という宣言でもあります。
確かに、企業は慈善団体や公共機関ではありませんし、高度なサービスを提供している会社は、ますます有能な人間(あるいはAI)を必要としていますから、当然の帰結なのかもしれません。
となると、これは政府や非営利団体の出番です。
ベーシックインカムは、その一つの解決方法かもしれませんが、「社会に出てくるな」というのも、解決になっているかと言うと、微妙です。
そういう意味では、4500年前のピラミッド建設のように、「社会的な大義があり」「MP消費の少ない」を作りだすことが、公共の役割、そして治安維持の良い方法なのかもしれません。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
安達裕哉
生成AI活用支援のワークワンダースCEO(https://workwonders.jp)|元Deloitteのコンサルタント|オウンドメディア支援のティネクト代表(http://tinect.jp)|著書「頭のいい人が話す前に考えていること」55万部(https://amzn.to/49Tivyi)|
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯note:(生成AI時代の「ライターとマーケティング」の、実践的教科書)
Photo:brut carniollus














