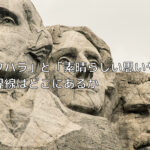タイトルですべて言い切ってしまっているのですが、補足します。
少し前に、こんな記事を見ました。
東大・理科三類に現役合格。「質は圧倒的な量の上でしか担保されない」と、彼が挑んだ参考書の膨大な冊数は?
「量より質って言う人がいるけれど、質ってのは圧倒的量の上でしか担保されないから」
これを読んで、「まあそうだよね」というビジネスパーソンは多いのではないでしょうか。
特に、最前線で頑張っている人ほど。
ただし、ビジネス上はもう少し異なる言い方をしたほうが、正確かもしれません。
わたしが若いときに先輩から言われたのは、以下のような言葉でした。
「「質で勝負」とか言っているうちは、二流。」
なぜこのようなことを言ったのか、私は先輩に聞きました。
「あえて言いますけど、質を高くして、効率を高めたほうが、業績あがりそうですけど。」
すると、先輩は言いました。
「それは別に間違ってないよ。」
「じゃなぜですか?」
「カンタンだよ。「時間をかけず質で勝負」、つまり効率よくやれる仕事って、自分が過去にやり方を見出したか、誰かがやり方を考えてくれた仕事でしょ?」
「まあ、そうです。」
「それって、過去を踏襲しているか、あるいは人から言われた通りやるだけだから、その人は兵隊ってことでしょ?」
「まあ、否定はしませんけど……。」
「まさか、それで一流だなんて、言うつもりないよね?」
「……。いえ。」
「新人なら、効率のいいやり方を追求させてもいい。平凡なサラリーマンなら「過去にやったこと」「人から言われたこと」をなぞるだけでもいい。」
「はい。」
「でも、一流、ってのは未知の領域で、新しいやり方、新しいビジネスを作るひとのことでしょ?30過ぎてそんなこと言ってたら、二流だといわれても仕方ない。」
*
先輩の言い方は、気持ちのいい言い方ではないと思いましたが、言っていることの中身は間違ってはいない、と思いました。
つまり質で勝負する「効率よくやれる世界」は、いうなれば「何をすればよいのかわかっている世界」です。
つまり不確実性が低く、アウトプットもはっきりしており、「効率」を計測することができる。
しかし、新しいことをすればするほど、あるいは大きく成果を出そうとすればするほど、「何をすればいいのか」は、はっきりと事前にはわかりません。
やり方は確立されておらず、あれこれ試して、徐々にうまいやり方を見つけていくしかない。
しかし、そこへいたる道は厳しいものです。
10回試して、うまいやり方が見つかるのはせいぜい1つ、2つつくらいでしょう。
そもそも、すべて徒労に終わるかもしれない。
「未知の領域」で効率は計算ができないのです。
だからそこは「効率の良いやり方」を見つけるためにも、量をこなすしかありません。
身銭を切って、実験する。
言い換えれば、量で勝負する世界は、フロンティアです。
だからそれは「一人前」だけに許された世界でもあります。
少し前にこんな記事を書きました。
「結果を追求する」なら、つべこべ言わず、「やるべきこと」は、一切の躊躇なく「やらねばならない」。
ビジネスをやる、商売をする、とは結局そういうことなのだ。
結局、ビジネスの世界は、上に行けば行くほど、結果でしかものを言うことが許されません。
だから、常に改善が求められる。
「効率よく」と言う言い方は、聞こえはいいですが、先輩からすれば、それは過去を肯定するだけの一種の「甘え」と見なされたのでしょう。
もちろん「ビジネスで成功したい」という人以外には、別にどうでもいい話なのかもしれませんが。
ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>
第6回 地方創生×事業再生
再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】
ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。
当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。
【今回のトーク概要】
- 0. オープニング(5分)
自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)
保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)
再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)
経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)
「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)
数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)
経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”
【ゲスト】
鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏
ExePro Partner代表 経営コンサルタント
兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。
高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。
卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。
株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。
その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。
現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。
【パーソナリティ】
倉増 京平(くらまし きょうへい)
ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事
顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。
コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。
ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。
(2025/7/14更新)
【著者プロフィール】
安達裕哉
元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)
頭のいい人が話す前に考えていること
- 安達 裕哉
- ダイヤモンド社
- 価格¥1,650(2025/07/14 10:05時点)
- 発売日2023/04/19
- 商品ランキング187位
Photo:Clay Banks