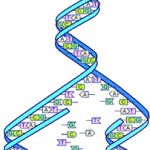かつて「ワンランク上の勉強法」というサイトで”わからん科目攻略法”というものが紹介されていた。
これは非常に有用な技術なのだが、現在はジオシティーズの閉鎖に伴い閲覧不可能である。。
このまま埋もれてしまうにはあまりにも勿体ないので簡単に紹介し、今日はその技術を土台として自分の頭でモノを考えるという事がどういう事なのかを書いていこうかと思う。
最近全然頭使ってないなという人には参考になるかもしれない。
難しい概念にぶち当たったら、理解しようと思わないで10回読め
あなたが物理の勉強を始めたと仮定しよう。
物理は難しい。
分野によっては一読しただけでは何が書いてあるのかサッパリ理解できない事も多い。
高校生の頃に早々に脱落してしまった人も多いだろう。
この難しい科目を”わからん科目攻略法”は「理解しようと思わずに毎日ただ目を通して10回ぐらい読め。そんで11回目にわかろうと思って読め」と説く。
こうすれば驚くほどスルスル理解が進むというのである。
「読むだけ?ウンウン唸って頭をフル回転させて理解しようとしなくていいの?」と思われるかもしれないが、それで問題はない。
そんな感じで10回ぐらい字面を追うように読み、11回目ぐらいで「さて、どんな事が書かれているかな」と”理解”しようと意識して読むと、不思議な事に驚くほど簡単に理解できる。
「なにそれ?そんな事ありえるの?」と思われるかもしれないが、これはマジだ。
実際、僕以外にもこの手法で数学や物理をハイスピードで攻略した知り合いが何人もいる。
”わからん科目攻略法”は物理以外の全てに使える魔法のような技術で、今でも僕は難しい英語の論文を読む時などでよく使っている。
例えば寝る前にザサっと目を通しておいてから翌朝になってから読むと、驚くほどスルリと論文が読めたりする。
無意識に学習させる
”わからん科目攻略法”の秘密は恐らく無意識の作用によるものだ。
寝る事で記憶が整備されるという現象は有名だが、実際は寝ていない時でも脳は知識の整理整頓や概念理解を水面下でやってくれている。
誰だって全然理解できなかった事がある日突然理解できて「なんでこんな簡単な事が今までわからなかったんだろう?」となった事があるだろう。
あれは無意識が脳の中で情報を整理してくれた事の恩恵に他ならない。
無意識は皆が思っている以上にかなり丁寧に脳内の情報を処理してくれる。
多くの人は無意識をヒラメキのような発想を生み出すものと思っているが、むしろ本当の本領は理解の促進だとか環境への適応の方だろう。
英語圏に放り込まれた人間が英会話を習得したり、新卒社員が2~3年して一端の社会人になったりするのも恐らくこの効用が大きい。
とにかく目の前でナマの情報を仕入れ続けるのが何よりも肝心で、それさえやってれば無意識が勝手に貴方を引っ張り上げてくれる。
自分の頭で考えるとは、脳に知識を抱えさせる事
学習する人間はこのように知識を常に脳に抱えるような状況下にある。
このような状態にあると脳は無意識下でかなりモノを考え続ける事になる。
結果、知識が色々な形で結びつき、自然と様々な意見が溢れ出るようになる。
これがいわゆる“発想”と言われるものの正体だ。
よく「若い人は頭が柔らかい」というが、僕が思うに若者の頭が柔軟なのは無意識が常に全力疾走して考え続けているからである。
若者は知識や経験が乏しい。
故に様々な情報を脳に与え続ける事になる。
これが意図しない形で無意識にモノを考えさせるよう作用しており、その副産物が”発想”となって現れているのである。
大人は反射で生きてて、ラクをしている
一方、多くの大人は無意識が全然働いていない。
これは単に全く勉強しなくなったというのもあるが、むしろ問題はできる事だけで人生を回せてしまう事にある。
人は若い頃は何もできない。
だから生き抜く為にも脳に必死になって情報を詰め込む。
こうすると無意識がフル回転し続け、脳は驚くほど多くの情報を処理し続ける事になる。
だが、ある程度成長するとその必要性が薄まってしまう。
できる事だけで人生が回せてしまうから、新しい事を脳に詰め込むインセンティブが無さすぎるのだ。
そうなると自然と無意識は知識の整備などを行わなくなるから、結果として無意識の働きがどんどん鈍化していってしまう。
反射は脳に負荷を与えない
このように人生は必然的に無意識が錆びつくようにできている。
物事に習熟するという事はどんどん脳で考える事から脊髄反射でもって行動するという事にシフトするという事でもある。
脊髄反射も無意識の為せる素晴らしい御業だが、残念ながらこの回路は無意識にあまり負荷を与えない。
こうして無意識に負荷がかからなくなった脳からは柔軟な発想や面白いアイディアなどがでなくなる。
中年以降になって一部の大人が急激につまらなくなるのは、無意識を稼働させず反射だけでラクして生きてしまっているというのが非常に大きいのではないかと僕は思う。
脳を使わず、脊髄だけで生きていれば、そりゃそうなるってもんだろう。
反射はラクをするという事である
反射でもってラクに生きられるようになるという事は、柔軟な思考回路を捨てるという事のコインの裏面のようなものだ。
無意識に負荷を与える事は苦労するという事にも等しい。
反射でもってできる事だけをやるという事はそれの真逆の行いで、ラクをしているのだからその代償として発想力が落ちるのも仕方がないといえる。
僕は反射でもってラクをするのが悪いというつもりは無い。
人生は塩梅が肝心だ。
ラクをするのも生き抜くにあたっては大切な事で、特に仕事なんてさっさと慣れてしまった方が絶対にいい。
反射の問題点は楽しすぎる事にある
ただ反射には問題も多い。
その1番の問題点は反射があまりにも楽しすぎるという点にある。
例えば仕事を猛烈なスピードでもって処理するのはかなり楽しい。
その逆である、不慣れな時のモタモタしている時の苦しみの対偶関係のようである。
仕事ならこんな感じで反射でもって処理をしても全然構わないのだが、実はこの反射による蠱惑的な罠は日常生活にかなり多く仕込まれている。
例えばテレビをみて悪態をついたりするのはとても楽しい。
政権批判や芸能人の不謹慎なニュースにコメントをつけるのは愉悦のひと時といっても過言ではない。
世の中を見渡すとこの手の反射を煽るコンテンツがかなり多い事に気がつく。
政権批判やゴシップニュースだけではなく、韓国人など特定の集団が悪いという結論ありきの論調だってその一つである。
あれらが提供しているものの正体は反射で、あれは人の頭を酷く馬鹿にする。
なにせ結論がほぼ決まりきっているのだから、知恵を働かせる場所がない。
反射はものすごくラクだし何よりも楽しい。
だからそれにハマる気持ちはわからなくはない。
だけど…反射だけで人生を構成してしまうのは、さすがにちょっとやりすぎだ。
少しだけでもいいから頭を働かせる機会は作った方がいい。
ではどうすればいいのだろうか。僕はその鍵は個人研究にあると思う。
個人研究のススメ
「無意識に負荷をかけたいのなら、大人になってから学び直しをしたり新しいアクティビティを始めればいいんじゃないの?」
こう思われた方は当然いると思う。
もちろん、できる人はそれでいい。
ただ…僕が思うに、これは言うは易く行うは難しの代表例みたいなもので、多くの人は実行困難だ。
それよりも個人的には個人研究をしてみるのがオススメだ。
研究はとても楽しい。
実際の研究は結構大変だが、こと個人でやる分には面白さしかないといっても過言ではない。
例えば映画を一本みて、何らかの感想を持ったとしよう。
そしたらその感想が何故生じたのかを、ずっと粘り強く考え続けてみよう。
映画をみて「面白かった」とか「スカッとした」、「つまらなかった」といった感想を持つのは単なる反射だが、その感想がどうして生じたのかを粘り強く考え続けると、色々なものがみえてくる。
この映画が楽しかったのは「あの俳優の演技がよかった」からだとかとか「ストーリーが面白かった」からだだとか、そういう風に一つのものを粘り強く考え続けていると、思考が広く展開し、様々な仮設が思い浮かぶようになる。
すると次々に色々と気になる事が出てくるはずだ。
例えば俳優の演技が気になったのなら、その俳優の他の仕事について調べてみるのもいいだろうし、ストーリーが面白かったというのなら映画監督の他の作品を調べてみるのも良い。
そうして調査を展開させてゆけば、自然と様々な情報に触れる事になるだろう。
そうやって情報をどんどん有機的に結合させていくと、次第にあなたの頭の中にユニークな意見が形成されてゆく。
あとはそれを上手にまとめ上げさえすれば、もう立派な個人研究といっても過言ではない。
複数回それをやれば、今度は自分の成果を比較して改善すべき点がみえてきたり、他の人がやっている事を参考にしてみたりできるようにもなるだろう。
誰も言っていないような意見が形成できるようになってくると、個人研究は俄然と面白さが増してくる。
ユニークな意見の形成は”反射”では絶対にできないもので、それができるという事は自分の頭でモノを考えているという事とほぼ同義である。
題材は何でもいい。頭に抱え続ける事が大事
先程は映画を例にあげたが、別に興味のある事なら何でもいい。
例えば牛丼が好きならば牛丼を食べて、いろいろ考えるのも一興だ。
吉野家と松屋の味の違いが何なのかを、牛肉と玉ねぎ、米、味付け、紅生姜など様々なファクターで分析してみるだけでもそれは立派な個人研究として成立する。
各社の売り上げを地域別に比較してみて、地域住民の好む味の傾向などを推察してみたりするのもいいかもしれない。
このように、やれる事は無限大である。
食べて感想を述べるだけだと単なる”反射”だが、そこから一歩先に進んで仮説をたてて、それを様々な角度でもって”意見”としてまとめようとすると粘り強く色々考える必然性が生じる。
そうして展開した思考から生み出される”意見”は”反射”では絶対に出ない味わい深いものとなる。
自分の頭でモノを考えるのはとても楽しい。
現代はインターネットがあるから、発表の場に困ることもない。
まさに国民総研究時代の到来といえよう。
なお研究の手法を参考したいのなら”大学で学ぶゾンビ学~人はなぜゾンビに惹かれるのか~”がオススメだ。
ゾンビを題材にこんなにも思考を展開できるのかと、驚くこと間違いなしである。
個人研究は脳を使うには実に都合のいい手法である。
勉強ほどには大変ではなく、反射よりかは脳にいい負荷がかかる。
ちょっとしたポイントを抑えるだけで、自分の興味が赴くままに行動し続ければ脳がハツラツとする。
暇な人もそうではない人も、ゆっくりと始めてみてはいかがだろうか?
自分の力で新しい真実を開拓する事の悦びを知る事で、ゆっくりと反射の沼から脱却しよう。
人生を無駄にするのも、有意義にするのも、全てはあなた次第なのである。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
都内で勤務医としてまったり生活中。
趣味はおいしいレストラン開拓とワインと読書です。
twitter:takasuka_toki ブログ→ 珈琲をゴクゴク呑むように
noteで食事に関するコラム執筆と人生相談もやってます
Photo by Pawel Czerwinski