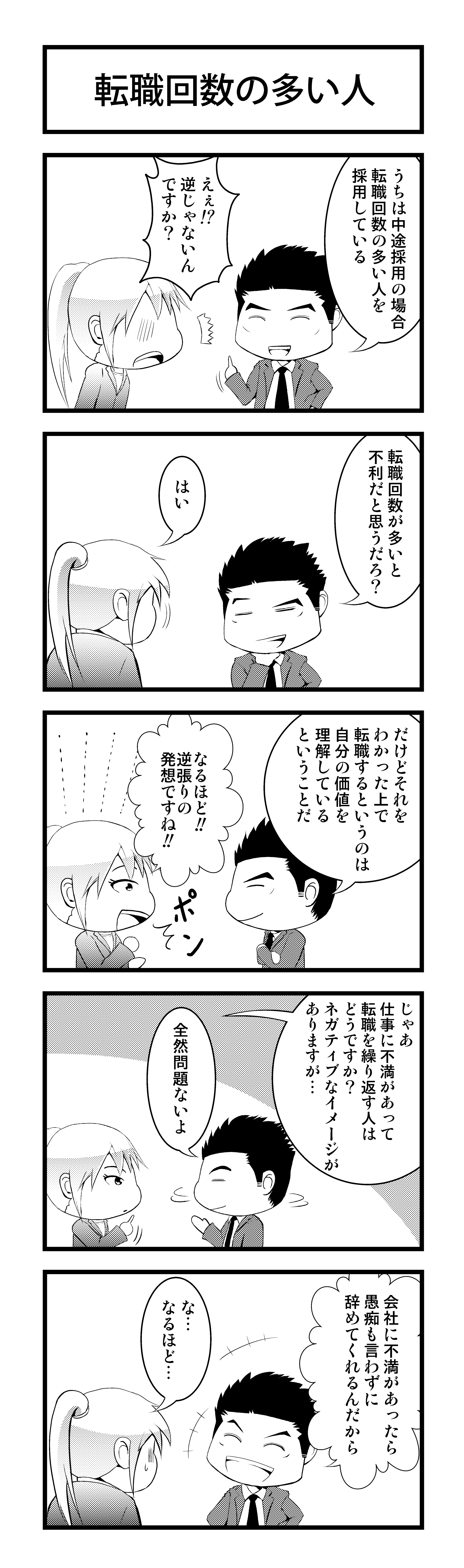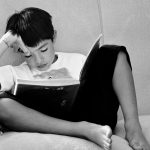『桃太郎』という作品をご存知だろうか?川に流れていた桃を叩き割るとそこにエスパー伊藤かの如く怪しげな人間が潜んでおり、その人間が動物の力を借りて鬼を一匹残らず抹殺するという、有名な作品だ。
この桃太郎という作品は完成度の高い創作物語として一定の市民権を得ているが、一つだけある深刻な問題を抱えている。それは、川へ洗濯に出向いたお婆さんが桃を見つけるあの有名なシーンにおける、桃が流れてくる様を言い表した不気味な擬態語、「ドンブラコ、ドンブラコ」である。
作中では特段の注釈もなく、何事もなかったかのように「桃がドンブラコと流れてきました」と書かれているが、一方、現実問題として、「ドンブラコ」などという謎の日本語は、この桃太郎という物語以外では全く聞いた事がない。ドンブラコ。桃がドンブラコ。
それまで気持ちよく桃太郎を読んできた読者は、この突然の「ドンブラコ」で置き去りにされてしまう。「ドンブラコ」って何だ。「桃がドンブラコ」って、どういう状況なんだ。
桃の登場シーンにおいて定番チューンかのように流された「ドンブラコ」というBGMが、実は誰も聞いたことのない狂気のワルツであるという事件。これが俗に言う、“ドンブラコ問題”である。
「桃がドンブラコ」という奇をてらったワーディングの衝撃は凄まじく、この独特のフレーズを目にするや否や、多くの読者はパニックに陥ってしまう。ど、ど、…ドンブラコ?!
平易な言葉のみで構成された分かりやすい文章の中にあって圧倒的に異彩を放つドンブラコ。孤高のドンブラコ。Amazing DONBRA-CO。
無論、ドンブラコの覇気に押しやられ、その後の物語は、読めども読めども頭には入って来ない。鬼ヶ島なんてどうでも良い。そんなことよりも、桃は一体、どんな風に流れてきたんだろうか?やはり、きびだんごも、ドンブラコと渡したんだろうか?キジは、ドンブラコと飛んだのだろうか?お爺さんとお婆さんは、末永くドンブラコドンブラコと暮らしたんだろうか?
このドンブラコという日本語が、万が一、「桃が流れてくる時」にのみ使うことの許された擬態語なのだとしたら、その汎用性の低さたるや常軌を逸している。あらゆる日本語の中で、最も使用機会に恵まれない単語だと断定して良いだろう。
思い出して欲しい。あなたが日常生活を送る中で、「桃が流れてきた」なんてことは、一度でもあっただろうか?ない。ないだろう。少なくとも筆者のこれまでの人生において桃は一度も流れてこなかったし、今後も流れてくることはない。そんなシーンに出くわしたければ、桃を自発的に、積極的に「流す」しか方法はない。こんなに汎用性の低い単語が存在するなんてことは、ありえない。
であれば、ドンブラコというのはやはり、桃の流れる様を描写する以外に、何か他に使い道があるのだろうと推測される。日常生活で、とても自然に、違和感なく「ドンブラコ」という表現を使うことが出来る。ドンブラコに適したシーンがある。筆者の考えでは、例えば以下のようなドンブラコがありえる。
「月例の予算会議、山田はまたしてもドンブラコドンブラコと居眠りを始めた。」
…そう、「グーグー」や「グウスカ」といった低次元の眠りを超越した豪快な眠り、それこそがこのドンブラコ睡眠。信じられない程のイビキをかき、寝返りをうち、大声で寝言を言いながら爆睡する様、そう、その姿まさにドンブラコ!
「こめかみに銃を突きつけた齋藤は、無慈悲にもその引き金を引いた。…ドンブラコッッ!!!!銃声が鳴り響き、山田は血しぶきをあげ、肉塊となった。」
…「バンッッ」では表現しきれなかった、銃声のあの、鈍く響き渡る感じ。銃弾が脳を裂きグチョっと体液が出てくるイメージをも想起させる、残酷な銃声、ドンブラコ。 マシンガンのような、連続した銃声を表現したいのであれば、「ドンブラブラブラブラブラブラブラブラコッ!」という具合に、「ブラ」を増やしていけば良いのだ。
「おお〜っと、横浜ベイスターズ、ここで8番の山田に代わり、代打、ドンブラコです。長打力のあるドンブラコがバッターボックスへ向かいます。」
…その黒人、なんと身長は2.1mで体重は165kg。恵まれた体格から繰り出される豪快なホームランで観客を魅了する、本格派外国人助っ人。打率1.9割にして、年間のホームラン数はなんと66本。長打率94%。ホームランの最大飛距離は233m。そう、彼こそがハマの巨神兵、南半球の打ち上げ花火、ベイスターズの破壊神、オドリック・ドンブラコだぁぁああああアアッッッ!!!!!!
桃太郎を読んだ後、読者の頭に残るのは鬼でもキジでも無く、ただドンブラコという独特な単語それのみである。「ドンブラコって、自分が知らないだけで、実は一般的に使われてる単語なのかな…?」
桃太郎という作品にはドンブラコという地雷が設置されており、それにより読者は自らの無知を疑い、恥を恐れる。その単語が、気になって気になって、仕方が無い。
それからと言うもの、生活のあらゆるシーンにおいて無意識にドンブラコを探してしまう自分に気付くだろう。あ、ドンブラコって、ここで使えるのかも?あ、いや、こっちの方がドンブラコはシックリくるかな?いや、こっちの方がドンブラコ感あるかな?ドンブラコ、ドンブラコ。
嗚呼、本当のドンブラコは、真実のドンブラコは、一体どこにあるんだい?
詰まるところ桃太郎という物語の真髄は、「物語を読み終えた後に、ようやく物語が始まる」ことにある。桃太郎が鬼を倒すというまやかしのエンディングを経て、読者は遂に、それぞれの旅に出ることを許される。自分だけのドンブラコを、未だ見ぬドンブラコを探す旅。
彼らは想像力という名の船に乗り込み、広大な言葉の海を進んでいく。ドンブラコ、ドンブラコと。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
—
紹介 :インターネットという公共の場に糞尿のような記事をせっせと投下して1人で大喜びしている性犯罪者は、この私です。