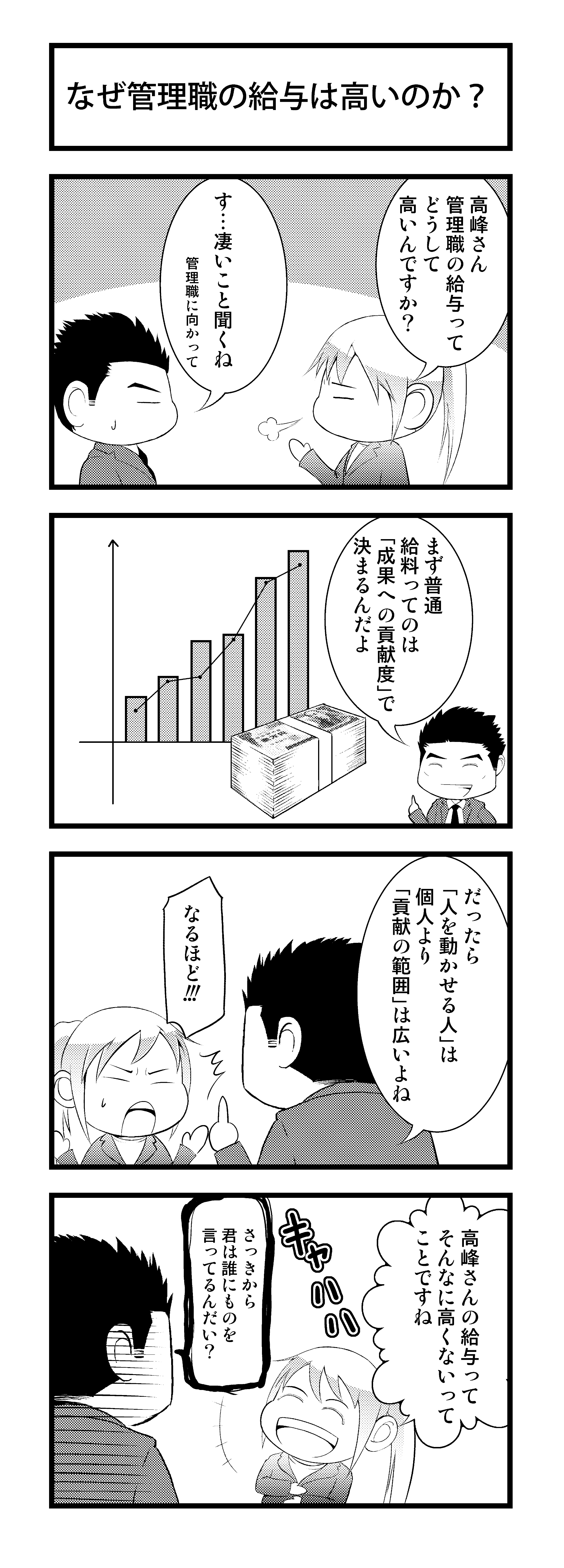wiredで、衝撃的なニュースを見た。
一時期かなりの話題となったスタートアップに関する報道だ。
ジョブズになり損ねた女:DNA検査の寵児、エリザベス・ホームズの墜落
称賛と金とを集めたバイオテックスタートアップ、セラノス。
『Vanity Fair』の記者ニック・ビルトンによる徹底的な取材から、若き創業者エリザベス・ホームズは「指先からの血液1滴で
すべてがわかる」と謳った血液検査テクノロジーの信頼性について、同社チーフサイエンティストら医療専門家の意見を無視し続けてきたことが判明した。(Wired)
端的に言えば、一滴の血液で、血液検査ができるとの触れ込みで、多くの注目と資金を集めたが、実際には中身がなく、詐欺同然であった、という話だ。
彼女を褒め称え、持ち上げたForbesらのメディアは面目丸つぶれだ。Forbes紙は、経営者であるホームズ氏を「成功モデル」として取り上げた誤りを認め、「米国で最もリッチなたたき上げの女性」のリストからホームズを抹消したという。
医療と言えば、日本でも積極的に推し進めている会社がある。DeNA社だ。
だが先日、DeNA社のサイトが相次いで閉鎖した。
ディー・エヌ・エー(DeNA)は、著作権侵害などの問題が指摘されている医療情報サイト「WELQ」を含む9サイトを11月29日から相次ぎ非公開とした。
7日に同社のキュレーション事業では主力の女性向けサイト「MERY」も非公開とすることを決めた。月間利用者数がのべ約1億5000万人に上る10サイトが非公開となる異例の事態となった。法律上では何が問題に当たり、サイトの運営者はどのような責任を負うのか。(日本経済新聞)
発端は、医療情報に関してDeNA社がアチラコチラのwebサイトからの不正確な情報を切り貼りしただけのコピペサイトを粗製乱造したため、批判を浴びたことだった。
一時期これらのサイトは利用者を欺き続け、巨大なトラフィックを集め続けたが、結局はサービス停止に追い込まれた。
セラノスとDeNA、やっていることは違えど、その思想は酷似しているように感じる。
大きな注目やトラフィックを集めても、結局ダメなものはダメなのだ。
————————–
だが、我々は本当に彼らを嗤えるだろうか。
拡大を急ぐあまり、中身と責任感のないサービスを推し進めてしまう話は、あまりにもありふれている。
思い起こすと、一昔前、あるWebサービス立ち上げプロジェクトに途中から参加したことがあった。
「経営者の肝いりプロジェクト」だったそのサービスは、大きなシステム開発投資を行っていたが、どうにもうまく立ち上がらず、「うまく売って欲しい」と依頼があったためだ。
しかし、見ると問題があるのは明らかに営業やマーケティングではなく、商品そのものであった。同様のサービスで、低価格で機能も豊富な競合製品がいくらでもあったのだ。
もちろん「これは営業の問題ではなく、商品の問題ではないか」との指摘は他のメンバーからも相次いで出されたが、上層部は「これだけの投資をしたのだから売れないほうがおかしい」と、それを撥ね付けた。
結果として、中身がないのに、売り込みと宣伝だけは素晴らしい、というサービスが、会社の「売上目標」という都合で無知な顧客に売りつけられた。
当然の事ながら、サービスは数年も経たずに「なかったこと」となった。
一方で、Googleは、これらの会社と全く反対の立場を取る。
企業が成功を続ける唯一の方法は、プロダクトの優位性を維持することだ。だからプロダクト戦略に関するグーグルの最も重視するルールはユーザーに焦点を絞ることだ。(中略)
利益が出るまでにしばらく時間がかかることもある。だからこの方針を貫くには、相当な信念が必要だ。ただ、間違いなくその価値はある。*1
結局のところ「商品が突き抜けていること」は売れる商品の数ある条件の1つでなく「前提」となった。
「必死に活動する営業」が、半ば顧客を欺いて売りつけてしまった商品が、結局会社の評判を下げてしまうのだ。
かつて、webがこれほど広く利用されていなかった時代、個人や一介の中小企業が発信する手段を持たなかった時代は、資本で評判をコントロール出来た。
一部のユーザーが不満を持とうが、マスメディアに金を出せば、評判をある程度保つことができたからだ。
だがいまはそうではない。
評判やプロダクトの欠陥を糊塗しても、結局すぐにユーザーの中でそれが広まってしまう。
アップルの創業者の一人である、スティーブ・ウォズニアックは、「マーケティング会社てなんてまっぴら」と述べた。
(マーケティング)委員会なんかが画期的なものを生み出せるわけがないよ。合意が得られるはずがないからね。
なぜエンジニアはアーティストににていると思うのかって?エンジニアは自分で想像もしていなかったほど完璧なものを作ろうとすることが多いからさ。部品の一つ一つ、配線の一本一本、すべて意味があるんだ。(中略)
画家が絵筆で色を重ねていくように、あるいは、作曲家が音符を重ねていくように。そして、完ぺきを求める努力、だれもやったことがない形であらゆるものを完璧に組み合わせる努力、これこそが、エンジニアであれだれであれ、真のアーティストを生み出す源泉なんだ。*2
営業、マーケティング、広報活動と言ったものは、事業の主従関係においては「従」に過ぎない。
それが逆転した時、結局ユーザーや世間を「騙す」ことになる。
冒頭に述べた2社のサービスは、それが逆転してしまった数ある事例の一つなのだろう。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者プロフィール】
・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)
・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント
・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ
・ブログが本になりました。
*1
*2