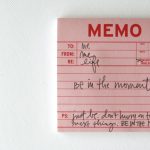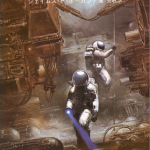糸井重里氏の「上場」に関するインタビューを見た。
その中で一点、気になるフレーズがあった。以下の部分である。
上場前は「要するに手帳の会社ですね」ってよく聞かれました。キングジムや良品計画をイメージさせる、文房具にも強い手帳の会社。
最初は抵抗があったんですが、今では割り切っています。農業に例えれば僕らの事業は苗木だらけ。(手帳以外は)数字に表れていないヒヨコばかりですからね。
これを見て、「あー」と思った。
同じような物言いを、他でも頻繁に見かけたからだ。
知人の一人は、この物言いに対して、露骨に不快感を表す。
「「要するに◯◯でしょ」と、すぐにまとめたがる人って何なの、あれ言う人って、自分で理解した気になって、人を見下したいだけだよね。」
少し前、彼は起業して「企業内教育に用いるアプリ」を作った。
だが、もちろんアプリをただ作るだけで事業になるわけがない。そこで彼は法人営業をし「社員教育研修」を受注する。そして、研修を提供するお客さんにアプリを使ってもらうことで少しずつ利用者を拡大している。
彼は「いつかは法人の教育プログラムのスタンダードを担いたい」と言っている。
だが、この話を他の人に話すと、時にこう言われるそうだ。
「要するに、研修会社でしょ。」
彼はいう。
「説明するのも面倒なんで、何も言わないけど「要するに◯◯でしょ。」って言う人は、はっきり言って「頭が悪い」と思っている。」
「なんで?」
「自分の今持っている価値観の中でしか考えようとしないから。iPadの発売の時「要するに大きいiPhoneでしょ」って言った人がいたけど、その感じ。」
「ああ。」
「iPadが「大きなiPhoneでしょ?」は、要するに、新しいものが想像できないから、自分の理解できる概念に無理やり押し込もうとする。それが「要するに◯◯なんでしょ?」っていう決めつけになるわけ。」
「なるほど。」
「まあ、どう思うかはその人の勝手だから、別にいいんだけど。でも、そう言う風に言う人はすごく損しているよね。」
「なぜ?」
「だって、それ以上は誰も何も言わないでしょう。自分が間違っていることを指摘されない状況は、バカの始まりだよ。」
確かに、糸井重里氏も、
最初は抵抗があったんですが、今では割り切っています。
と言っている。
おそらくその後には
「どうせ言ってもお前には理解できないだろうから」
と続くのだろう。
指摘する気も起きない、と言ったところだろうか。
———————
「ほぼ日」は手帳の会社なのだろうか。
普通に考えれば、「手帳の会社」と、無邪気にまとめてしまうのは控えたい。
ほぼ日は少なくとも「メディア」「ECサイト」を運営しており、手帳はその回収エンジンの一つに過ぎない。しかも現在たまたま、売上が大きいだけである。
たしかにそれを「手帳の会社ですよね」と言ってしまうのは、あまりにも不勉強であるし、糸井重里氏にも失礼だ。
おそらく「手帳の会社ですよね」と言ったどこかの誰かは、「ほぼ日」をきちんと理解しようとしていない。
単に「何の売上が大きいか」だけを見、自分の中の価値観に照らし合わせて、「これは手帳屋だ」と決めつけたか、メディアの成功を見て揶揄したいだけだろう。
ちなみに、中小企業向けのコンサルティング会社である日本能率協会やタナベ経営も、「手帳」の売上の割合はかなり大きいと聞く。
しかし、彼らをよく知っていれば「手帳の会社」とは言わないはずである。
そう言えば少し前、ある人物が
「自分はライターでなく、作家」と主張したことで、物議を醸したトピックがあった。
「自称」と「他称」が異なるのは珍しいことではないが、これは「ほぼ日」の話と似通っている。「何かの枠に決めつけたがる外部」と「そうではないと主張したい当事者」の対立だ。
他にも、村上春樹を「小説家」ではなく、「エッセイスト」と呼んでいた人に出会ったことがある。
「小説も書いているのでは?」と聴くと、「あんなものは小説ではない」とその人は言う。
残念ながら、この方は客観的視点にかけているようだ、と思ったが、結局のところ、プロは「どう名乗ったか」ではなく「何を生み出したか」でしか評価されない、と思ったのも事実である。
だからもちろん、その人物をどのように思うかは、個人の勝手だ。
しかし、個人的には、
「要するに手帳の会社でしょ」と、「要するにライターでしょ」には多くの共通点があると思うし、失礼な響きが含まれていると思う。
したがって
「要するに◯◯でしょ」
と会ったこともない誰かや、よく知りもしないサービスの評価を聞きかじっただけで決めつけるのは、少なくとも「賢い行い」とは言えないな、と私は思う。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者プロフィール】
・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)
・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント
・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ
・ブログが本になりました。
・「「仕事ができるやつ」になる最短の道」のオーディオブックもできました!
(Photo:Joan M. Mas)