「コンサル一年目が学ぶこと」という本について、知人から「本当にこういうことを習うの?」という質問をもらった。
パッと読んだ限りでは、特に違和感はないし、目次を見ていただいても分かる通り、特に「コンサルタントだから習う技術」というわけでもない。
大体、どんな会社でも「やってますよね?」と言われたら、仕事ができる人なら「まあ、やってるよね」ということが並んでいる。
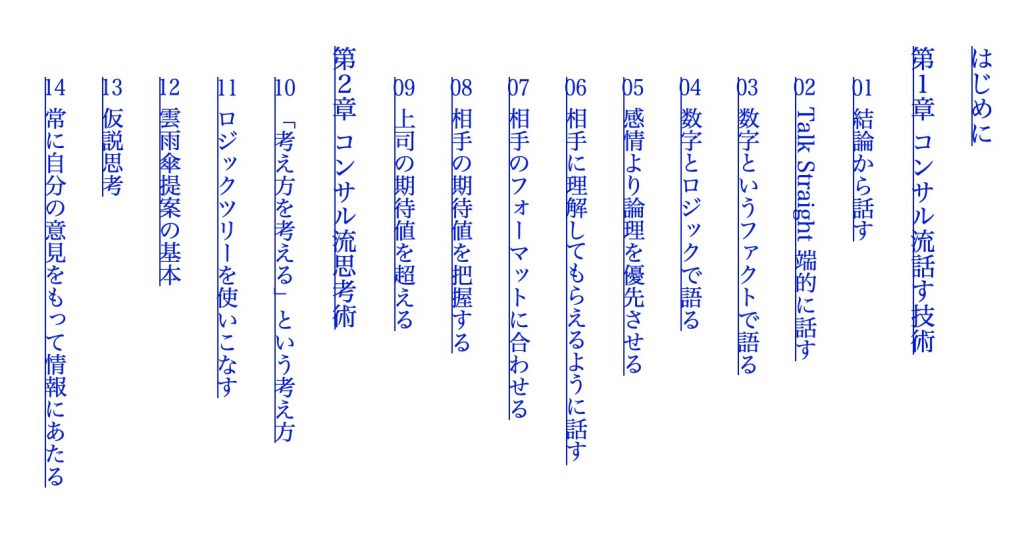
ただ読み進めていくと「コンサル会社ならでは」と言えそうな話もあった。
内容ではない。
コンサル会社のカルチャーの部分だ。
例えば「01結論から話す」において。
コンサルティング会社では、あらゆるものが、「結論から」のフォーマットに沿っていました。
そして、常にそれを意識するよう、すべてにおいて徹底されていました。
コンサルティングの報告書はもちろん、日常のメール、メモ書き、上司とのやりとり、すべて、結論から言うことが徹底されました。
この「徹底」というやつが肝心で、少なくとも私が在籍していたコンサルティング会社は、守るべき事項をガチで徹底してきた。
ここが、特有のカルチャーかも知れない。
新人だろうと、ベテランだろうと、年次に関係なく、この規範に沿えない人物は指摘をくらう。
しかも、極めて穏やかにではあるが、ドライに、かつ、しつこくしつこくしつこくしつこくしつこく言われる。
そして基本的に、そこに容赦はされない。
結論から話せないコンサルタントは、クライアント先にも出してもらえないし、コンサルタント失格の烙印がおされる。
「あいつ、話わかりにくいよな」という噂が立つ。
怒られない。けど、プロジェクトにアサインされず、干される。
だから、特に上司に対する社内コミュニケーションには、毎度、かなりの負荷がかかった。
毎度毎度、自分を値踏みされているような気分になるのだ。
例えば、私が入社一年目のとき、中島さん(仮名)という上司に相談したときは、こんな感じだった。
*****
「中島さん、17日にお客さんに提出する資料ですが、ちょっと悩んでまして……お時間いいですか?」
「いいよいいよ。(超にこやかに)」
「えーと、今T社が現状調査フェーズなのですが、戻ってきたのが文書調査票、課題管理票、プロセス分析表……」
「安達さん、結論から。(冷たく)」
「あ、も、申し訳ありません。えーと、課題管理表のサマリーを作っているのですが、「購買」に関する課題がとても多いんですよ。逆に「検査」に関する課題がすくなく……」
「安達さん、結論から。(まったくイラつく様子も見せず、冷たく)」
「す、すみません! 調査票に記入してもらった課題について、部署ごとに量と質にばらつきがあるのですが、このまま進めてよいかどうか迷っています。助けていただきたく。」
「OK。じゃ、資料を見せて。(超にこやかに)」
*****
結論から言わないと、話を聞いてすらもらえないのである。
「こんなかんたんなことができないんだ」と嗤う人もいるかも知れない。
だが、上司が超にこやかなのでかえって恐ろしい。
それが「毎日」「毎回」、相談されるたびに発生するのだ。
これは「結論から言えない人」にとっては、すさまじいストレスだろう。
もちろん、上司は「結論から言えるまで」本当に辛抱強く待ってくれるし、
怒ることも決してなかった。
が、毎度、上司に相談するだけでも覚悟が必要だった。
なお「結論から言う」カルチャーは、仕事にたいへん役に立つが、結構な訓練が必要だ。
いや、できる人は何の意識もせずにできてしまうのだが、できない人は何をどう説明しても、なかなかできない。
「ノウハウ」を聞いただけではダメなのだ。
だが、それを毎日、報告のたびにしつこくしつこく言われることで、二年目に入る頃にはそこそこ皆ができるようになる。
そうして、毎日の訓練、環境こそ「凡人」を「そこそこできる人」に鍛え上げるのだと、私は痛感した。
*
もう一つ例をあげよう。
「09上司の期待値を超える」と、「14常に自分の意見をもって情報にあたる」だ。
「14常に自分の意見をもって情報にあたる」には以下のようにあった。
情報量を増やしても、右から左に情報は抜けていき、頭に残らない、そして、せいぜい手に入れた他人の意見を鵜呑みにするだけなら、意味はありません。
考えるとは、端的に言って、自分の意見をもつということです。これも、コンサル一年目に学んだ大事なことです。
まあ、そうだよね、という感じだろう。
しかし、これが「カルチャー」となり、ガチ運用されるとどうなるか。
私が上の「中島さん」に話しかけた会話の続きだ。
*****
「す、すみません! 調査票に記入してもらった課題について、部署ごとに量と質にばらつきがあるのですが、このまま進めてよいかどうか迷っています。助けていただきたく。」
「OK。じゃ、資料を見せて。(超にこやかに)」
(中島さん、しばらく資料を見ている)
「安達さん、どうしてこうなったと思う?(真面目な顔で)」
「……えー、と。」
(中島さん、一言も発せず、じっと待っている。手元に紙を取り出してメモをとり始める。)
「せ、……説明が悪かったのかも知れないです。」
「そうだね。それもあるかもね。でも、この調査票への記入方法の説明って、全部署の代表メンバーに同じようにやったでしょ?(にこやかに)」
「は、はい……だとすると、代表の方が、うまく部署内に依頼できなかったのかもしれないです。」
「おー、それもあるね。他には?(うれしそうに)」
「課題が見えてない、とか」
「うんうん、課題が見えてない、ね。それもあるね。あとは?(もっと嬉しそうに)」
「……メンバーのやる気がない、とか……?もありますかね」
「おー、いいねいいね、それから?(身を乗り出してくる)」
「書いている人の能力が低い……というのもありますかね。」
「なるほどなるほど(ノリノリ)、で、安達さん、どれだと思う?これ、資料のここを見ると、何が正解か、一発でわかるよ。」
「ええええええ!(ど、どれだろう……)」
「考えて。理由もね。(マジな顔で)」
*****
上司は、ちょっと相談するだけでも、きちんとディスカッションの時間を取ってくれた。
だが、一度相談すれば、私自身が答えを発見できるようになるまで、簡単には離してもらえない。
ヒントはくれるが、答えは教えず「自分で考えろ」と言われる。
こうして、圧倒的な経験と力量の差を見せつけられるのだが、要するに、
「安達さんはどう思う?」「意見は?」「なぜだ?」「根拠は?」
をひたすら問われるカルチャーが、そこにはあった。
ただ、誤解をしていただきたくないのは、これらの質問は、上司が適当に「まあ、部下にも聞いとくか」とやっているのではないことだ。
彼は常に私に「価値ある回答」を求め、紳士的に、プロとしての自覚を促した。
また、私が良い回答をできたときは、「お、それは素晴らしい(満面の笑み)」と、資料に必ずそれを入れてくれた。
しかし、私が「判で押したような回答」をしようものなら、容赦なく
「……安達さん、そんなんで、お客さんが納得するかな?(にこやかに)」
と言われる。
要するに、常に知恵を試される状況が、そこにはあった。
しかも、これを「すべての上司」がやっているのだ。
そして、人事評価ではなく、会議や質問の場でのこうしたやりとりこそが「お前は使えるヤツなのか?」を判断される場だった。
もちろん、他にも
「感情への配慮の仕方」
「仮説⇛検証のサイクルの回し方」
「上司への意見の仕方」
「わかりやすい資料の作り方」
「文章の書き方」
など、お客さんのところですぐに使える技が、日常のコミュニケーションに組み込まれ、常に規範に照らし合わせて評価を受けるのだ。
*
こうしたカルチャーで仕事をするのが好きなら、コンサルティング会社は天国だ。
大いに知的好奇心は充足し、「ビジネス」という名前のゲームを楽しめることだろう。
だが、そうしたゲームが嫌いな人、仕事は最低限にとどめたい人、
「答えを教えてほしい」
「意見を聞かれるのは苦手」
「毎日値踏みされるのはイヤ」
という人は、コンサルティング会社は辞めておいたほうがいい。
そういう人にとっては、中島さんのような上司は、にこやかに、容赦なく、心を壊してくる「鬼」に見えるだろうから。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
◯Twitterアカウント▶安達裕哉
元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者(http://tinect.jp)/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。
◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(http://note.mu/yuyadachi)
◯安達裕哉Facebookアカウント (他社への寄稿も含めて、安達の記事をフォローできます)
◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をすべてフォローしたい方に)
◯ブログが本になりました。
Photo by Wonderlane














