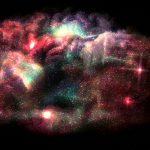ああ、これこれ。反出生主義って世俗からの離脱とうつるかもだけど、正反対に、能力主義や成果主義や自己責任を厳しく内面化した結果として反出生主義ってあるように思うわけです。そういうの珍しくないんじゃないかな。 https://t.co/YOmevsmwf8
— p_shirokuma(熊代亨) (@twit_shirokuma) June 3, 2021
6月上旬にtwitterで上掲のようにつぶやいたところ、じわじわと「いいね」と「リツイート」が集まってきた。
このことをとおして、似た風に考えている人が結構いることを私は知った。
なので、このつぶやきに関連して、世俗のきわみのような自称-反出生主義について簡単にまとめてみる。
私にとって反出生主義といえば、輪廻からの離脱
反出生主義という語彙を頻繁に目にするようになったのは令和に入るか入らないかの頃、2010年代の終わり頃からだったと思う。
反出生主義という語彙には、「自分自身の幸福追求や不幸回避のために子どもをもうけない」という以上の意味合いがある。
それは、「子どもが生まれてくるという事態そのものが不幸なことなのだから、子どもはもうけないほうが良い」「生まれてくるという事態が痛みや苦しみの究極のはじまりなのだから、生まれてこないほうが良い」といった意味合いだ。
こうした反出生主義の話を聞くたび、私は(仏教の)釈尊の教えと、それに連なる上座部仏教の教えを思い出さずにいられなくなる。
私は日本の在家の大乗仏教徒なので、原始仏教や上座部仏教が説く”輪廻からの離脱”という遠い目標は目指していない。
それでも、一切皆苦という考え方にもとづいて輪廻からの離脱を目指し新しい生をもうけないとする目標設定と、そのための戒律には説得力を感じている。
いまどきの反出生主義を唱える人には、輪廻からの離脱、そもそも輪廻という概念はあるのだろうか?
私の場合、仏教の影響があるからインド生まれの輪廻という概念に親しみを感じずにいられないのだが、それゆえ、輪廻という概念を伴わない反出生主義がどういうものなのか一層わからない。
もし私が反出生主義的な何かを信奉したくなったら、きっと原始仏教や上座部仏教にアプローチするだろう。
いや、アプローチしていない現在でも、(在家の大乗仏教徒とはいえ)世俗にあって子孫を残すことにうしろめたさを感じることはある。
僧侶の資格を持っていた私の祖父が残した、「だが結局、生きるとは苦というほかない」という言葉を私はどこかで真に受けているのだと思う。
ああ、反出生主義について肯定的なことを書こうとすると、私はどうしても仏教に吸い寄せられてしまう。
とはいえ、釈尊や輪廻とは無関係な反出生主義も「生きること・生まれてくることは根本的に苦である」とする点は共通している。
でもって、こうした反出生主義的な考え方は、あらゆる生を肯定し、快楽追及や幸福追求のために努力を積み重ねることを自明視し、社会の構成員すべてにそう考えることを強制するイマドキの考え方へのアンチテーゼとして、私はあったほうがいいと思っている。
少なくとも反出生主義には、イマドキの考え方が見て見ぬふりをしている何かが含まれていると感じる。
しかし、世俗をきわめた反出生主義っぽい人々もいる
……と、ここまでが反出生主義についての個人的所感なのだが、自称-反出生主義者にはまったく違う感覚をおぼえることが多い。
反出生主義そのものは世俗から超越していると感じられても、自称-反出生主義者のなかには世俗にすっかり絡めとられて、むしろ世俗の考え方を内面化しすぎた結果として反出生主義を自称するようになったらしき人が、少なからず見つかる。
自分のような劣性遺伝子は後世に残すべきではないと思うので子供はいらない
他人に強制はしないのできっと穏やかな反出生主義者なんだろうななんて思っていたがこれどちらかと言えば優生主義者じゃねぇか??
— やまだ (@hetero__combat) June 2, 2021
たまたまタイムラインに流れてきたやまださんのツイートが気づきを含んでいたので、例示してみる。
この人は、ある時期まで自分のことを反出生主義者だと考えていた様子だ。
ところがそう考えていた理由は、「自分のような劣性遺伝子は後世に残すべきではないと思う」となっている。
ご本人が続けて書いているとおり、これは反出生主義というより優生主義の発想である。
良くない遺伝子だから後世に残すべきではないという考え方は、良い遺伝子なら後世に残すべきという考え方と表裏一体であって、反出生主義とも仏教の考え方とも相容れるものではない。
反出生主義という言葉が知られていくうちに、反出生主義っぽいけれども内実はそうではない人が反出生主義を自称するようになっているのではないだろうか。
そうした反出生主義に似て非なるもののなかには、まず優生主義的な自称-反出生主義がある。
ありがちなのは、社会的成功や配偶者獲得がうまくいかない人が優生主義的に考えた結果として、「自分のような人間は子どもを持つべきではない」と思い至るパターンだ。
ナチスドイツのような優生学は世界じゅうで忌むべきものとみなされているが、たとえば個人が自分自身を振り返る際には、こんな風に「自分の遺伝子が後世に残すに値するか否か」が言葉となって現れる。
余談だが、国家レベルの優生学が死に絶えても個人レベルの優生学は今なお健在である。ますます盛んかもしれない。
話を戻そう。
反出生主義者を自称している人々を眺めていると、ほかにも、能力主義や成果主義を強く内面化している(が、それを果たせない)人々、自己責任の考え方を強く内面化している人々が散見される。
こうした人々に共通しているのは、特定の人々は子どもをもうけるべきではない反面、その裏返しとして、特定の人々こそ子どもをもうけるにふさわしいという意味合いが感じられる点だ。
こうした自称-反出生主義者からは、世俗を超越した雰囲気はまったく感じられない。
幸福追求を自明視し、自己の優越性や卓越性を獲得することが生きるに値するという、世俗の考え方をしっかりなぞらえていると感じる。
これは世俗からの超越ではない。
むしろ逆で、世俗のきわみ、通俗のきわみである。
世俗の考え方がきわまった結果として、反出生主義という語彙がこぼれ落ちるようになっているのである。
彼らは世俗を否定するのでなく、肯定している
釈尊とその忠実なフォロワーがそうであるように、「生きるということ、生まれてくるということは、根本的に苦である」と説く人には世俗を超越した雰囲気が漂う。
今日、反出生主義を支持する人からも、そうした、良く言えば世俗を超越した、悪く言えば世俗を逸脱した雰囲気が感じられることが多い。
そうした言葉を耳にする時、私はいくらかの反感といくらかのシンパシーを感じる。
彼らが口にしている言葉のなかには、いまどきの考え方に馴らされている私自身が黙殺している考え方や、日本の在家の大乗仏教徒としての私自身が諦めている考え方が含まれているからだ。
しかし、反出生主義といいつつ内実が優生主義や能力主義や成果主義である人の言葉には、そうした反感やシンパシーを喚起する力がない。
彼らの言葉から感ぜられるのは、いまどきの考え方の否定ではなく肯定であり、世俗に対するオルタナティブではなく世俗の追認だ。
彼らが否定しているのは、世俗ではなく彼ら自身ではないだろうか。
そしてその彼ら自身を否定する言葉もまた、世俗の評価尺度によって構成されているのである。
反出生主義が、娑婆苦全体を否定的にとらえるなら、是非はともかく、世俗の考えから遠いに違いない。
だが、その反出生主義が世俗をきわめた人々によって語られ、似て非なるかたちで人口に膾炙しているのは、興味深いことだ。
このように思想思弁の次元だけでみても、世俗の枠組みから逃れるのは簡単ではないようである。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【プロフィール】
著者:熊代亨
精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。
通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(イースト・プレス)など。
twitter:@twit_shirokuma
ブログ:『シロクマの屑籠』