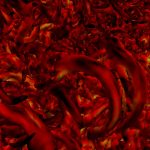「要点の見分け方をどうやって身に着ければいいのか」という話をします。
いきなり例示から入るんですけど、ちょっと次の引用文を読んでみて頂けるでしょうか。面倒な方は斜め読みで大丈夫です。
鎌倉を拠点とした源頼朝は、無断で朝廷から官位を受けた弟の義経を許さず、義経をかくまった平泉の奥州藤原氏をほろぼして、東北地方をも支配下におきました。一方、にげた義経をとらえることを口実に、1185年、国ごとに守護を、荘園や公領に地頭を設置しました。頼朝は1192年に征夷大将軍となり、武士による新しい政治を始めました。
頼朝の開いた鎌倉幕府は、家来となることを誓った武士を御家人にして、先祖から引きついできたその領地の支配を認め、てがらに応じて新たな領地や守護・地頭の職を与えました。
鎌倉幕府成立前後の経緯についての記述ですね。
文章としては、帝国書院、「中学生の歴史」からの引用です。長男が学校で使ってる教科書なんですけどね。
皆さん、日本史の試験でこの文章が範囲になった時、どこをどうやって覚えるか、ちょっと考えてみていただけますか?
どこがこの文章のポイントになるか、どこを覚えればこの文章を「抑えた」ことになるか、ってぱっと分かりますか?
「勉強が出来る人」と「勉強が出来ない人」の違いは一体なんなのか、というテーマを、結構あちこちで目にします。
色んな方々の書く文章や意見を読んでいると、それぞれ説得力のあることをおっしゃっていて、「なるほどー」と思うことしきりです。
とはいえ私の個人的な所感としては、「勉強が出来る」というのはものすごーく色んな要素の集合体であって、一言で総括するのはなかなか難しいよな、というところに落ち着くことが多いです。
ただ、その色んな要素の中でも重要性の高い、低いというものはもちろんあります。
私が考える限り、「勉強が出来る/出来ない」というテーマが包含する要素の中でもかなり重要性が高いものとして、
「抑えなくてはいけない「ポイント」の見分け方、嗅ぎ付け方」
「ポイントとポイントの繋ぎ方」
というものがあります。
出来る人にとっては呼吸をするような当たり前のことなんですけど、出来ない人にはさっぱり分からない。
そして、出来る人と出来ない人の間で恐ろしく差がついてしまう。そういう勉強のノウハウです。
以前から何回か書いているんですが、しんざきは学生の頃、補習塾の講師のアルバイトをしていました。
補習塾って、主に学校の試験で成績が悪い子をフォローすることを目的にした塾でして、受験勉強とかはあんまり守備範囲に入っていません。
必然、「勉強が出来ない」子をたくさん観ましたし、たくさん教えました。
そんな中で一つ得た知見があるんですけど、勉強が出来ない子って、まず「全部同じに見える」だから「全部覚えようとする」んですよ。
ここで話は冒頭の文章に戻ります。鎌倉幕府成立についての文章。
勉強が出来ない子にとっては、この文章って、「どの記述が重要な情報で、どこを覚えればこの文章の要点を抑えたことになるのか」が分からないんですね。というか、そもそも「要点」というものが分からない。
だから、例えば
「無断で朝廷から官位を受けた弟の義経を許さず」
という記述も、
「1185年、国ごとに守護を、荘園や公領に地頭を設置しました」
という記述も、
「先祖から引きついできたその領地の支配を認め」
という記述も、全て同じような重要度に見える。
強いて言うと、「平仮名よりも漢字の単語の方が重要に見える」とか、マジでそういう理解です。
更に言うと、単語という「点」が、ただそれだけでは意味のある情報として繋がらなくって、「守護」「荘園」「領地」「公領」「地頭」といった単語単語を必死に覚えようとするのに、折角覚えられたとしても元の意味を再現出来ない。
覚える情報のピントが合ってないので、守護ってなんだっけ?公領ってなんだっけ?ってなってしまうのです。
私が補習塾時代に観た子たち、私が何も口出ししないと、ほぼ百発百中、
1.取り敢えず漢字の単語だけ全て抜き出して覚えようとする
2.頑張って覚えきる
3.そのあと「1185年に起きたことってなんだっけ?」と聞かれても答えられない
というプロセスをたどっていました。
どこが重要か分からないので、全部覚えなきゃいけない、と考える。
全部覚えようとするから到底脳のメモリーに収まり切らないし、「こんなにたくさん覚えられるわけない……」って絶望してしまう。
あるいは、部分的には覚えられても、その覚えた内容から「重要な情報」を抽出できない。
例えば「1185年」「守護」「地頭」という言葉を辛うじて思い出せたとしても、それが何を意味している言葉だったかが良く分からない、という状態になってしまうんです。
じゃあ「勉強が出来る」子はどうするかっていうと。
もちろん子どもによって随分違うとは思いますけど、まずこんなん「全部覚えよう」となんて絶対しない、というのは大体共通しているでしょう。
多かれ少なかれ、こういうステップになる筈です。
・重要な情報や単語だけを抜き出して要約する
・要約した文章の中の情報の重要性を(大体)ランクづけする
・その要約の中でも、キーワードになりそうな重要な部分だけを覚えて、一旦他の情報は忘れる
・必要になったらキーワードから全体の情報を思い出す
まあ元の例文自体、既にかなり要約して必要な情報を凝縮しているので、どれも重要っちゃ重要なんですが、可能な限り情報を圧縮すると、まあ大体以下のように要約できるでしょう。
1.頼朝は義経をかくまった奥州藤原氏を滅ぼした
2.義経を追うことを口実に、頼朝は1185年守護と地頭を各国に設置した
3.頼朝は1192年に征夷大将軍になった
4.家来である御家人に、褒美として守護・地頭の地位を与えた
もうちょっと出来る子だと、この文章のテーマがざっくり「鎌倉幕府の成立」であることを読み取って、上記の1と4はどちらかというとその経緯と副次的な要素であって、より重要なのは2と3の情報だ、とランクづけ出来るかも知れません。
「年号が絡む情報は(テストに出やすいという意味で)重要」という、ライフハック的な勘所を理解している子もいます。
で、一度こういう風に情報を整理しておくと、後は部分的な単語だけからでも大体の流れが再生出来たりするんですよ。
最終的には、
「1185年、地頭・守護設置」「1192年、征夷大将軍」くらいだけちゃんと覚えて、後はいったんメモリからクリアする、というような感じの処理をする子が、恐らく一番「勉強が出来る子」の部類になるのでしょう。
いわゆる「要領がいい子」というやつです。
元の文章を全部覚えようとする子と、「1185年、地頭・守護設置」「1192年、征夷大将軍」のほんの30字足らずだけをしっかり覚える子。
どっちが効率良く勉強出来るかなんて決まってますよね。
この、「要点を見分ける」「その文章の中で、どこが重要なのかを判断する」「圧縮した情報から元の情報を再生する」という練習って、恐らく小学校・中学校で勉強することの中で、最上級に重要なノウハウです。
こういう、「どこが重要かを見分ける」為に勉強があり試験がある、と言ってしまってもいいくらいです。
じゃあ、私がこれを「出来ない」子にどうやって教えていたかというと。
もちろん段階は色々あって、そもそも文章が読み解けない子にはそれはそれで別の教え方をしないといけなかったんですけど、「文章は読めるけど要点が良く分からない」という子には、
まず
「10文字でまとめろ」
「それが出来るまで絶対覚えようとするな」
と教えていました。
読む前に、まず「この文章って何について書いてある文章なのかなあ?」ということを考える。
この文章を書いた人は何を伝えたいのかなあ、と考える。
すると、取り敢えず全体的に頼朝の名前が多く出てくるし、「頼朝の開いた鎌倉幕府」という言葉もあるので、「鎌倉幕府が出来るまで」ということがテーマだな、ということまでは何となく分かる。
いや、ここまで来るにも結構練習が必要なんですけど。
で、「鎌倉幕府」という話になると、それぞれの単語がどう鎌倉幕府と関係するのか、という考え方が出来る。
ここで出てきた単語が、「幕府」という統治機構を構成する上でどういう役割を持っているのか、という視点が持てる。
征夷大将軍というのは「幕府の偉い人」。守護とか地頭とか御家人というのは「幕府を構成する役割の一つ」。義経がどうというのは、鎌倉幕府成立というテーマの上では「口実、経緯」。
これが出来るようになってくると、段々「単語と単語のつながり」ということも分かるようになってきて、更に「色んなつながりを持っている単語が重要な単語なんだな」というのもちょっとずつ分かるようになってくるんですよ。
まず要約する。その後重要性をランクづけする。そして繋がりを理解させる。
いわゆる、上で書いた「勉強が出来る子」のやり方をひたすらなぞらせたわけです。
これをとにかく繰り返す内に、そこそこの率で「要点の見分け方」を理解させられるようになったと思います。
時間は凄ーくかかるんですけどね。
でも、いくら時間をかけてもまずここからやった方がいい。
これ、社会人になって仕事をするようになると、「出来るか出来ないかで滅茶苦茶な差が出る」ということがよく分かるんですよ。
同じ新人の子を教える時にも、「まず要点を見つけようとする子」と「取り敢えず全部覚えようとする子」だと、学習効率が想像を絶する程違います。
知らない技術を身に着ける時にも、仕事のやり方を覚える時にも、その「スタンス」の有無で天地の差。自転車とF1カーかよ、ってくらい違う。
そういうのを見てると、「勉強って何の役に立つの?」とか一体どんな恐ろしいことを言っているのか、と思うようになりますよね。
もちろん、こういうノウハウを身に着ける場所が「学校の勉強」だけに限られるかというとそうでもないんですが、「学校の勉強」のコスパが凄まじく良いというのはつくづく感じます。
「勉強を通して身に着くこと」の重要さをつくづく痛感しつつ、自分の子どもにはしっかりこういうノウハウを身に着けさせてあげたいなあ、と思うところ大なわけです。
全然関係ないんですが、小学中学の教科書って、今読んでも滅茶苦茶面白いですよね。
鎌倉幕府成立の年代なんて今ちゃんと「諸説ある」って明記してあって、私が小学生の頃と随分違うなーと感心したりしてました。教科書作ってる人すごい。
今日書きたいことはそれくらいです。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
著者名:しんざき
SE、ケーナ奏者、キャベツ太郎ソムリエ。三児の父。
レトロゲームブログ「不倒城」を2004年に開設。以下、レトロゲーム、漫画、駄菓子、育児、ダライアス外伝などについて書き綴る日々を送る。好きな敵ボスはシャコ。
ブログ:不倒城
Photo by Tom Mills