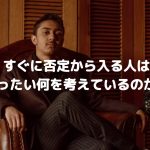もう最初から、この記事の結論を書いてしまおう。
「しょっちゅう人手不足になるところでは働くな」である。
わたしはちゃんと(?)企業勤めした経験はないから、あくまで学生時代のアルバイトを通じての所感だけど。
でも、バイトだろうが正社員だろうが、これはたぶん同じだと思う。
「しょっちゅう人手不足になるところでは働くな」
バイトの面接を取り付けたらため息をつかれた
学生時代アルバイトを探しているとき、地域の無料求人雑誌で、ちょうどよさそうな募集を見つけた。
駅前のスーパーの惣菜屋さんで、時給は低いが家から近く、1日3時間から入れるとのこと。希望条件にぴったりだ。
さてさて、さっそく電話。
「求人広告を拝見してご連絡いたしました。担当の方はいらっしゃいますか?」と聞いてみる。
すると電話口の女性は、「ふぅん……年は?」と無愛想に聞いてくる。
「大学1年です」と答えたら、大きなため息をつかれた。
ため息?
「若い子ってすぐに辞めるんだよねぇ。キッチン掃除なんてしたくないんでしょ、どうせ」
「いえ、焼肉屋のキッチンでアルバイトもしていましたし、多少経験はあります」
「ふーん。でも学生って金目当てでしょ、なんで時給が低いうちで働きたいの?」
「給料以外にも、家からの近さや募集の時間帯などの条件もあったので」
「あっそう。まぁ一応面接くらいしてもいいけど……」
と、こんな対応をされた。
噓のような本当の話である。
いまだに、なんでここまでひどい態度を取られたのか、まったくわからない。
わたしはただバイトがしたいと電話しただけなのに。
っていうか、人が足りないから募集したんじゃないの? 応募がきたら喜ぶべきでは?
そのことを友だちに愚痴ると、「あそこ、いっつも求人出てるからヘンだと思ってたんだよねー。バイトいびるオバサンがいるんじゃないかなって思ってたけど、その人なのかも」と苦笑い。
なるほど、しょっちゅう求人が出るところには人が来ない理由があるんだなぁ……と学んだ一件だ(もちろん面接は辞退した)。
毎日ヘルプを呼ぶ店は「地雷アルバイト」が仕切ってた
「人手不足」といえば、居酒屋でアルバイトしていたとき、かなり不愉快な経験をしたことがある。
バイト先は全国チェーン店で、時折系列店にヘルプで呼ばれることがあった。
たいていは、病欠で人が足りないとか、大人数宴会の予約が入っているとか、やむをえない理由で1日だけヘルプを呼ぶのだ。
しかし一時期、しょっちゅうヘルプを必要としている店があった。
一時的に人が足りないのではなく、どう考えても、単純にその店で働いている人が少なすぎる。
だから毎日のように、ヨソから人を呼ぶしかない。
実際その店に行ってみて、その理由はすぐにわかった。
ヘルプに行ったら、「来てくれてありがとう!」と満面の笑みで迎えてもらうのがふつうだ。
しかしそこでは、「タイムカード切ってきた?」「初めて会うけどどこの店?」「あんたはまずこれやって」
と、来た早々にアラサー前後の女性が偉そうにいろいろと指示してくる。
なるほど、この人が店長なのか……と思いながらキッチンに行くと、中年男性が「店長の◯◯です」と言う。
あれ? じゃあこの人はだれ?
他の人にこっそり聞いたところ、この店は店長の権力が異常に弱く、この古株のバイト女性が仕切っているらしい。なんじゃそりゃ。
しかもわたしがその店にはじめて行ったのは、大繁盛で店は満席、それなのに自店バイトよりヘルプのほうが多いというとんでもない日だった。
いくら系列店とはいえ、メニューも店のレイアウトもちがうまったく別の店。
料理の中身を聞かれてもわからないのでキッチンに確認、ハンディ(注文を入力する小型端末機器)の仕組みもちがうので注文を手書きメモして入力、各テーブルに振ってある卓番もわからないのでビールを持っていくのも一苦労。
本来ヘルプは、食器を下げたり空いたテーブルをリセット(次のお客様を迎えられる状態にする)したり、「どの店でもある程度同じ作業」をするものだ。
しかし唯一の自店ホールバイトがドリンカーで飲み物をつくっているものだから、接客はすべてヘルプというカオス具合。
当然うまくいくはずもなく、仕切っていたバイト女性はイライラしてどんどん口調がきつくなる(その女性はキッチンに入っていた)。
「早くドリンク持って行って」「料理追いつかないからオーダー一旦ストップ」と言っていたのが、だんだん「なんでまだドリンク出てねぇんだよ!」「料理冷めるじゃねぇか!」にヒートアップ。
最終的にインカムで、「やる気ないならてめぇら辞めろ! 帰れ!」と絶叫。
さんざんインカムでぐちぐち言われていたヘルプたちもそれで堪忍袋の緒が切れて、「帰られたら困るのそっちだろ! そこまで言われてヘルプしてやる義理はない!」とわたしを含め数人が帰宅。
いま思えば、つねにヘルプを求めるということはそれだけ人手不足というわけで、その理由はまぁ……お察しである。
総菜屋のように新しい人が来ないパターンもあれば、このように人が定着しないパターンもある。
いずれにせよ、つねに人手不足なのには相応の理由があるのだ。
面接をすっぽかす店長のもとに人が集まるわけがない
「いつも人手不足の店はロクなもんじゃない」という例を、もうひとつだけ挙げておこう。
アルバイト募集の広告を見て面接を取り付け、指定された日時にお店に足を運んだときのこと。店内にいるのは学生と思しき仕込みの男の子ひとりだけだった。
「面接? いま店長席を外してるんですが……」
「え?」
「すみません、ちょっと確認します」
店長が店におらず、そもそも連絡が取れないとのことで、わたしは30分ほど待たされた。
やっと連絡が取れたと思ったら、「会議で忙しいから後日にしてくれ」とその男の子に言ったらしい。
はぁ?と思ったが、彼を責めてもしかたない。
店長の希望どおり履歴書を彼に預け、男の子づてに聞いた「夜改めて連絡する」という言葉を信じて電話を待っていた。が、電話がかかってこない。
翌日電話をかけたら、「忙しくて忘れていた」とのこと。なんだそれ!
面接をすっぽかし、フォローの電話も忘れ、こちらからかけても悪びれずに「忙しかったんだよねー」で済ませてしまうとは!
こんな店長のもとで働きたくないなぁ。全部適当でうまくいかなそう。
というわけで、「もうちょっとちゃんと対応すべきでは?」と面接は断った。
その後、友人との飲み会で何度かその店に行くことがあったが、いつ行っても店のトイレに求人広告が貼ってあった。
「まぁあの店長じゃねぇ……」とひとり納得した記憶がある。
しょっちゅう求人を出す人手不足のところでは働くな
人手不足のところは応募条件が緩く、いかにも「働きやすそう」に見える。
しかし求人広告がつねに出ているということは、定着しないなにかしらの理由がある、もしくは応募者が辞退するような理由がある、ということだ。
いずれにせよ、ロクな労働環境ではない。
もちろん、学生バイトが多いから卒業シーズンの春休みに求人するとか、繁忙期に大量募集するとか、そういった事情もあるだろう。
しかしそれはどれも一時的なもので、募集が埋まれば求人広告では見なくなるものだ。
そのなかでずっと残り続ける求人広告があれば……つまりそういうことである。
まぁ、もしかしたら急成長中でどんどん会社規模を拡大しているのかもしれないけどね。
仕事先を探すとき、その求人がどれくらいの期間、どれくらいの頻度で出されているかなんて、だいたいの人は気にしないだろう。
でも可能であれば、その求人がどれだけ残り続けているのか、ちょっと調べてみることをおすすめしたい。
っていうか、求人サイトにはもはや明記してほしいよね。
いつから公開されて、何人募集していて、何人応募があって、何人採用されて、どれくらい定着してるのか、とか。
大人の事情で公開されないんだろうけど、プライバシーに配慮しつつ、公開しちゃったほうがいいような気がするなぁ。応募する側としてはそっちのほうが絶対に助かる。
もしかして、公開されると困る理由でもあるのかな……?
というわけで、「しょっちゅう人手不足になるところでは働くな」。
避けられる地雷を、わざわざ踏む必要はないのだから。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
名前:雨宮紫苑
91年生まれ、ドイツ在住のフリーライター。小説執筆&
ハロプロとアニメが好きだけど、
著書:『日本人とドイツ人 比べてみたらどっちもどっち』(新潮新書)
ブログ:『雨宮の迷走ニュース』
Twitter:amamiya9901
Photo by Nick Fewings