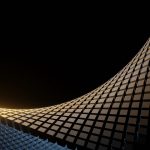私が以前在籍していたコンサルティング会社の一部署では、「失敗」という言葉を使うことが禁止されていた。
代わりに「成長ネタ」という言葉を使いなさい、と。
会社は、「失敗」を、公式に次のように言っていた。
失敗は「成長ネタ」です。成功よりも成長ネタからの方が、学ぶことは多いです。
成長ネタは、全く恥ではありません。
正直なところ、当初は「呼び方だけ変えてもね……」と懐疑的であったが、のちに、これは全く私が間違っていたことがわかった。
「成長ネタ」と呼ぶことで、失敗の公表に対してポジティブな態度をとれる人が増えたからだ。
*
私がチームリーダーを務めていた時、一人の部下が、顧客から苦言をもらってしまったことがあった。
原因は、説明不足によるもので、お客様の誤解とはいえ、こちらに非があるものでもあった。
これは、再発防止をしなければならない。
しかし、「十分に説明をしなさい」だけで、それが徹底されるだろうか。
たぶん、難しいだろう。
コンサルティングツールも、資料もチェックリストもあったが、結局、それを実行するのは人間だ。
現場に裁量を認める以上、「人間に依存する部分」は生まれてしまう。
だから、「成長ネタ」として、起きた生々しい話を詳しく本人から説明してもらい、再発防止のための情報共有を図ることは、避けて通れないと判断した。
しかし、苦言をもらって凹んでいる本人に、さらにその傷口に塩を塗るようなことにならないか。
本人がやる気を失ってしまうことになるのではないか。
私は心配だった。
そこで私は、本人に確認した。
「今回の件について、他のメンバーと情報公開のミーティングをしたいと思っているが、どう思うか」と。
ところが、その本人の返答は、私の想像をはるかに上回っていた。
彼は「ぜひやりたいです」と言ったのだ。
私は言った。
「ありがとう、だけど、絶対じゃなくて、私がやってもいい、無理しないでいいから」と。
ところが、その人はこういった。
「成長ネタを共有する機会をもらって、逆にありがたいくらいです。むしろ皆に、聞いてもらいたいです。」
私はその時気づいた。
「企業風土の影響は、すごいものだ」
と。
実際、意見交換会は非常に盛り上がった。
これに乗じて、メンバーたちから「別の成長ネタ」も共有され、「とても有意義な意見交換だった」とのコメントも得られた。
そして私は初めて気づいた。
「失敗」と呼ばないことを徹底するだけで、皆の反応がこんなに違うのか、と。
また、つらかった体験を、受け入れてもらえる場があれば、本人も救われるのだな、と。
*
昨年末、ある記事が話題になった。
1500万円の退職金を元手に、居酒屋経営を始めた脱サラ経営者が、失敗して1年で破綻した、というのだ。
1500万円の退職金を元手に居酒屋経営。1年で破綻したワケは「客の意識の低さ」
上司の顔色を窺い、部下のパワハラ糾弾に怯える毎日。そんな生活からの脱出は、全サラリーマンの悲願だ。47歳のときに上場企業の管理職を捨て、居酒屋経営に飛び込んだ児玉謙次さん(仮名・54歳)は嘆く。
「もともと居酒屋巡りが好きで、日に日に自分の店を持ちたい思いが強まっていくなかで人事異動があり、傘下の集客施設内に新しい店を立ち上げるプロジェクトを任されたんです。『脱サラの練習をせよ』と神様がプレゼントしてくれたように感じましたね」
様々なニュースサイトで取り上げられていたが、Twitterでも様々なコメントがついていた。
大半は失敗について「甘く考えてる」「そりゃそうだ」「当然」というものであり、ネガティブなコメントが多数ついている。
https://t.co/OnQ6kUAPYv
こう言う人とかね。— 谷梅之助 (@umenosuke_tani) January 6, 2022
失敗者が叩かれるのは、世の常だ。
ただ、私は過去の経験から、この居酒屋経営者に、感謝せねばなるまい、と改めて思った。
成長ネタを提供してくれたからだ。
彼は個人で退職金1500万円に加えて、借入金1000万円というリスクを取り、店を開業した。
しかし、彼の想定と、現実は全く違っていた。
そしてなによりの負担が接客だ。
「おいしい料理でお客さんを笑顔に、なんて思っていましたが、来る客は今までの大企業サラリーマン人生では接したことのないような人ばかりで、大変なストレスでした。
『お前、こんな店やめてラーメン屋をやれよ』とか、とにかく説教をしたがる客が多い。故郷から取り寄せた珍しい食材を使ったこだわりの料理は見向きもされず、フライドポテトや焼き鳥のようなありふれたメニューばかり注文が入る現実にもうんざりでしたよ」
実際、記事の通りの思いなのだろう。
が、手痛い失敗にも関わらず、彼は「取材に応じる」という選択をしてくれた。
ポジティブな動機だけでは、事業は立ち行かない、ということ。
客のせいにしても、何も改善しない、ということ。
説教したがる客のこと。
ありふれたメニューばかり注文されること。
ほとんどの起業家が失敗することから、ナシーム・ニコラス・タレブは、「起業家は社会の英雄だ。私たちのために失敗を肩代わりしてくれる」という。
居酒屋経営に踏み込んだ、上の記事の主人は、リスクを取って、我々に貴重な教訓をもたらしてくれた。
しかし、その「成長ネタ」に対して、記事の最後のコメントは、何とも無慈悲だ。
会社にいたほうが楽だったか。
マスコミが無神経なのか、そういうコメントを皆が求めているのか。
それはわからないが、つくづく、世の中は、失敗に冷たいな、と思う。
もちろん「彼が勝手にやったことだ」と言えば、それまでだ。
ただ、私は「失敗を語ってくれて、ありがとうございました。」と言わなければならない気がしている。
それが、「失敗した人」にとって大きな救いとなり、結果として、良い社会の雰囲気を作るということを、過去に私は確かに、実感したからだ。
*
「悪の組織」は、失敗者をすぐに粛正するがゆえに、再発防止の知見がたまらず、正義の味方に常に敗北するのだ、と知人が言っていた。
確かにそうなのだろう。
飛行機事故や火事、なども含む、あらゆる失敗・悲劇は、人類全体としては「貴重な教訓」だ。
悲劇にあった人、再発防止のために頑張る人に、私たちは感謝せねばならないのだろう。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
安達裕哉
元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)