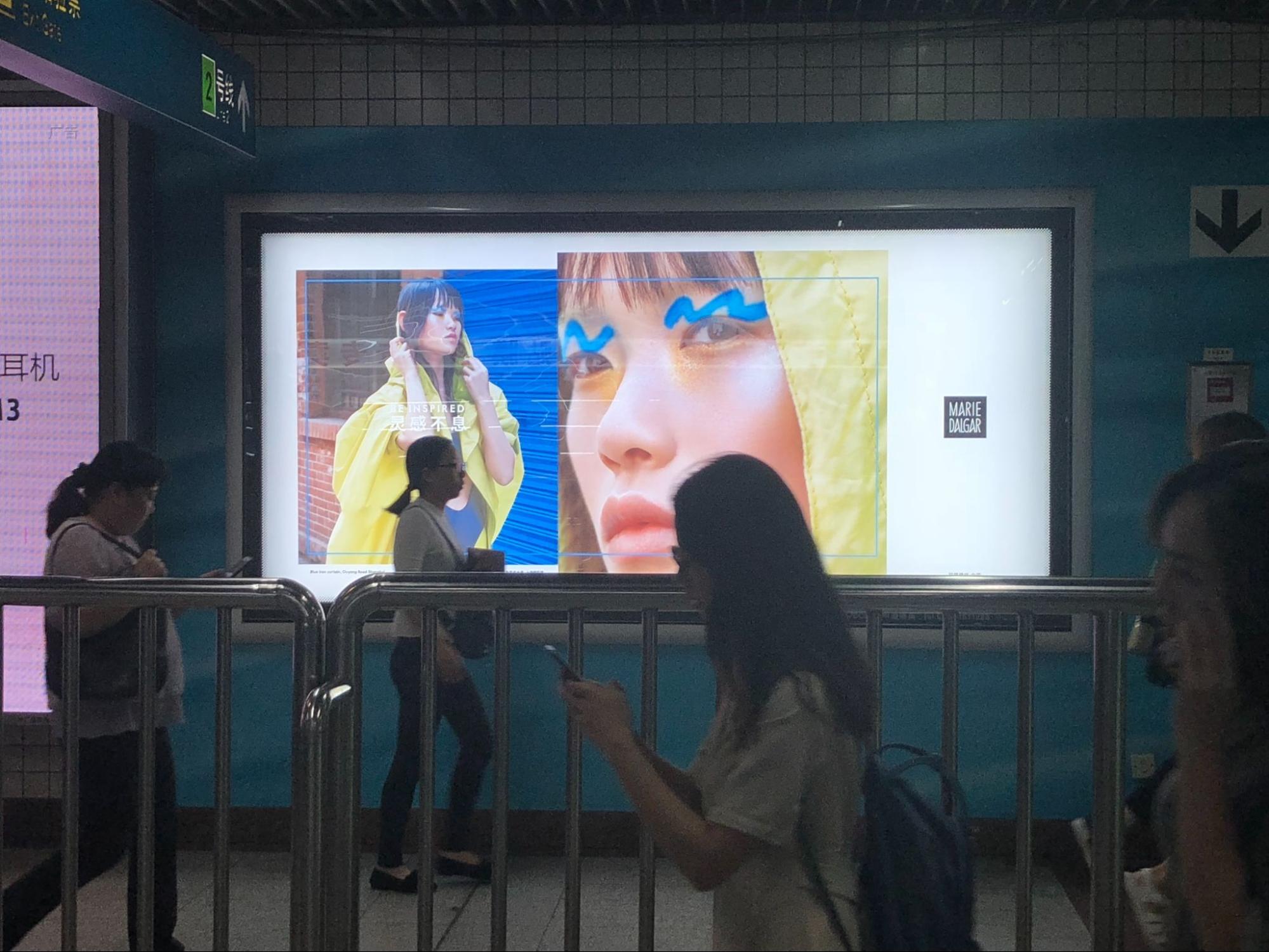中国で今、奇妙な日本語熱が巻き起こっていることをご存知だろうか。
人によっては敵性言語、口にするのも汚らわしいーーガチでそういう考えを持つ方が一部にいるお国柄でありながら、「お受験言語」として人気を博しているのだ。
相手国の言語を学ぶことは、相互理解のための大きな一歩。きっと、将来の日中友好に利するに違いない……と信じたいところなのだが、中国で暮らす身としては、そう簡単にはいかないのではと感じている。
それはなぜかというと、学んだ日本語が必ず生かされるとは限らないからだ。もっと言えば、「無駄」な学習になってしまうのではという危惧すら覚えるのが現状である。
なぜそう思うのかということについて、以下私見を語ってみたい。
中国の厳しい受験戦争で賢く闘うための日本語
日中は隣国同士、深い文化的結び付きを持っており、それが色濃く反映されたものとして双方の言語が挙げられる。
漢字の存在は言わずもがなだが、共通語彙もやたらと多い。
とりわけ近代以降、西洋世界から入ってきたさまざまな概念が日本語に訳され、そのまま中華圏に持ち込まれたことから、ややこしい言葉ほど両国で同義語だったりする。
実際、中国語を学んでみれば分かることだが、日本人はとんでもなく大きなアドバンテージを持っており、それは逆もまたしかり。
思えば自分がまだ東京で暮らしていた頃、駅前で「マッサージどうですか」と声をかけてくる中国人のお姉さんたちは、来日1年足らずという人でもなかなかどうして日本語が上手かった。
当時は彼女たちがよほど努力をしたのだろうと思っていたが、今考えてみれば何ということはない。
中国の人々にとって日本語は、全くの初学者であっても身につけやすい言語というだけのことだ。
そこで話は中国の受験に戻るのだが、日本のセンター試験に相当する全国統一大学入試試験「高考」(ガオカオ)には、外国語の選択科目がある。
選べる言語は英語、ロシア語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、そして日本語。
そのうち日本語を選んだ学生の成績が突出してよく、しかも難しくないということで、学生たちが殺到しているのだ。
昨年、とある日本語教育フォーラムで発表された概算データによれば、ここ5年間の受験生の増加ペースは毎年約80%で、昨年は20万人近くにまで達している。
しかも、メリットは単にとっつきやすいという点に留まらない。
試験で必要とされる語彙数は英語が3000から4000語と言われるのに対し、日本語は2000語程度。
そしてここが重要なのだが、英語は各地域で問題が異なる一方、日本語は全国共通なのである。
ものすごく乱暴に言ってしまうと英語の場合、人口が多く教育水準の高い省では他地域と合格者のバランスを取るため、やたらと難しい問題が出される。
それに対し、日本語ならどこでも一緒。
また、日本語クラスを設ける中学・高校も、お受験熱がもともと高い発展地域に多い。
よって、そういう場所の学生さんほど、日本語に駆け込むという手は有効なワケだ。
さらに、学び始めればグイグイズンズン身に付くのでモチベーションを保てる上、アニメや漫画を通じてもともと日本語に親しんでいる場合もある。
日本の比ではない熾烈な受験戦争に晒されている中国の学生たちの間で、日本語人気が高まるのは道理と言えよう。
ちなみに日本語を選択科目とした場合、進学先にはほぼ制限がない。
「ほぼ」と付け加えたのは、国防や軍事関連等の高等教育機関の場合、英語での受験しか認められないからだ。
逆に言えば日本語を選んだからといって、必ず日本語学科に進まなければならないという決まりはない。
受験が終わったら、日本語よサヨウナラーーこういう学生が今後増えてくる可能性は充分にある。なぜなら、中国における日本語とは、もはや決して就職に有利な言語ではないからだ。
日本語学習者たちの期待に応えるために
本来、全ての学びには意味がある。
たとえ社会に出て使わなかったからといって無駄のひと言では切り捨てられないのだが、厳しい就活に直面する学生の場合、話が違ってくる。
日本語を習得した目的が就職のためであり、しかもそれが役に立たなかったら、時間を返せと怒る若者が出てきてもおかしくはない。
というか、自分が中国に来て見てきたのはまさにそういう「日本語を捨てる人々」だった。
「日本語を使う職を探すと、やりたくない仕事だったり、条件がむしろ悪くなるからもうやめた」
こう語って英語圏に再留学し、結局コロナで帰国した友人は、最近会う度に日本語レベルが落ちていると感じる。
同じく、元日本語専攻で現在は国有企業に勤める知人の若者も、数年ほど前に日本語を捨てた。
将来のことを考えて、言語を使う部門ではなくより出世の早い管理部門に移ったのである。
日本の大学で博士号を取り、現在は中国国内の大学で講師を務める女子からも、聞こえてくるのは嘆きの声。
いわく、給料が安すぎて留学の元が取れないというのだ。
でも、これらの人々はまだいい方で、「大学は出たけれど」という日本語専攻の学生は近年ますます増えている。
日本語学科卒の学生が毎年供給されるものの、需要が追いついていないため、どうしても職にあぶれる者が出てしまうからだ。
「日本語能力だけでなく、金融やIT、物流など専門分野が他にないと、今の子たちは就職で苦労しますねえ……」
とは、日本人講師として現地で働く先輩の話。
彼らがせっかく学んだ言語が「無駄」になってしまうのは、突き詰めれば日本自身のせいでもある。
中国における日系企業の存在感は今も決して小さくないが、相対的に見た場合、かつてに比べて弱まっているのは紛れもない事実。
日本がもっと強く、稼げる国であれば、日本語学習者の就職難民はきっと今より減っているだろう。
これは中国に限ったことではなく、我が国でも言えることだろう。
言語はしょせん、ひとつのツール。
中国語ひと筋に生きてきて大陸在住20年余り、コロナで日本に帰国して仕事を探してみたら、就職あっせん業者の人に
「あなたに紹介できる仕事はビックカ○ラの店員くらいしかない」
と言い放たれた知人もいる。
単なる日中バイリンガルなんぞは池袋や西川口辺りにいくらでもいるわけで、言語をキャリアに活かそうと思うなら「もう一役」が大事ということだ。
しかも、同じような現象は中国以外でも起きている。
「せっかく少しは話せるようになった日本語を、最近は使う機会がない。この歳で今から中国語とか韓国語なんて覚えられると思うか」
だからチップをはずんでくれと言ってきたのはアンコールワットで出会ったバイタクのおっさんだが、言語の価値はその国の影響力で決まるのだなとつくづく感じたものだ。
たとえ受験目的だろうが何だろうが、自分たちの言語を学ぶ人々が世界で増えるのは、ジャパニーズとして嬉しいことだ。
だが、少なくない時間を費やして日本語を学ぼうとする人々に、自らの選択を後悔させていては、いずれは日本語、そして日本という国が見向きされなくなってしまう。
海外の日本語話者の期待を裏切らないよう、自国の魅力により一層磨きをかけるーー。
それこそが今の日本に求められていることであり、中国という巨大なパワーに飲み込まれないために必要な取り組みであると自分は信じている。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【プロフィール】
御堂筋あかり
スポーツ新聞記者、出版社勤務を経て現在は中国にて編集・ライターおよび翻訳業を営む。趣味は中国の戦跡巡り。