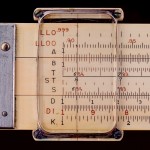参考リンク(1):「鎌倉殿の13人」にも起用…三浦透子は他の女優とどこが違うのか(デイリー新潮)
アメリカのアカデミー賞にもノミネートされている、映画『ドライブ・マイ・カー』。
僕も観たのですが、主役の演出家・家福を演じた西島秀俊さんと同じくらい、あるいはそれ以上に、寡黙で運転が上手い(劇中では「車に乗っていることを感じさせない」と評されていました)「みさき」を演じた三浦透子さんが印象に残りました。
参考リンク(2):【映画感想】ドライブ・マイ・カー(琥珀色の戯言)
冒頭の記事(参考リンク(1))では、子役として演技の世界に入った三浦さんが、さまざまな役柄でキャリアを重ねながらも、芸能界に染まりすぎないように意識してきたことが紹介されています。
5歳でデビューしながら、なぜ女優臭が薄いのかというと、それは本人が意識的にそういう生き方をしてきたから。早くから女優を一生の仕事にしていくことを決心したからこそ、多くの芸能人が歩みがちな道を選ばなかった。
三浦「この仕事が当たり前である人生を歩んできてしまったので、そうじゃない世界を知りたかったんです。いや、知る時間を作らなくちゃと思ったというか。だから高校も一般の高校でしたし、大学にも行こうと思いました」
2019年に卒業した大学では数学を専攻。プログラミングなどを学んだ。女優という職業を持ちながら、進級も卒業も簡単ではない数学を専攻するのは異例と言える。しかも在学中は家庭教師のアルバイトもやっていた。
芸能界で仕事をしながら、一般の高校から大学、それも理系の学部で数学を専攻するって、すごいことですよね。
基本的に、学ぶこと、考えることが好きな人なんだろうなあ、とも思います。
僕はこれを読んで、以前、中谷美紀さんの著書『ないものねだり』(幻冬舎文庫)の巻末の「解説」で、映画監督の黒沢清さんが書いておられた話を思い出しました。
今でも強烈に印象に残っている撮影現場の光景がある。中谷さんに、沼の上に突き出た桟橋をふらふらと歩いていき、突端まで行き着いてついにそれ以上進めなくなるという場面を演じてもらったときのことだ。これは、一見別にどうってことのない芝居に思える。正直私も簡単なことだろうとタカをくくっていた。だから中谷さんに「桟橋の先まで行って立ち止まってください」としか指示していない。中谷さんは「はい、わかりました。少し練習させてください」と言い、何度か桟橋を往復していたようだった。最初、ただ足場の安全性を確かめているのだろうくらいに思って気にも留めなかったのだが、そうではなかった。見ると、中谷さんはスタート位置から突端までの歩数を何度も往復して正確に測っている。私はこの時点でもまだ、それが何の目的なのかわからなかった。
そしていよいよ撮影が開始され、よーいスタートとなり、中谷さんは桟橋を歩き始めた。徐々に突端に近づき、その端まで行ったとき、私もスタッフたちも一瞬「あっ!」と声を上げそうになった。と言うのは、彼女の身体がぐらりと傾き、本当に水に落ちてしまうのではないかと見えたからだ。しかし彼女はぎりぎりのところで踏みとどまって、まさに呆然と立ちすくんだのだ。もちろん私は一発でOKを出した。要するに彼女は、あらかじめこのぎりぎりのところで足を踏み外す寸前の歩数を正確に測っていたのだった。「なんて精密なんだ……」私は舌を巻いた。と同時に、この精密さがあったからこそ、彼女の芝居はまったく計算したようなところがなく、徹底して自然なのである。
つまりこれは脚本に書かれた「桟橋の先まで行って、それ以上進めなくなる」という一行を完全に表現した結果だったのだ。どういうことかと言うと、この一行には実は伏せられた重要なポイントがある。なぜその女はそれ以上進めなくなるのか、という点だ。別に難しい抽象的な理由や心理的な原因があったわけではない。彼女は物理的に「行けなく」なったのだ。「行かない」ことを選んだのではなく「行けなく」なった。どうしてか? それ以上行ったら水に落ちてしまうから。現実には十分あり得るシチュエーションで、別に難しくも何ともないと思うかもしれないが、これを演技でやるとなると細心の注意が必要となる。先まで行って適当に立ち止まるのとは全然違い、落ちそうになって踏みとどまり立ち尽くすという動きによってのみそれは表現可能なのであって、そのためには桟橋の突端ぎりぎりまでの歩数を正確に把握しておかねばならないのだった。
と偉そうなことを書いたが、中谷美紀が目の前でこれを実践してくれるまで私は気づかなかった。彼女は知っていたのだ。映画の中では全てのできごとは自然でなければならず、カメラの前で何ひとつゴマかしがきかないということを。そして、演技としての自然さは、徹底した計算によってのみ達成されるということを。ところで、このことは中谷さんの文章にもそのまま当てはまるのではないだろうか。
「アート」とか「芸能」「スポーツ」「創作」の世界では、「センスが良い」なんて言葉がよく使われますよね。
天から与えられた才能がある人は、他の人ができないことを、無意識のうちに、あるいは当たり前のようにやってしまうように見えるのです。
実際、才能の違いというか、同じ経験値を得てもレベルアップのしかたには差がある、というのは事実だと思います。
でも、周りが「あの人は才能がある。センスがいい」と思っている人の多くは、けっして「センスなんていう曖昧なものを信用してはいない」のです。
役者として「演じる」という仕事は、僕には縁遠い仕事であり、「できる人はできるし、センスが無い人はずっと大根役者なんだろう」と漠然と考えていたのですが、この中谷美紀さんのエピソードを読んで、僕は思い知らされました。
「演技としての自然さは、徹底した計算によってのみ達成される」
矛盾しているようですが、たしかに「(精神的に)演じる役柄になりきる」だけでは、結果的に「自然な(自然にみえる)演技」にはならないのです。
そもそも、脚本を読んで演じている役者と、桟橋の先が行き止まりであることを意識していない登場人物が「同じ感情」にはなれません。
内心が「同じ」にはなれないからこそ、そういう状況での身体の動き、を計算し、再現するのです。
演技とかアートの世界って、外部からみれば、「内から湧き上がってくる情熱とかセンス」の有無で勝負が決まるようにみえます。なんのかんの言っても、役者さんは「見た目が大事」ではありますし。
でも、アメリカでは、有名な大学に「演劇科」があり(日本にもいくつか存在します)、そこで長年積み上げられた「演劇理論」が教えられているのです。
天賦の才能を持った人は、他の人よりも飲み込みが早いし、理論なんて学ばなくても、ある程度のところまではいくこともある。周りからは「才能がある」ともてはやされ、本人もその気になってしまう。
ただ、そうやって、センスだけでやっていると、いつか壁に当たることが多いのです。
これは、仕事でも、勉強でも、スポーツでもそうだと思います。
野村克也さんは、「自分には並外れた才能はなかったけれど、『頭を使って野球をする』『相手のピッチャーの配球やチームの作戦をひたすら考える』ことで、プロ野球界で生き残ってきた」と、著書のなかで何度も仰っています。
どの世界でも、よりレベルが高いところに行けば行くほど、「才能やセンス」だけでは頭打ちになってしまうのです。
「早熟の天才」や「神童」よりも、才能が乏しいことを自覚して、問題を解決するプロセスを積み重ね、挫折することにめげなくなった人のほうが、長い目でみれば大成することもあります。
「自分には才能がない、センスがない」と嘆いている人は、まず、先人が積み上げてきた「基礎」や「理論」に立ち返ってみるべきなのかもしれません。
やみくもに「自分が『練習』だと思っていること」を重ねるよりも、一度立ち止まって、道を知っている人に尋ねたほうがいい。
こういう話を読んでいて考えてしまうのは、「芸能」とか「創作」「スポーツ」などに限らず、世の中には、日常生活でも意図的に感情を演じ、使い分けている人がいるのだろうな、ということなんですよ。
「感情的」と「理論的」は反対の位置にあるものだと思われがちで、だからこそ「感情的な言葉や態度」は状況によっては大きな効果や影響があるのです。
「感情的」=「本心」だと多くの人は感じやすい。
しかしながら、「腹が立ったから怒る」のではなくて、「ここは怒ってみせたほうが相手をコントロールできる」という「目的達成の手段として、感情的にみえる行動をとれる」人って少なからずいるし、TPOによっては、僕だってそういうことをやっているのです。
そういう人は「サイコパス」なんて言葉で呼ばれるのですが、みんな多かれ少なかれ、「サイコパス的な要素」を持っているし、そうじゃないとこの世界を生きていけないのかもしれません。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
著者:fujipon
読書感想ブログ『琥珀色の戯言』、瞑想・迷走しつづけている雑記『いつか電池がきれるまで』を書きつづけている、「人生の折り返し点を過ぎたことにようやく気づいてしまった」ネット中毒の40代内科医です。
ブログ:琥珀色の戯言 / いつか電池がきれるまで
Twitter:@fujipon2
Photo by Kyle Head