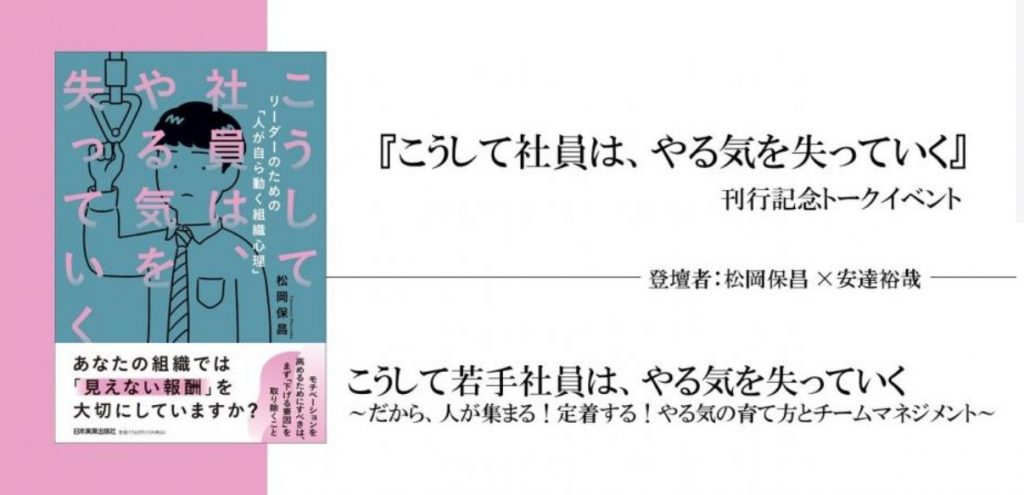『こうして社員は、やる気を失っていく』という書籍が売れていると聞きました。
もしかしたら「日本人は死ぬほど会社が嫌い」という現実を表しているのかもしれません。
その際、編集者の方から、その本のプロモーションとしてイベントをやるのですが、登壇しないかとお誘いを受けたのです。
少し考えましたが、結局お引き受けしました。(イベント詳細は、記事末尾です)
その理由は、この本の序章に書かれている「部下のやる気を高めようとするより、やる気を削ぐ行為を直ちにやめろ」というメッセージをもっともだと思ったからです。
他人のやる気は操作できない
私が考える「やる気」に関する議論で最も重要なのは、「他人のやる気は、都合よく操作できない」という点です。
というのも、人のやる気というものは、仕事だけではなく、様々なプライベートな要因によっても、上がったり下がったりするからです。
*
かつて「管理職研修」の講師をやっていたこともあり、私は部下の「やる気」に、とても気をつかっていました。
特に、会社からも「社員には、やりたいことをやってもらおう」という方針が出ていたため、マネジャーになってからは「どうやって部下のやる気を上げようか」と悩みました。
そんなある日、私は普段頑張っていた部下の一人が、元気がないと気づきました。
お客さん先なのに落ち込んでいて、明らかに仕事が手についていないようなのです。そこで「これは良くない」と思い、後で理由を尋ねたところ、
「そんな風に見えます?」と言われました。
「普段と違うとは思う」というと、彼は
「すいません、プライベートの事情で落ち込んでます。」
というのです。
ああ、なるほど。
勘違いしていた。
そう思いました。
つまり、お金をもらっているプロであれば、「仕事のやる気」と「プライベート」は切り離されており、プライベートの状況によらず、仕事を遂行するという思い込みは、間違っていたのです。
確かに都合よく切り離せる人もいるでしょうが、そうでない人もまた、数多くいるのです。
いや、むしろ仕事とプライベートが地続きの人のほうが多い。
そんな当たり前のことに気づいたのです。
だから、こんな理由で、たやすく仕事のやる気は下がります。
パートナーにフラれた。
親類縁者が重い病気になった。
娘の受験がうまくいかなかった。
昨日夫婦ゲンカした。
二日酔いになった。
好きなアイドルのスキャンダル。
最近太った。
ランチがおいしくなかった。
財布を落とした。
むしろ、人生における仕事の優先度が低い人は、「好きなアイドルのスキャンダル」に心奪われて、仕事どころではない、という事が普通にあるのです。
そして、ここから得た教訓は、「上司がいくら踏ん張っても、人のやる気は予測不能かつ、操作不能」という事実です。
上司は部下のプライベートで下がった「やる気」に責任を持つ必要などない。
「それはそれ、これはこれ。プライベートで悩んでいるなら休みをとれ、出勤するなら仕事しろ」と言えばいいのです。
上司はせめて「部下のやる気」を削ぐようなことはするな。
ただし、これをもって上司が「部下のやる気」に無関心でよいという事にはなりません。
というのも、上司が「やる気を削ぐ原因」になるケースも多いからです。
例えば、上述した『こうして社員は、やる気を失っていく』には、こんな「やる気を削ぐ上司」のケースが記載されています。
・理由や背景を説明しない──「意味のない、ムダな仕事」と思わせる上司
・一方通行の指示──双方向のコミュニケーションがとれない上司
・話を聞かずに結論を出す──頭ごなしに決めつける思い込み上司
・意見も提案も受け入れない──「自分が絶対」のお山の大将上司
・言うことに一貫性がない──行き当たりばったり上司
こんな上司であれば、プライベートに関わらず、会社が憂鬱な場所となるのは無理ありません。
上司がわざわざ、仕事を邪魔しているようなものです。
私のかつてのボスは、こう言っていました。
『上司の役割は、部下の靴の中の石ころを取り除いて、走りやすくしてあげることだよ』と。
それはつまり、上司は部下の仕事の障害を取り除くことがメインの仕事であり、「部下のやる気を上げよう」なんて考えなくていいということ。
そして、せめてやる気を削ぐようなことはするな、という意味だと私は理解しています。
*
以下、『こうして社員は、やる気を失っていく』トークイベントのご案内です。
日時:2022/09/21 (水) 19:00 – 20:30 【店頭参加およびオンライン参加】
数多あるマネジメント書籍ではモチベーションを高め、高い意識で目標に突き進むチームを創り出していくことを目的としています。
しかし、そういった意識向上を果たしたチームの影に、振り落とされてしまった人々がいるのではないでしょうか。
本イベントは、社員のモチベーション管理と組織管理を題材にした対談イベントとなっており、モチベーションの下がらないチームの形成を扱います。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者プロフィール】
安達裕哉
元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)