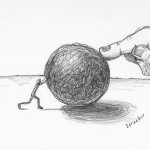警察当局と事件記者は不思議な関係にある。
以前にも記事にしたことがあるが、過去に事件記者をやっていた身からすると、やはりマスコミというのは何事においても「ほかのマスコミよりも自分達がいちばん最初に報道したい」という欲が強い。
筆者もそのひとりだった。
しかし最低限の「マナー」がある。
容疑者逮捕や家宅捜索前の「前打ち報道」は、万が一容疑者の目に留まってしまうと逃亡や証拠隠滅に繋がりかねない。
そして、事件を潰すのはマスコミの本望ではない。
よって当局と記者はギリギリの「交渉」をする。
そのためにはいくつかの慣習があるが、筆者はそれを守ったにもかかわらず長期間、担当幹部から「課内出入り禁止」をくらい、エレベーターで出会ってもシカトされるということがあった。
事件記者と捜査当局の間にある「交渉」
警視庁がある事件の内偵捜査を進めている。
しかも今回はありふれた事件ではなく珍しい検挙事例で、ニュースバリューは高そうだ。
筆者はその情報を先輩記者から聞き、各所で調査や取材を静かに進めた。
そして、捜査対象の姿が浮かび上がってきた。
そして具体的な社名を「ここかな」というところまで絞った。ただ100%の確信にまでは至らなかった。
多くの内偵捜査事件において、事前に情報をコンプリートするのは、基本的には難しい。
そして、先走りにはリスクがある。当てずっぽうに取材をかけたとして、しかしそれが全く関係なかった場所の場合は収まりがつかなくなってしまう。ヘタをすると名誉毀損にあたる。
では、そんな時、どうするか。
当局と「交渉」に入るのである。
「報道協定」という言葉をご存じだろうか。
事件の発生を知らせつつ、当局はマスコミ各社に報道自粛を求めるというしくみだ。
何もこれは、事件のもみ消しのためにあるわけではない。簡単に言えば「報道されることによって被害者の命に危険が及ぶ可能性がある」ときに、当局とマスコミが話し合ったうえで発効するものである。
ことの発端は1960年代にさかのぼる。東京で男児が誘拐される事件があった。
当時のマスコミは犯人の要求や捜査の様子などを逐一報道した。男児は殺害されてしまったが、逮捕後に犯人が「新聞報道で追い詰められた」と供述したことでマスコミ各社は大きく反省することになる。
報道が被害者の殺害を後押ししてしまう可能性があるという問題が見つかったわけだ。
そこで現代では協定が成立したとき、マスコミは当局から逐次レクチャーを受けつつも、容疑者確保などのきっかけで情報解禁されるまでは報じないという形になっている。
捜査幹部の「もうひとつの」仕事
警視庁では一般的に、内偵捜査の場合、所轄の事件なら副署長、本部が捜査している事件の場合は担当課長といった幹部がマスコミ対応をする。
そして記者から「こんな事件を捜査してますよね」と「当てられた」時、彼らがうまく話を運ばなければマスコミが好き放題に前打ち報道をしてしまう。あるいは張り込みなどをしてしまい、捜査対象に気づかれてしまう。
よって、ここから腹の探り合いが始まり、win-winの関係に持ち込めるかは記者と幹部、互いの腕の見せ所だ。
報道協定事案でない限り、本来マスコミはこれから掲載する記事の内容を当局に伝える必要はないし、当局もそれを一方的に止めることはできない。よって当局にとっては、どこのマスコミが事件を嗅ぎ回っているかを把握することも重要になる。
ただ、多くの場合、前打ち報道をするには情報が少し足りなかったり、あるいはコンプリートしていても事件を潰したいわけではない、あるいは恩を売るという理由で、幹部から「どの社よりも先に書かせてあげるから」「他の社には与えてない情報をあげるから」といった優位性を約束してもらい、時を待つこともある。
少なくとも「あすの朝刊で書きますよ」など、「通告」をするのが慣例でもあった。もちろん、それをしない記者もいたが。この「通告」の慣習を守らなければ、担当部署から2週間の出入り禁止を受ける、という、今考えれば謎ルールもあった。
さて、筆者が追っていた事件である。筆者はすでに、裏で被害者にも取材を進めていた。そして最終的な情報確認、念押しをするため、担当の幹部に情報を「当て」に行った。
しかし、そこでの幹部の反応は予想外のものだった。
イエスノークエスチョンにもならないような会話しかしてもらえなかったのである。
さらに、捜査対象の企業の元社員にまで取材を進めた上で、もう一度念押しの確認に行った。
筆者の中で99%の確度だったものを100%にするためだった。
ここでも「交渉」とはとても呼べないようなイエスノークエスチョン、しかも1つの確認事項についてぶつけたことに対して「そうだよ!」とインターホン越しに不機嫌に伝えられただけである。またお前か、と言わんばかりに。具体的な社名すらお互いの口からは出なかった(筆者は確信していたが)。
大前提として、彼らは何を聞かれても嘘をつくことはできない。警察なのだから当然である。
その範囲で記者をどうコントロールするかが彼らの仕事でもある。事件の指揮だけではないのだ。
しかしこんなあしらいを受けたのでは交渉とは呼べない。そう判断した記者は、家宅捜索の日の早朝、その幹部が自宅から出てきて車に乗ろうとした時に、「書きます」とだけ伝えた。
相手はめっちゃ怒った顔をしていた。
しかし、知るもんか。あなたがやってくれたことは「嘘をつかなかった」ことだけで、まともに向き合わなかったのだから。だから報道した。ご丁寧に通告をしてからである。
独走状態の記者が怒鳴りつけられた
驚いたことに、これがクリーンヒットだった。
幹部の自宅への「朝周り取材」「夜回り取材」に関しては、記者同士の間にも暗黙のルールがある。一番最初に待っていた記者が「囲みではなく個別取材を少しだけしたい」と伝えれば、他の記者はそれを許すというものだ。
筆者はその日の朝、いったい何時から待っていたことだろうか。そして後から来た記者に「個別」の時間をもらう約束を取り付け、そのことを通告した。
しかし他の記者は、別の、ほとんど各社が知っている事件の進捗確認に幹部の自宅に来ていたため、実際この事件は、筆者だけが独走状態で取材を進めていたのだ。
筆者の報道後、その幹部のもとにはマスコミ全社の問い合わせが殺到する。
犯人の身柄を確保した後に会見が始まるが、それを待っていられないのである。
さて、その後。筆者はその幹部から呼び出しを食らった。
そして、座る間も無くドアの前でいきなり怒鳴りつけられた。
筆者の心の中では「だから書くって通告したじゃないですか」である。怒鳴られるほどの理由はない。それも、ご丁寧に家宅捜索が入るまではカメラマンを隠していたのだから良心的なくらいだ。逃走した容疑者もいなかった。
一方的に怒鳴られ、出入り禁止を告げられた。
100歩譲って「出入り禁止」というのは他社との公平性を保っていますというパフォーマンスであったとしても、エレベーターに乗り合わせて挨拶をしてもシカトされる。パワハラの領域である。
怒りの根源にあったもの
彼の怒りの根源を、筆者はこう察している。
ひとつは「若いねえちゃんにやられた」ということだろう。ベテラン記者ならともかく、相手は社会に出てまもないねえちゃんである。
もうひとつは、この幹部は筆者の情報源を自分の上司だと疑っていた。
自分の頭を通り越した、コントロールのきかない場所で情報のやりとりが行われていたと疑い、怒りを感じていたのである。
しかし、あなたは私の保護者か?
そんなことは、筆者にとってとばっちりでしかない。
仮にそうであったとしても、責められるべきはその幹部の上司であって、筆者ではないはずだ。そう思うならまずあなたの上司を問い詰めればいいのに、という話である。
しかし筆者は情報源に関しては、情報源については何を聞かれてもイエスともノーとも言えない。情報源の秘匿という、記者にとって最も重要な原則があるからだ。
結局こちらからは何も発言する余地もないまま、部屋を追い出された。
捜査幹部にとって、記者とのこういう関係は、実はまずいものなのである。じゃああなたのところの事件、あなたが相手をしてくれないなら今後好き放題書きますね、となってしまうからだ。ますますコントロールできなくなってしまう。
私憤をぶつけられても困る
筆者からすれば、この幹部の対応は「私憤」からきたものでしかないと思っている。しかしぶつける相手を「推測」だけで決めている。
彼は勝手に自分の上司を疑った。
しかし筆者はのちにその「上司」にも話を聞いた。部内で何かがあったのかと。しかし何の情報もなかった。何も言われていない、ということだけだ。
結局、その幹部は疑いを上司にぶつけることはせず、弱い立場にある筆者だけを怒鳴りつけたことがわかったのだ。
本人が「自分の上司が情報源である」ことを確信できなかったからだろう。
カウンターパートである彼が合理的に怒る理由を説明できないまま、「私憤」を部下や弱そうな人たちを相手に発散しても、それは何の意味もなさないどころの話ではない。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【プロフィール】
著者:清水 沙矢香
北九州市出身。京都大学理学部卒業後、TBSでおもに報道記者として社会部・経済部で勤務、その後フリー。
かたわらでサックスプレイヤー。バンドや自ら率いるユニット、ソロなどで活動。ほかには酒と横浜DeNAベイスターズが好き。
Twitter:@M6Sayaka
Facebook:https://www.facebook.com/shimizu.sayaka/
Photo:Matt Seymour