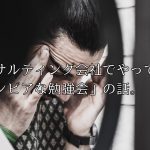ゾッとする話
とある友人の話を聞いた私は、思わずゾッとした。その内容とはこれだ。
「息子が小学生の頃の話だけど、右手の薬指だったかな?ばい菌が入って膿んじゃったのよ」
話はさらに続く。
「それで皮膚科を受診したんだけど、その時の光景が未だに脳裏に焼きついて離れないの」
ほぅ、それはいったいどのような光景なのか?
「膿んだせいで少し浮いてる爪を見た先生が、『お母さん、息子さんの顔をちょっとあちらへ向けてもらえますか?』って言うから、(息子の)顔をグイッと横へ向けたのね。そしたらその瞬間、先生がピンセットで爪をピッて剥がしたのよ!」
・・なんということだ。つ、爪を一気に剥がしただと!?
しかし、爪と肉の間に膿が溜まって浮いているわけだから、抗生物質を塗りこむよりも、爪を剥がすほうが治療もしやすく治癒も早い。つまりドクターの判断は正しく、そこについては特筆すべきことはない。
それよりも、「爪剥ぎ」の一部始終を目の当たりにした母の心境たるや、想像を絶する衝撃的な光景だったわけだ。
「先生は慣れているんでしょうね。顔色一つ変えずにシレっとしていたわ。でも、息子の顔を横に向けた瞬間、ほんとその瞬間に、ピッと剥がしたのよ。それで私が『え?!』と思った時にはもうガーゼが当てられていたから、息子は何が起きたか知らずに終わったのよね」
これはもはや「驚いた」どころの話ではない。目の前で最愛の息子の爪が剥がされたわけで、しかも、なんの前触れもなくいきなりピッとやられたのだから、母の思考が停止するのは当然のこと。ましてや、ここで母親がうろたえでもすれば、何かを悟った息子が恐怖を感じて泣き叫ぶ可能性もあり、不穏な挙動は避けなければならない——。
そんな葛藤と戦いつつも処置は終わり、親子は無事に病院を後にしたのである。
(爪を瞬間的にピッと剥がすって、テーブルクロス引きみたいな感じなのかな・・)
テーブルクロス引きとは、テーブルに敷かれた布の上に食器を並べた状態で、布を一気に引き抜く一発芸のこと。食器を倒すことなく布を引き抜く技術や精神力は相当なものだろう。
話を戻すが、一瞬で爪を剥がすという行為を明確にイメージすることができない私は、皮膚科医になるのは無理だと思った。
テーブルクロス引きもかなりの集中力と度胸を要するが、対象が「人間の爪」となると、テーブルクロスどころではない度胸と覚悟が必須なわけで。
もしも一瞬の迷いが生じれば、患者は激痛に悶えることとなり、皮膚科というものがトラウマになるだろう。それこそ拷問のような痛みと恐怖を与えるわけで・・これ以上想像するのは止めにしよう——。
よくよく考えると、歴史上さまざまな拷問が行われてきたが、その一つに「爪剥ぎ」が挙げられる。
読んで字のごとく「生えている爪を剥がす行為」であり、爪と肉の間に針やヘラなどを突き刺すことで強烈な痛みを与えつつ、対象者から自白を迫るという恐ろしいやり方だ。
文字にするだけでも背筋がゾクゾクするが、そのくらい爪を剥がすという行為は人間にとって恐怖の象徴であり、地獄の痛みを意味するのである。
・・という話を、私は今この瞬間に思い出した。プチンという鈍い音とともに、友人のアノ話が頭をよぎったのだ。
(あぁ、きっとこういうことだったんだ・・)
首に現れた異常
中年女性にとって、「加齢」ほど恐ろしい現象はない。
化粧や服装でカバーできる部分には限界があり、しかもやりすぎれば「痛いババァ」となるわけで、その塩梅は非常に難しいのである。
とくに相手から視認されやすい顔や首、手の甲については、歳を重ねるごとにチェックが厳しくなるわけで、カネをかけてでも若さを手に入れたいと願うオバサンは少なくないだろう。
そんな中年真っ盛りの私は、自分の首にちょっとした異変を感じた。
なんだろう?と鏡を覗くも、違和感は耳の下辺りのため見づらくてよく分からない。ならばとスマホで撮影してみるも、距離が近すぎて鮮明に写らない。いよいよ不安になった私は、首の異常についてネット検索を行った。
「首 小さなイボ」
・・そう。私は、首に1ミリ程度の突起物の存在を確認したのだ。幸いなことに一つだけなので、気にしなければ何事もなく過ごせるのだが、多くの中高齢者の首に小さなイボがあることを思い出した私は、これが「加齢に伴う老化現象なのではないか」と青ざめた。
だがどれほど検索しようが、自分の「それ」とネット上の「それ」が同じかどうかは分からない。仮に同じだからといって、放置することもできない。——これは、皮膚科へ行くしかないな。
首のイボの検索をやめて、近所の皮膚科を調べ始めた私は、徒歩3分のところにオンライン予約のできる皮膚科を発見した。
(明日の朝一番に診てもらおう・・)
対面のみならずオンライン診療も行っているクリニックで、支払いをクレジットカードで済ませられる点も魅力的。あぁ、早く明日にならないかな——。
そして翌朝。予約時間ピッタリに皮膚科を訪れた私は、若い女医の前に座らされた。
「えっと、どこですかね?」
私の首に齧りつきながら、可愛らしい女医が尋ねる。
「んー、たしかこの辺です・・」
指先で首をさすり、小さな突起の部分で止めた。
「あぁ、これですか。ちょっとあっちを向いててください、取っちゃうんで」
発言の意味を深くは考えなかった私は、おそらく液体窒素か炭酸ガスレーザーを使って除去するのだと予想した。なぜなら、昨晩ネットで調べまくった結果がそれらの方法だったからだ。
いずれにせよ、まずは患部を診察した上で、どちらの処置にするのかを決めるのだろう——。
そう勝手に思い込んだ私は、女医に顔を押されるがまま右を向いた。その瞬間、プチン・・という小さな鈍い音が聞こえたのだ。
あまりに瞬間的な出来事だったため、何が起こったのかは分からないが、彼女の右手には銀色のピンセットが光っている。
つまり、あのピンセットから音が鳴ったのだ。・・・え?
何食わぬ顔でピンセットを置いた女医は、呆気にとられてきょとんとしている私を見ると、
「これ、医療用のハサミなんですよ」
と笑顔で説明してくれた。つまり、ちょっと右を向いた瞬間に、そのピンセット型のハサミで私のイボを・・言い換えると、私の皮膚の一部を切り取ったわけか!?
時間にして一秒もかからなかった。
すべてを理解した途端、いや、正確には「プチン」という音を聞いた瞬間に、私は前出の友人の話を思い出したのだ。顔色一つ変えずシレっと爪を剥がした、あの皮膚科医の手際の良さを——。
たしかに、1ミリにも満たない小さな突起を切除するだけなのに、「今からハサミで切りますよ、いいですね?」とか、「少し痛いかもしれないけど、いきますよ?」などと言われたら、むしろガチガチに身構えてしまい、わずかな痛みが無駄に倍増するだろう。
実際のところ、切除の瞬間に痛みは感じなかった。というか、痛みを感じるようなことをされるとは、これっぽっちも思っていなかったため、何が起きたのか分からなかったのだ。
ピンセットで皮膚をつままれる感覚はあったが、まさかそのままプチッとやられるとは、予想だにしなかったわけで・・。
(なるほど。これはテーブルクロス引きとは別のテクニックが必要だな・・)
皮膚科医に求められる能力
とにかく、皮膚科医は懇切丁寧に状況説明するよりも、タイミングよくパッと処置する度胸(?)が必要である。
少なくとも私は、痛みという恐怖を滔々と語られるくらいなら、「そんなことはいいから、パパっとやっちゃって!」と思うからだ。
加えて、ピンセットの使い方に長けていなければならない。ある時は爪を剥ぎ、ある時はイボを切り取り、ピンセット一本で瞬時に処置を済ませる、マジシャンのようなテクニックが必要なのだ。
(了)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
URABE(ウラベ)
ライター&社労士/ブラジリアン柔術茶帯/クレー射撃スキート
■Twitter https://twitter.com/uraberica
Photo:Diana Polekhina