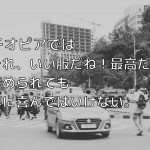クライアントとの仕事の中で、あらゆる組織に「仕事の早い人」と、そして逆に「仕事の遅い人」が存在していることを見てきました。
では、仕事が早い人と遅い人の差は、何にあるのでしょうか。
*
まずここでは、良質なアウトプットを期限内に余裕を持って仕上げる人を「仕事が早い」と称します。
それに対して、期限内に結果を出せない人や、期限ギリギリで低品質な成果を出す人を、「仕事が遅い」と呼びます。
ただし、この議論は、往々にして単純化されがちです。
仕事が遅い人は、優先度を間違っている!
とか。
仕事が早い人は、PDCAが早い!
とか。
仕事の速さは、「コミュニケーション力で決まる!」
とか。
キャッチな言葉で、仕事の速さに言及するという事が良く行われます。
しかし、この議題を単純化することは適切ではありません。
実際、仕事のスピードアップや効率化は一つの要因だけで操作できるようなものではなく、多岐にわたる要素が絡み合う総合芸術と言えるのです。
つまり、原因を単純化して、キャッチに踊らされても、それほど成果に結びつかないことが多い。
実際、製造業では、リードタイム短縮のためには、あらゆる細かな改善を行います。
細かく「無駄」を突き詰めて、一つ一つを修正していく。
そうして、初めて「生産性の向上」という果実を得ることができます。
そういう意味で、「仕事が早くなる」というのは、製造業の地道なカイゼンに近い行為です。
*
例えば、コンサルタント時代に「仕事が遅い人」に対して、改善が要求された項目は、大まかに分類して以下のような7つのポイントに分類し、アタリを付け、少しずつ改善をしてきました。
1. 取り掛かるまでが遅い
最初の一歩を踏み出すことは、仕事の効率性において非常に重要です。
ここで重要なのは、まずは手を動かし始めること。
例えば、企画を書かねばならないのであれば、何でもいいのでアウトラインを書き始めてしまうこと。
テレアポであれば、まず受話器を取って1件目に電話をすること。
実際、脳科学の成果で「やる気は、やり始めると湧いてくる」ことがわかっています。
2. 集中力を出すまでが遅い
仕事を始めたら、次は集中することが求められます。
ここで何より重要なのが、意図しない仕事の中断を避けることです。
そのためには例えば、
「使える時間を細切れにせず、大きくまとめること」
「身の回りに気の散るもの(例えば携帯や本など)を置かないこと」
「メールやメッセンジャーへの返信はスキマ時間に行うこと」
「安易に話しかけられない場所で仕事をすること」
「集中できる時間帯(例えば午前中)に頭を使うこと」
などの工夫が挙げられます。
3. 意思決定するまでが遅い
仕事を進める過程での迅速な意思決定は、効率性の向上に欠かせませんが、往々にして、「決めなければならない」シーンでは、十分な情報がないままであっても、迅速に意思決定をする必要があります。
例えば、「サイトのデザイン」が3種類あって、どれに決めなければならない時があります。
あるいは「採用の可否」でも、「web広告の出稿を継続するかどうか」「納期遅延が発生しそうなプロジェクトの状況報告」なども同じです。
しかし、先送りは状況が悪化することはよくありますが、良くなることはほとんどありません。
そんな時有効なのが、「メリット」「デメリット」を言語化して洗い出すことです。
得られるものとコストを可視化することで、迅速に取捨選択をすることが可能になり、失敗したとしても、反省する材料となります。
4. たたき台を出すまでが遅い
アイデアを形にするためには、まずはたたき台を素早く作成することが必要です。
この際に重要なのは、適切にツールを活用することです。
早い段階で具体的な形に仕上げることができます。
少し前までは事例を調査したり、テンプレートを利用したりする方法が一般的でした。
が、最近では特に、ChatGPTをはじめとする生成AIが、「たたき台」を圧倒的なスピードで生成してくれますので、仕事のスピードが飛躍的に上がった、と感じている人も多いようです。
5. 成果品を仕上げるのが遅い
仕事道具、あるいは業務ツールやソフトウェアへの習熟度が高いと、成果品の作成速度も向上します。
例えば、エクセルやイラストレーター、コーディングの開発環境なども、ツールに習熟すればするほど、仕事は早く済みます。
日常的に使用するツールに関しては、定期的な学習や、最新情報へのキャッチアップの習得を心がけなければなりません。
職人にとって、使う道具は魂が込められているのと同じです。
6. 相談が遅い
人間の得意分野には限りがありますから、全てを自分一人で解決しようとせず、周囲の人々の知識や経験を活用することも重要です。
ですから、得意な人にどんどん聞いて、マネをしましょう。
そもそも、仕事においては芸術家や学者でない限り、「オリジナリティ」はあまり重要ではありません。
独自性を追求するあまり、他者の意見を無視するのは仕事が遅くなる大きな原因の一つです。
また、「自分から提供できるものがない」からといって、引け目を勝手に感じて、できる人に聞かないのも仕事を遅らせる原因となります。
妙なプライドは捨てること。
会社員は、作品を作っているのではなく、仕事の成果をあげるために雇われているのです。
7. 改善が遅い
最後に、自分の成果に対するフィードバックや指摘を受け入れ、それをもとに作業の改善を行うことが大切です。
特に成果品を受け取る先、例えば、上司や顧客、あるいは別部署の担当者などからのコメントは、大きく仕事のクオリティを上げるチャンスだと思って聞きます。
もちろん、すべての意見を受け入れる必要はありませんが、「仮にフィードバックをもらったことを改善したら、何が起きるのか?」をシミュレーションしてみることは、時間を使う価値がある行為です。
以上が、「仕事の遅い理由」を分類し、言語化したものの一覧です。
作業のスピードアップをしたいと願う時に、最初のとっかかりとして使うには、まあまあ使えるほうだと思います。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
安達裕哉
元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)
Photo:toine G