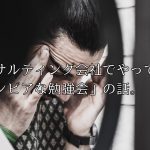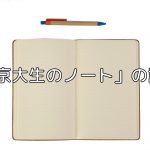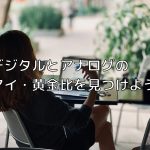新人を育成するときに、まず有効なのは現場での指導、いわゆるOJTです。
が、同時にOff-JT、いわゆる座学である「研修」や「勉強会」なども合わせて行うと、OJTの効果が高まることを、経験的に知っている人も多いでしょう。
私が在籍していたコンサルティング会社でも、上の2つの教育は併用されており、それぞれに目的がありました。
OJTは純粋に、お客さんのプロジェクトを進めるためのスキルを教える場所。
そして、Off-JTである勉強会は、そのスキルを「標準化」する場所でした。
コンサルティング会社における標準化というと、何やら難しげに感じるかもしれませんが、非常に単純で、以下の3点からなります。
1.現場の属人的な技術を「ツール」に落とし込むこと
2.ツールの使い方を新人に指導すること
3.既存のツールの改善をすること
ここでいう「ツール」とは、例えば
「提案書のテンプレート」
「顧客向けの勉強会テキスト」
「各種の現状調査票」
「サンプルの様式類」
などを総称したものを指し、コンサルタントによる「サービス品質のばらつき」を極力減らし、仕事の効率を上げるために使うものでした。
実際、多くの仕事において、その質は3つの要素によって決定されます。
一つは、仕事をする人の素質。
二つ目は、教育・訓練。
そして三つ目が、標準化。
素質は採用の際に検証します。
そして、その人が持つ素質を、教育と標準化でその素質を強化してやることで、顧客へのサービス品質を高める。
それが、私が在籍していたコンサルティング会社の方針でした。
「勉強会」という名のサービス品質チェック
とまあ、ここまではある意味「普通」の話なのですが、実際には勉強会には「裏の顔」がありました。
それは、社長や幹部たちによる、現場のチェックです。
コンサルタントたちが、質の低いサービスをしていないかどうか、細かくチェックをする場でもあったのです。
ですから、勉強会の題材は、ほとんどが「現場の事例」でした。
題材として指定されたプロジェクトは
・プロジェクトの概要
・お客さんとのやり取りの記録
・成果品
などを、参加者全員に提出し、全員から質問や疑問点を受け付けます。
幹部から、「このやり取りには重大な問題がある」という指摘を受け、それを全員でディスカッションすることもありました。
プロジェクトが丸裸にされますから、当人たちにとってみれば、一種の内部監査、プロジェクトの抜き打ち調査を、全員の前でやらされるわけです。
もちろん、質の低いコンサルティングが見つかると、プロジェクトの担当者は一種の「吊し上げ」状態になります。
ですから、勉強会はいつも、異様な緊張感に包まれていました。
「恥をかいて学ぶ」
そんなわけで、コンサルタントとしては、勉強会というのは、「楽しいものだ」というイメージは全くありませんでした。
むしろ、私の上司は「恥をかいたときに、真に学ぶ」という考え方を持っていたので、どちらかと言うと、「間違ったこと」「わからないこと」を積極的に開示していかないと、勉強会に参加した意味がない、というスタンスでした。
ただ、勉強会に出席する精神的な負荷は高かったですが。
それでも、コンサルタントたちは、この勉強会に出席するだけで、メキメキ力をつけていきました。
*
社内で勉強会をやっていて
「どうも参加者の意欲が低いなあ」
「役に立っているのかなあ」
「緊張感がないなあ」
という疑問を持つ方も多いと思います。
そんな時は、
1.社長や役員・部長など、評価者が主体となって主催する(講師をやる)
→ 緊張感が圧倒的に増します
2.仕事の実例を題材とし、当事者に中身を説明させる
→ サービス品質のチェックを兼ねます
3.中身に容赦なくツッコむ。
→ 恥をかかせることを容赦なくやると、憶えます。
4.意見を戦わせる
→ 参加者全員に意見を述べさせます
5.その結果は「標準化」し、ルールやツールに落とし込む
→ 勉強しただけで終わらせません
という条件を満たすと、圧倒的に勉強会の質が変わります。
人の成長スピードや、サービス品質も変わります。
それが「超シビアな勉強会」です。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
安達裕哉
元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)
Photo:Siavash Ghanbari