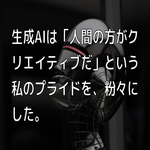かつて在籍していた会社には、優秀な人がゴロゴロいた。
会社では、顧客にアンケートを取っていたので「どのくらい優秀か」は数値ではっきりと示された。
優秀な人は、明らかに顧客の満足度が高く、プロジェクトの継続率も高い。
おまけにマネジャー以上になると、営業の数字もはっきりと出る。
特に受注率は重要で、優秀な人は明らかに提案を出してからの受注率が高かった。
そんな人に対して、私は「すごいなあ」という気持ちと、「悔しい」と言う気持ち、両方があり、どちらかというと「悔しい」が勝っていたように思う。
だから、彼らの実力をそのまま認めることができなかった。
もっと具体的に言えば「彼らは運が良い」「実力的にはそう変わらない」のだと自分を納得させ、彼らから学ぼうとしなかった。
教えを乞う事もしなかったし、「同行させてくれ」と頼みに行くこともしなかった。
それは「負けたような気になるから」だ。
*
しかし、そんな自分を見透かしている人も、たくさんいた。
当然だ。彼らは優秀なのだから、自分よりも未熟な人間はすぐにわかる。
だから先輩の一人は、私に向かって「素直じゃないねえ」と言った。
わたしはカチンときて、先輩に抗弁したが、まあ、彼らは優秀なので、そんなことも含めて、お見通しだった。
「そんなことしてると伸びないよ。これ以上。」
そうはっきりと指摘された。
わたしは悩んだ。
自分のプライドを取るか。
それとも「自分が無能である」と言う事実を受け入れて、彼らに教えを乞うか。
結局私は「無能だ」という事実を受け入れた。
それは、借金返済のためのカネが欲しかったからだ。
評価は客観的な指標をもとになされるから、私は高い評価を得ている人間に学ぶ必要があった。
だが一つ問題があった。
「高い評価を得ている」人間たちが、快く私に教えてくれるかどうかは、わからなかった。
彼らは忙しいし、私に、自分が苦労して得たノウハウをくれてやる義務はない。
そこで、苦肉の策を取った。
成果をあげている人物に対して、相手の人格に関わらず、本気で下手にでて、ひたすら教えを乞うことにした。
しかもそれは表層だけの話ではなく、「心からやる」ことが必要だった。
つまり「彼の能力は完全にわたしよりも上で、それについては私は一切の批判的意見を持たない」と、思うことだ。
バカなことだと思うだろうか?
しかし、私はこの決定を合理的だと思った。
なぜなら、「私は無能」なのだから、私には「彼らの行動の良し悪しが判定できない」からだ。
それが「教えを乞う」ことの本質だ。
教わりたいなら、教えてくれる人に対して、批判的であってはならない。そうして、彼らから一つ残らず吸収するように動く。
彼のやることなすこと、すべてに対して「オープン」になるようにする。
そうして、少しずつ「自分より優秀な人々」を模倣することが、唯一の生き残りの道だった。
*
後日分かったことだが、これは「教育」の本質を含んでいた。
本物の教育には、自分には知らないことが(たくさん)あると知ることも含まれている。持っている知識だけでなく、持っていない知識に目を向ける方法を身につけるのだ。そのためには思いあがりを捨てなければならない。知らないことは知らないと、認める必要がある。
何を知らないかを知るというのは、自分の知識の限界を知り、その先に何があるかを考えてみることにほかならない。
つまり「自分がわかっていないことすら、知らない」ことを前提にすれば、とにかく「自分は下である」と思い込む必要がある。
「リスキリング」と言う言葉がはやっている。
しかし、本当の意味で「リスキル」が難しいのは、「自分は下である」ことを、行動として体現するのが難しいからだ。
なぜなら、プライドに関わることが多いから。
だから、私は今もなお、「優秀だな」と思った方に対しては、徹底して「上下関係」を自らつくりに行くのが良いと思っている。
もちろん、自分は「下」だ。
バカにされるときもあるが、別に気にしなければいいだけの話だ。
つまらないプライドで飯は食えない。
だが、成果を上げる方法さえ身につければ、もう食うに困らない。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
安達裕哉
生成AI活用支援のワークワンダースCEO(https://workwonders.jp)|元Deloitteのコンサルタント|オウンドメディア支援のティネクト代表(http://tinect.jp)|著書「頭のいい人が話す前に考えていること」55万部(https://amzn.to/49Tivyi)|
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯note:(生成AI時代の「ライターとマーケティング」の、実践的教科書)
Photo:Sergey Zolkin