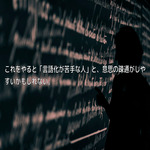「取締役に任命されたのですが、力不足を感じています。このまま職を続けるべきでしょうか」
先日ある講演会で、そんな質問をされることがあった。
質問をして下さったのは、勤務先企業で役員に抜擢されたばかりという男性だ。
与えられた役職を重く感じているものの、
「器が人を育てる」
と信じ、職責に取り組み続けているのだという。
しかし想いだけでは難しい壁を感じ、このまま続けるべきなのか。
どうすることが組織と部下のためであるのか意見を聞かせて欲しい、という趣旨のご質問だった。
「何が正解なのか、私には正直わかりません」
軽々に答えられない質問に、思わず本音が出る。
そして要旨、以下のような回答をする。
私自身、困難な仕事を乗り越えられた時に成長を感じることができたとは、思っている。
しかしあんな経験はもう二度としたいと思わないし、無茶をすべきとも思わない。
「自分にはできない」と思った時には撤退することも、一つの勇気ある決断ではないか。
それを聞いた男性は、どこか釈然としない表情のままお礼を言ってくださると、マイクを置いた。
この回答をした後から、ずっとモヤモヤしている。
自分で出した答えに、自分でもどこか納得していないからだ。
「力不足のまま、重い責任を背負い、リーダーを続けるべきなのかどうか」
そう思い悩み立ち往生している人に、私はどのように答えるべきだったのか…。
「55%正しければ大儲け」
話は変わるが、織田信長の生涯の中でもっとも有名な戦いといえばやはり、桶狭間の戦いだろうか。
わずか3,000ほどの兵で、2万とも3万とも言われる今川義元の軍勢を破り一躍、戦国時代の主役に昇り詰めていくことになった“デビュー戦”とされる。
そして私たちは昔から、こういった「劣勢からの大逆転劇」といった物語が大好きだ。
時代を遡ると、源義経が100騎にも満たない手勢で急峻な崖を駆け下り、平家の本陣を抜き大手柄をあげたとされる「鵯越えの逆落とし」。
楠木正成が、わずか500騎の手勢で20万の幕府軍を相手に戦い抜いたとされる千早赤坂城の戦いなど、“英雄物語”があふれている。
もちろんこれらは、史実というよりもフィクションに近い物語だ。
それでも多くの人が胸を躍らせ続けてきたのは、こういったピンチからの大逆転というストーリーに、感情移入してしまう何かがあるからなのだろう。
とはいえこのような話から、組織を率いるリーダーが学んで良いことなど、ほとんど無い。なぜか。
奇跡とはレアケースだから奇跡なのであって、まったく再現性がないこと。
追い詰められた結果として発動した、ヤケクソであること。
部下と組織を壊滅させる可能性が極めて高かった、失敗前提の作戦であることなどだ。
例えるなら、法人口座に残っている最後の10万円で宝くじを買い、たまたま1等が当たったような話である。
実際に、信長が天下統一に片手を掛けるまでに勢力を拡大したその強さは、決して奇襲と大逆転の戦い方などではない。
勝てる環境が整うまで決して戦わない我慢強さと、その環境を作るための政治力であった。
この組織論は古く、中国の古典「孫子の兵法」にも見られる。
・勝ち易きに勝つ
・まず勝ちて、後に戦う
といったように、小さな準備と勝利を一つずつ重ねた結果が、大きな仕事につながっていくと教える。
そしてこの考え方、近現代の優れたリーダーたちに共通する価値観でもある。
例えば、米国の第25・6代大統領で、今に至るも国民的人気の高いセオドア・ルーズベルトの言葉。
「私の判断のうち75%までが正しいとすれば、それは十分な数字である」
株式投資の世界には、こんな格言もある。
「55%以上の確率で正しい判断を下す事が出来れば、誰しもウォール街で大儲けできる」
なぜこれらの言葉が、“勝てるリーダーの価値観”に通底するのか。
私たちはなぜか、リーダーたちに無謬を求める。
リーダーとは完全無欠であり、決して間違えないこと。
いつも正しく、潔癖であること。
そんなありえない幻想を抱く。
しかし企業や組織でリーダーと呼ばれる人であればわかると思うが、どんな大組織のトップリーダーであっても、ただの人だ。
間違えるし、昼メシ抜きなら腹が減るし、感情的になることもある。
気負わないリーダーはそのことを理解し、自分のできることとできないことを見極め、時に
「助けて!」
とすら、素直に言える柔軟さを兼ね備えている。
だからこそ、「75%正しければ、俺十分すげえ」「55%正しければ大儲け」と、正しく自己認識する。
ここまで肩から力が抜けると、独りよがりで独善的な意志決定から、リーダー自身が自由になる。
「できることから小さく」成果を挙げようと、着実に詰将棋を進められる。
その一方で、「リーダーとは無謬でなければならない」と、肩に力が入っていたらどうだろうか。
部下からの進言に素直に耳を傾けられず、間違いを認めることが難しくなり、組織と部下を壮大な不幸に巻き込んでしまうだろう。
常に無謬で、どんなピンチでもひっくり返す“奇跡のリーダー”が本当に存在するなら、確かに美しい。
しかしそんな物語はフィクションであって、絶対に目指してはならない。
「当たり前の仕事を着実に進められる人こそ、優れたリーダーであること」
「凡事徹底の結果にこそ、大きな仕事の成果があること」
そんな形で、故事と現実を切り分けて考えられることこそ、優れたリーダーの第一歩なのではないだろうか。
「とても優れたリーダーだと思います」
話は冒頭の、新任役員の男性についてだ。
「力不足のまま、重い責任を背負い、リーダーを続けるべきなのかどうか」
そう思い悩み、立ち往生している彼に私は、どう答えるべきだったのか。
実はこの質問を頂いたのは、私の出版記念講演会だったので、出版にたずさわって下さった多くの“偉い人”が会場に来てくださっていた。
リーダー論の要諦を教えて下さる、陸上自衛隊の元陸将。
原稿のチェックを無償で引き受けて下さる、元大学教授。
コラムを連載して頂いている、朝日新聞の編集長。
本を出版して下さった、新潮社の役員といったそうそうたる”偉い人たち”だ。
そのため講演後、近くの居酒屋に席を移し懇親会をしたのだが、私は開口一番、皆さんにこんなことをお聞きした。
「あの質問をして下さった役員さんへのご回答、実は私、消化不良なんです。皆さんなら、どう答えたでしょうか?」
この質問について、やはり皆、とても気になっていたようだ。
そしてその場で出た意見はざっと、以下のようなものだった。
「人には向き不向きがあり、無理をすべきではないので、回答は妥当」
「難しい仕事を与えられたからといって、人は必ず成長できるわけではない。しかし難しい仕事を乗り越えないと、人は成長しない」
そんなケンケンガクガクの議論の最後に、それまで黙っていた“某エラい人”がぼそっと、こんな事を言う。
「自分は力不足ではないかと言えるだけで、あの人は立派です。それだけで、リーダーの資格があるのではないでしょうか」
その場にいた全員が一瞬、静まり返った。
そして口々に、それこそ、あの質問をして下さった方に回答すべき答えであったのではないかと、「感想戦」が締めくくられた。
もちろん私も、その意見に腹落ちし、なぜそれが言えなかったのかと悔しい思いになった。
ではなぜ、そこまでストンと腹落ちできたのだろうか。
私自身、もしかしてリーダーとは、完全無欠の無謬でなければならないと心の奥底で気負っていたのではないのか。
優れたリーダーとは、
「75%正しければ、俺十分すげえ」
「55%正しければ大儲け」
と認識し、組織のパフォーマンスを最大化することこそ仕事だと、“知識では知っていた”にもかかわらずである。
言い換えれば、私自身が歴史の“英雄譚”を真に受けていたということだ。
だからこそ、「自分は力不足なのではないのか」と悩む、あの時のリーダーにお掛けする言葉は、今は一つしか無い。
「あなたはとても、優れたリーダーになれる人だと思います。それを言えるのですから」
私のような無名の著者の出版記念講演に来てくださる方なので、きっと私のコラムをいつも読んで下さる方なのだろう。
お名前を聞きそびれてしまったが、どうかこのコラムも、目に止まることを心から願っている。
そして改めて、あの時のご質問にご回答を差し上げたいと願っている。
「あなたはとても、優れたリーダーになれる人だと思います。お会いできて本当に光栄でした」と。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【プロフィール】
桃野泰徳
大学卒業後、大和證券に勤務。
中堅メーカーなどでCFOを歴任し独立。
主な著書
『なぜこんな人が上司なのか』(新潮新書)
『自衛隊の最高幹部はどのように選ばれるのか』(週刊東洋経済)
など
小さく刻んだ奈良漬を、一度炊き込みご飯にして下さい。
本当に旨いのでオススメです!
X(旧Twitter) :@ momod1997
facebook :桃野泰徳
Photo by:Priscilla Du Preez 🇨🇦