何に対しても「偏見や差別が素晴らしい」という人はほとんどいなくて、大抵の人は偏見や差別は良くないと思っているだろう。
残念ながらネットにはひどい書き込みがあったり、ネットではなく現実の社会でも偏見や差別がないわけではないけれど、本人からしてみれば正義感に基づく言動で、偏見や差別を肯定しているわけではなかったりする。
私は自分がバイセクシュアルだからか、LGBTに対する周りの人の反応に結構敏感になってしまっていて、LGBTフレンドリーであれば嬉しくなり、LGBTに偏見があると言われると悲しくなる。
先日、友人から「LGBTに偏見ないよ」と“わざわざ”言われた、という話を聞いた。
そして「わざわざ言われるとちょっとモヤっとするんだよね~」とモヤモヤした気持ちを分かち合った。
友人とこの話をして思い出したことがある。以前、企業に対してLGBTという観点から様々なアプローチをしている方にお会いする機会があって、その方がこのように言っていたのだ。
「企業はLGBTフレンドリーであるならば、それをちゃんと外部に発信した方がいい。
『“わざわざ”言う必要はあるのか』『“わざわざ”言うのではなく、LGBTの人も当然他の人と同じように存在している、という環境こそが真のフレンドリーではないか』という人もいる。
確かにそれが理想かもしれない。でもその実態を知らない人には、その企業が実際どうなのか知るすべがない。
全ての企業がLGBTフレンドリーである社会なら発信する必要はないかもしれないけれど、まだ理解が進んでいない企業がたくさんある中では、発信しないと外部からは自分の会社も『理解が進んでいない企業かもしれない』と思われてしまう可能性がある。
だから、フレンドリーであることを掲げることは、今の日本社会では意味があることだ」
“わざわざ”言わなくてもいい社会ならば、言う必要はない。でも、言わないと外部からは実際どうなのかわからないからあえて言う、という戦略。なるほど、と思った。
友人に「LGBTに偏見ないよ」と言った人の受け止め方が少し変わる。
☆★☆★☆
似たような話をもう一つ。
大学生の頃の講義で、「友人に『実は在日朝鮮人なんだ』とカミングアウトされたら、あなたはどのような言葉をかけますか?」という問いかけがあった。
その問いかけに対し、「そうなんだ」と受け止めるだけだ、と答えた学生がいた。
その人が在日朝鮮人であってもそうでなくても、その人の見方もその人との関係性も変わらないから、とのこと。もし「だから相談にのってほしい」と言われたら相談にのるし、「悩みがある」と言われたら聞いて何か言葉をかける。
でも『在日朝鮮人なんだ』と言われただけでは、ただ受け止めるしかない。こう言っていた。
それに対し、講義されていた方は、「その人は自分がずっと背負ってきたもの、アイデンティティにも関わることをやっとの思いで、打ち明けた。それを『そうなんだ』で済まされてしまったら、悲しい気持ちになるのではないだろうか」と言った。
高校生の頃の授業で部落問題についてみんなで考えたことがあって、同様の問いかけをされたことがある。
その時に私は上述の学生と同じようなことを回答した記憶がある。だから大学の頃も学生の意見に同意し、講義されていた方の意見はしっくりきていなかった。
だが、今振り返ると、『そうなんだ』というリアクションは果たしてどうなのか、とも思えてくる。
もちろん、リアクションに正解なんてないのだけれど、“わざわざ”打ち明けた友人に対し『そうなんだ』の一言で済ませるのは、確かに軽すぎる気もする。
☆★☆★☆
一般的にセンシティブだと思われやすい話題にあえて触れてみた。実は何か主張したいことがあるわけではなく、こういう、その人の価値観が表れるような話題が現実の社会では避けられる傾向にあると常々実感していて、だからこそ触れたいと思った次第である。
強いて言えば、いろんな価値観・正義感がある、くらいのことは伝わればいいなと思っている。
そういえば、先日買った本『信じる者はダマされる うさぎとマツコの人生相談』の中で正義について次のように語られていた。
うさぎ「自分が正しい、自分が正義だと思ってるかもしれないけど、正義ってものほど他人への抑圧になるものはないよ。(省略)『正義』という衣をまとうと、『自分は正しいこと言っているんだから受け入れられるべきだ』みたいに思っちゃうわけ。
でもね、誰かの正義が必ずしも万人の正義ではないの。その食い違いで戦争が起きたりもするわけじゃない。あなたの正義は危険なのよ。正義は『凶器』なのよ」
マツコ「そう。そして『狂気』でもあるわよ。(省略)」
自分こそが正しいという思い込みの危険性について語っている。
自分とは違う価値観や正義感に触れる度に、自分の中の価値観や正義感が揺らぐ。自分とは違う価値観や正義感に触れておくことが、他人の価値観や正義感を受け入れる土台になると思う。
ではまた!
次も読んでね!
生成AIでメディア運営はここまで変わる!
記事制作・SEO・メール文面まで、コンテンツ業務の自動化が加速中。
本セミナーでは、AIを活用した「記事作成」「SEO最適化」「運営効率化」の最新事例と実践ノウハウをお届けします。
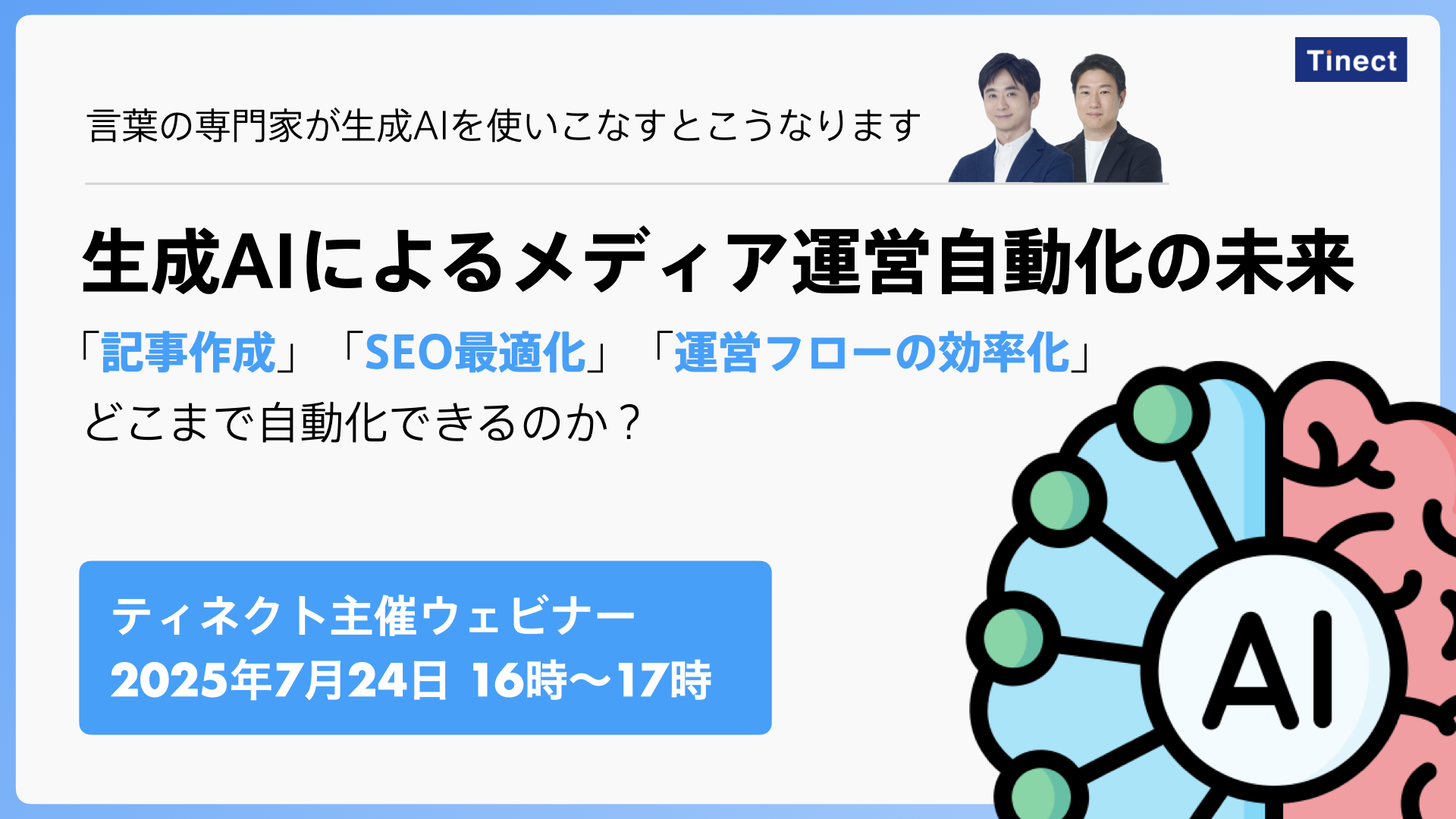
【開催概要】
・開催日:2025年7月24日(木)
・時間:16:00〜17:00(+Q&A)
・形式:Zoomウェビナー(参加無料)
【こんな方におすすめ】
・企業のPR・マーケティング・メディア担当者
・AIによるコンテンツ制作・運用に関心がある方
・SEO・ニュースレター・営業メールの効率化を進めたい方
【セミナー内容】
・AIが“記事を書く”とはどういうことか?
・SEOも、メールも、ニュースレターも。コンテンツ制作はどこまでAIで置き換えられるか?
・人がやるべきこととは何か?
・導入事例と運用のポイント
【登壇者】
・安達 裕哉(ティネクト株式会社 代表取締役)
【お申込み・詳細】
こちらウェビナーお申込みページをご覧ください
(2025/7/14更新)
[著者プロフィール]
名前: きゅうり(矢野 友理)
2015年に東京大学を卒業後、不動産系ベンチャー企業に勤める。バイセクシュアルで性別問わず人を好きになる。
著書「[STUDY HACKER]数学嫌いの東大生が実践していた「読むだけ数学勉強法」」(マイナビ、2015)
(Photo:Hamed Masoumi)














