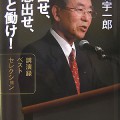会社において、意見の衝突は日常茶飯事である。あるいは、「衝突」までは発展しないまでも、意見の相違が無いことは殆ど無いだろう。
ただ、意見の衝突があった場合、「どちらが正しいことを言っているか」を判断することは難しい。もちろん、お互いに「自分のほうが正しい」と思って主張してるのだから、それぞれに一理あるのだ。
従って、理想的には「お互いに腹を割って話した上で、合意に達する」のが良いのだが、そうそう都合よく合意形成ができるとは限らない。
そんな時には、是非使って欲しい方法がある。これは、「意見の正しさ」をある程度客観的に判断できる方法なので、お互いが納得しやすい話し合いの方法だ。抽象的な話ではわかりにくいので、例を挙げよう
鈴木さんは、成績が良い部下の「五郎さん」を昇進させるべきだと考えている。
佐藤さんは、「五郎さん」の仕事ぶりは認めつつも、勤務態度が良くないことをあげ、昇進は見送るべきだと考えている。
通常、意見が出た所で複数の意見を比較検討する。比較検討の際には「費用対効果」を推定することがよく行われるが、ほとんどの施策は「やってみなければわからない」事が多い。特に人事においては、「費用対効果」を測定することは不可能に近い。「任せてみなければわからない」のである。
さて、この時点で会議は膠着している。どのようにこの状況を打開するべきだろうか?
ちょっと考えてみて欲しい・・・・・・・・。
もちろん、万能の方法はない。しかし、最も有効だと考えられるのが
「話の次数を上げる」
という行為だ。
話の次数を上げるとはどういうことか。次の2つのことを決めることである。
- この行為の目的は何か
- この行為が成功したとみなされる判断基準は何か
つまり上の事例で言えば、五郎さんを昇進させることは何が目的なのか、五郎さんをの昇進が成功であったとみなされるための基準は何かを話すことが、「話の次数を上げる」という行為だ。
鈴木さんは「昇進という行為」の目的は「業績向上」に繋がると考えている。判断基準は「目標の達成度合い」だろう。それに対して佐藤さんの昇進させる目的は「模範的人物を人の上に立たせる」という考え方であり、判断基準は「社内のモラル」である。
さらに、目的についての価値基準が異なるようであれば、更に「話の次数を上げる」事が必要だ。こうして、最終的には「会社の理念」や「会社の方針」と照らし合わせることになる。
このように、ある行為に対してその見解に相違がある時、大抵の場合は話の次数を上げる事によって出来るだけ客観的に話を進めることができる。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。