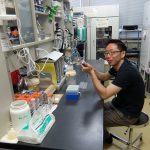努力したからと言って、成功するわけではない。
だが、努力しなければ成功できないことは、成功した人物であれば誰しも知っていることである。
だが、成功のための必要条件である「努力をする能力」は、出身階層によって不平等に分配されている。
オックスフォード大の苅谷剛彦氏は、著書「学力と階層」*1の中で、子供の「努力の量」は両親の出身階層(学歴や社会経済的地位)が高いほど、多いという研究結果を発表した。
さらに刈谷氏は出身階層による努力時間の差が、近年拡大している事を合わせて発表しており、これらのことから「親の成功」が子供に引き継がれやすい、という現状が浮かび上がってくる。
*1
人々は「不平等な競争」に生まれた時から投げ込まれているのである。
————————-
学校だけではなく企業においても、「努力をする能力の差」はかなり深刻な問題となっている。
例えば、ある中堅の専門商社では「営業能力の強化」ということで、リーダーがプロジェクトメンバーに「業界研究」の課題を与えた。
定期的に各人が特定業界の調査・研究を行い、それを皆で共有、学習し営業先の選定や提案に活かそう、という試みだった。
だが、課題を真面目にやる人物と、全くやらない人物が分かれ、しかもそれは営業成績と強い相関があった。
営業成績の良い人物は課題をこなし、更にそれを活かしてますます成績が向上する。だが逆に、勉強もせず、営業の行動も中途半端なダメな人物はますます落ちこぼれてしまい、終いには「忙しい」という理由で業界の研究会にも顔を出さなくなった。
現場には凄まじい意欲の差があった。
かつてはこのような「意欲の低い人物」においても、会社は雇用を保証し、昇給も行ってきた。社内で出世はできなくとも、それなりに居場所を用意する余裕があった。
だが現在、会社に余裕はなくなり、スキルの個人化、多様化が進んでおり、ますます意欲の差が個人の能力の差に直結するようになっている。
そして、こういった「意欲に欠ける社員」を引き上げようとする努力も、会社は行わなくなってきている。
「ヤル気のない人は、基本放置。お金が勿体無いので、そう行った人へは研修の機会も徐々に減らします」
と言う研修担当者、経営者は珍しくない。
あるweb開発企業の経営者は、このように述べた。
「意欲のない人を助けるのは面倒だし、生産性も低いのでやりたくない。大体それは本来、企業がやるべきことでもないでしょう。結果がでなくても頑張っている人は応援しますが、意欲のない人は、去ってもらうだけです。」
冒頭の研究は学校において「低い意欲の人」や「努力できない人」が増えていることを示唆している。
しかし、社会において企業も彼らの「意欲」を引き出すことができなくなった今、うまく働けない人が大量に出てきていることは、想像に難くない。
「努力できる社会人」は当たり前ではなくなった。
だが、つい先日、一人のユニークな経営者にお会いした。
「社員教育」というテーマで少し話をした後、彼は次のように言った。
「ウチみたいな中小には、最初から意欲あふれる優秀な人なんて来ないんですよ。当たり前です。だから自分たちで何とかするしかない。」
「どうやって意欲を引き出しているんでしょう?」
「彼らはね、世の中に「努力できないヤツ」と言われ続けてきたんです。そんな状態では意欲も何もない。」
「そうですね」
「でも、勘違いしないでいただきたいのは、彼らは努力できないわけじゃないんです。その証拠に、ゲームなどは真剣にやっている。」
「言われてみればそうですね」
「自分の力でコントロールできることなら、彼らは喜んで取り組むんです。意欲を引き出すのは、与える課題の難易度設定がキモなんですよ。」
「具体的にはどうするのですか?」
「それには、上司が一人ひとり、得意なことと苦手なことをよく見るしかない。ウチは「目標達成!」の前に、「その人にとって適切な目標か?」を必ず検証するようにしています。これを数サイクル繰り返すと、わかるんですね、努力が面白い、ということが。」
————————-
「フロー理論」で有名なミハイ・チクセントミハイ氏は、「挑戦と能力のバランスが取れている場所で、人は何かにのめり込み、幸福感を得ることができる」と述べた。
フローは、人間がそのときしていることに、完全に浸り、精力的に集中している感覚に特徴づけられ、完全にのめり込んでいて、その過程が活発さにおいて成功しているような活動における、精神的な状態をいう。
ZONE、ピークエクスペリエンスとも呼ばれる。心理学者のミハイ・チクセントミハイによって提唱され、その概念は、あらゆる分野に渡って広く論及されている。
チクセントミハイが見たところによれば、明確に列挙することができるフロー体験の構成要素が存在する。彼は8つ挙げている。
- 明確な目的(予想と法則が認識できる)
- 専念と集中、注意力の限定された分野への高度な集中。(活動に従事する人が、それに深く集中し探求する機会を持つ)
- 自己に対する意識の感覚の低下、活動と意識の融合。
- 時間感覚のゆがみ – 時間への我々の主体的な経験の変更
- 直接的で即座な反応(活動の過程における成功と失敗が明確で、行動が必要に応じて調節される)
- 能力の水準と難易度とのバランス(活動が易しすぎず、難しすぎない)
- 状況や活動を自分で制御している感覚。
- 活動に本質的な価値がある、だから活動が苦にならない。
(Wikipedia)
もはや「意欲」は本人だけの問題ではない。家庭や学校を当てにしていては、企業も停滞する。適切なマネジメントと、意欲に関する正確な知識を用いて、従業員の能力を引き出した企業が勝ち残るのだ。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)
・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント
・最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ
・ブログが本になりました。