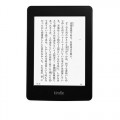電子書籍リーダの旗手であるKindleですが、今年の1月から使い始めて色々とわかってきたので、その利用に関してのデメリットとメリットを書いてみます。
電子書籍リーダの旗手であるKindleですが、今年の1月から使い始めて色々とわかってきたので、その利用に関してのデメリットとメリットを書いてみます。
まず、今までの9ヶ月で154冊、Kindleで電子書籍を購入して読みました。紙の本はその倍くらい買っているので、実感としては「まだまだ欲しい本が電子書籍になっていない」と感じます。これが一番大きなデメリットです。
特に、最近のベストセラーや漫画などは直ぐに電子書籍になって読めるのですが、少し昔の良い本などが電子書籍になっておらず、「いつも持ち歩きたい、思い出に残る」本ほど電子化が望まれるのですが、現実はそうはなっていません。
むしろ、「今、紙で売れている」本が、電子書籍にもなっている、というイメージですので、電子書籍の「在庫をもっておく必要がない」というメリットが全く生かされていないように感じます。ただ、とりあえず紙で注文する前に、欲しい本をまずはKindleで探すようにはなりました。
欲しい本があるとすぐに買ってしまうので、衝動買いが増えることは間違いないです。これが2番めのデメリット。
あと、私が買った今年の最初に出た端末は、容量が小さいので、もういっぱいになりそうです。これはデメリットと言うよりは、不満ですが。新しい端末は
”4GBに増えたストレージで最大4,000冊を保存(一般的な書籍の場合)”
とAmazonのプロモーションサイトにあるので、もっと入るのでしょう。
そして、最も気になるデメリットは、「動きがもっさりしている」という点でしょうか。ページをめくるアクションから、暫く遅れてページが変わる間隔です。ちょっとイラッとする時も多いです。
しかし、メリットのほうが圧倒的に大きいです。挙げてみます。
1.本を持ち歩ける
本を何十冊、何百冊と持ち歩けるのは調べ物や、アイデアを出すのに非常にありがたいです。ちなみに自分の紙の本をスキャナで取り込んでPDF化した、いわゆる「自炊本」も、Amazonのサイト経由でKindleに入れることが出来ます。これ、何気に良い機能です。
私は「ローマ人の物語」を全巻PDF化して、Kindleに入れています。
2.軽い
一般的なタブレットに比べて、圧倒的に軽い端末なので、持って行く時に迷う必要がありません。とりあえずカバンに放り込めます。
3.電池のもちが良い
スマートフォンでもKindleの本を見ることが出来ますが、電池のもちが圧倒的にKindleの方が良いです。ほとんど充電せずに1周間は持ちます。
4.目が疲れにくい
プロモーションサイトでも強く推していますが、確かにディスプレイが見やすいです。特に薄暗いところなどでは、明度を落とすと紙のように読めます。
5.ポピュラー・ハイライト機能が面白い
Kindleには、本の中で仮想的に蛍光ペンを引くことが出来ます。これは紙でも出来ますが、電子書籍ならではの機能として「線を引いた部分をWebで共有できる」という面白い事ができます。
「ポピュラー・ハイライト」という機能ですが、「40人がハイライト」と言った具合に、文中にいろいろな人が線を引いた部分がわかります。
6.無料本の種類が豊富
「青空文庫」という、著作権の切れた名作を無料で読むことができる形にした電子書籍のサービスが有りますが、Kindleで読むことが出来ます。「芥川龍之介」や「夏目漱石」、「太宰治」など、文豪たちの作品が無料で読めることは、紙の書籍に比べると大きな利点です。
7.場所を取らない
家にあふれていた本を、整理できます。これでやっとクローゼットが綺麗に・・・。
今年は、電子書籍元年と言われましたが、Kindleはいい端末だと思いますので、使ってみてください。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。