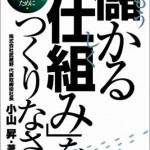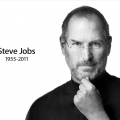昔からよくわからない言葉の一つに、「ビジネスモデル」という言葉がある。
昔からよくわからない言葉の一つに、「ビジネスモデル」という言葉がある。
何なんですかね、これ。
おそらく発端は、「ビジネスモデル特許」という言葉だろう。立教大学ビジネスデザイン研究科ジャーナルによれば、
1998年、米連邦交際がビジネスモデルに特許性を認めたと言われるState Street Bank & Trust Co.v.Signature Financial Group, Inc 裁判以後、「この判決を震源地とした激震の津波のようなもの」が起き、次第にビジネスモデル特許はブームとなった。
従来、特許は主として製造業に関係するものであったが、このビジネスモデル特許の出現により、金融業や流通業などそれまで特許とは無縁であった業界もいきなり特許の世界に叩き込まれる、という現象が起きた。
だが、「ビジネスモデル」という言葉は、「ビジネスモデル特許」で使われている意味と同一視はできない。特許庁の審査基準によれば、
2000年には、「特定技術分野の審査基準」として「コンピュータ・ソフトウエア関連発明」についての審査基準が加えられた。今日問題となっているビジネス方法特許は、ビジネス方法をコンピュータ・ソフトウエアによってシステム化した発明に関するものであるから、その審査は、通常の審査基準とこの「コンピュータ・ソフトウエア関連発明」についての基準に則って行われると考えてよい。
この基準では、取引の形態や、商取引の方法など、ビジネスの手法のみに主眼が置かれ、コンピュータ・ソフトウエアなどの技術的な部分に特徴がないものは、発明の要件を満たさないとされている。(Wikipedia)
ということで、「ビジネスモデル特許」は、商取引の方法や取引の形態などよりもむしろ、ソフトウェアの技術に主眼が置かれているといえる。
しかし、企業や銀行では、「ビジネスモデル」という言葉がソフトウェア抜きで頻繁に用いられている。企画書を出せば、やれ「ビジネスモデルがわかりにくい」だとか、「ビジネスモデルに新規性がない」など言われるが、指摘している側も本当にわかっているのだろうか。
余談だが、そういう人に、「スイマセン、ビジネスモデルの正確な定義を教えてください」というと多分怒られると思うので、聞かないほうが良いと思う。
さて、「ビジネスモデル」について調べると、先ほどの立教大学の論文によれば「儲ける仕組み」と答える人が多いということだ。確かにそのように言う人を私も見たことがある。
儲ける仕組み・・・?
一体なんだろうか。Amazonで「儲ける仕組み」と検索すると、確かに本がゴマンとでてくる。
これは私の主観だが、「ビジネスモデル」という言葉を使う人も、「儲ける仕組み」という言い方をする人も、「何か商売には正解のやり方があって、その正解に沿ったかたちで商売をすべきだ」とでも言いたいのだろうか。
もちろん、「最低限の原則」はある。約束は守る、とか、お客さんの役に立つ、などだ。だが、残念ながら商売は科学ではないので、成功するための「正解」も「法則」も無い。当たり前だ。
よくある「成功した人の体験本」を読んで、仮に100%その通りやってもも成功しないのは、「商売は、完全に再現することが出来ない」からだ。
前の仕事をやっていた頃、よく言われたのが、「事例はないのか」という言葉だった。もちろん、事例なんかいくらでもある。でも、事例を見ても成功するかどうかは全く別の問題だ。正直、「事例なんか見てるヒマがあったら、やってみればいいのに」と常に感じた。
そういった時、根底にあるのは「ムダなことはしたくない」という考え方だったように感じる。「合理性」や「科学」、あるいは「最短距離」「短期志向」が、こういった考え方を生み出していた。
別に悪いわけではない。それはその人なりの考え方なのだろう。しかし、個人的に「ムダなことはしたくない」という人と一緒に働いて楽しかったことはない。
ムダだったらムダでいいんじゃないだろうか。「しくみ」なんか考えているヒマがあったら、とりあえずやってみて、お客さんの表情や行動を見て変えればいいような気がする。
え、「私のポジションだと、失敗は許されない」ですって?
それはお気の毒に。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。