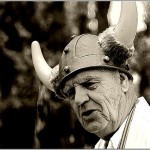以前、「趣味を答える難しさについて」という記事を書いた。
趣味を答えるという日常の一コマが何やら難しいものになってしまうというような、さらっとできる人にとっては何でもないことを難しく捉えてしまう人間がいる。今回は服を買うという別の切り口から、日常の一コマの難しさについて考えたい。
☆★☆★☆
「服を買う」というイベントを楽しめる人間がいる。ファッションが好きなのか、おしゃれに興味があるのか、ショッピング自体が好きなのかわからないが、とにかく事実としてそういう人間がいる。
一方で「服を買う」というイベントが、かけっこの苦手な小学生にとっての運動会と同じイベントになっている人間もいる。世界に何人いるのかわからないが、少なくともここに1人いる。
嫌いなわけではない。「難しい」のである。難しさゆえの苦手意識である。
何が難しいのか。
センスがない、ということではない。いや、センスがないのはその通りなのだが、センスがないから難しい、という因果関係ではない。センスなんてなくても、服はたやすく買える。
「センスがある」とは、多くの人にとってセンスが良いと思われる服の選択ができるということである。逆に言うとセンスがないというのは、多くの人にセンスが悪いと思われる服の選択をしてしまうことであるが、本人はそれが良いと思っているわけであり、つまりはセンスの良し悪しなんてものは他者が判断するもので、本人目線では「自分の選択=センスが良い」という式が成り立っているのである。
本人目線でのセンスの悪さは存在しない。センスの悪さは他者目線なので、本人にとってはあまり関係のないことだ。したがってセンスがないから服の選択が難しくなるという影響の仕方は考えられないと言うことができる。
では、センスの有無は関係ないとすると何なのか。
私は服を選ぶ難しさとは「優先順位をつける難しさ」だと思っている。
「性格の良いブスと性格の悪い美人、どっちを選ぶ?」という若干失礼な質問を耳にすることがある。これは性格と容姿のどちらを選ぶかという優先順位のつけ方が問われている。(二択なので順位といっても2位までだが……。)この究極の選択と似たような難しさに直面するのが服選びだ。
好きな服か、似合う服か。
服を選ぶとき、どちらを優先するかという問題が発生する。性格の良い美人がいれば悩むことなく選べるように、好きな服が似合うのであれば悩む必要はないが、好きな服が似合わなかったり、似合う服を好きになれなかったりするから「難しさ」が生じてしまう。
難しさと闘った結果、どうなったのか。選ぶことを辞めることになった。
私は「いつも似たようなワンピースを着ているよね」とよく言われる。
・つるつるした生地の
・台形の
・単色の
ワンピースをよく着ているらしい。まるで私の好みがそうであるかのような言い方、そのような服を私が好んで選んでいるかのような言い方をされる。
「こういうワンピースが好きなんだね」と勘違いされるので、「違います」ときちんと否定する。
「消去法なんです」
「えっ!?」
「好きなワンピースを選んでいるのではなく、選べない服を除いていくと、こういうワンピースしか残らないんです」
消去法――――――自分で自分の言葉に悲しくなる。なんて残念な選択の仕方なんだろう。なんて残念な人間なんだろう。でも、事実なのだ。
「この服は嫌い」「この服は似合わない」「この服は体のラインが出るからダメ」と、着ることができない服を選択肢から外していった結果、残ったのが単色・台形・つるつるワンピース、というわけだ。
消去法という響きの虚しさを実感し、自分の意志で「コレ!!」というものを選んでいきたいと思う今日この頃。だって、消去法で選ぶ人生なんてつまらないもん。「こんな人生でいいのか」と自分に問いかけると「ダメでしょ」と返ってくる。
思えば就職活動も、最初は消去法だった。
やりたいことは特にない。働く姿もイメージできない。そんな人間がどうやって企業を選ぶかというと、なんとなくダメだと思う企業(=ベンチャー企業や中小企業)を選択肢から外していき、残った、なんとなく問題なさそうな大手企業に応募する。
そこで実現したいことが特にあるわけではないけれど、他に選択肢がない(と思っている)から大手企業をいくつか受けてみる。
消去法で選んだ企業に選ばれるわけがなく、落ちる。今思えば落ちて当然だが、当時は釈然としなかった。
服選びと就職活動という全然違う2つのことが、消去法というキーワードでつながった。就職活動を失敗というつもりはないけれど、大手企業をなんとなく受けていた頃は消去法で選んでいたな~と反省する。
就職活動は今後転職するにしても何百回もするようなものではない。でも服を選ぶというイベントは、今後何度も発生するイベントだ。「消去法で選ぶのは、もうやめようよ」と自分に言い聞かせる。服だけじゃなくて、何をするにも「選択」の毎日だしね……。
☆★☆★☆
新年1回目の記事ということで、「消去法」ではなく「自分の意志で積極的に選ぶ」ことを決意して終わりたいと思います。「お前の決意なんてどうでもいいよ」と思った人も、これは他山の石、もしかしたら消去法で選んでいることがあるのではないか、「なんとなく無難な方を選べばいいか」と思っていないか、振り返ってみてはいかがでしょうか。
ではまた!
次も読んでね!
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
[著者プロフィール]
名前: きゅうり(矢野 友理)
2015年に東京大学を卒業後、不動産系ベンチャー企業に勤める。バイセクシュアルで性別問わず人を好きになる。
著書「[STUDY HACKER]数学嫌いの東大生が実践していた「読むだけ数学勉強法」」(マイナビ、2015)