最近、以下のようなフレーズを、本当によく見かけるようになった。
「好きなことを仕事に」
「やりたいことを見つなさい」
「好きなことだけをやれ」
ネット上のみならず、旧来のメディア上にも、そのような言説が踊る。
「前から、そう言う人っていなかった?」という方もいるかもしれない。
それは、そのとおりだ。
人類は常に「昔より、より大きな自由」を獲得してきた。
スティーブ・ジョブズは2006年のスタンフォード大学のスピーチで、こう言った。
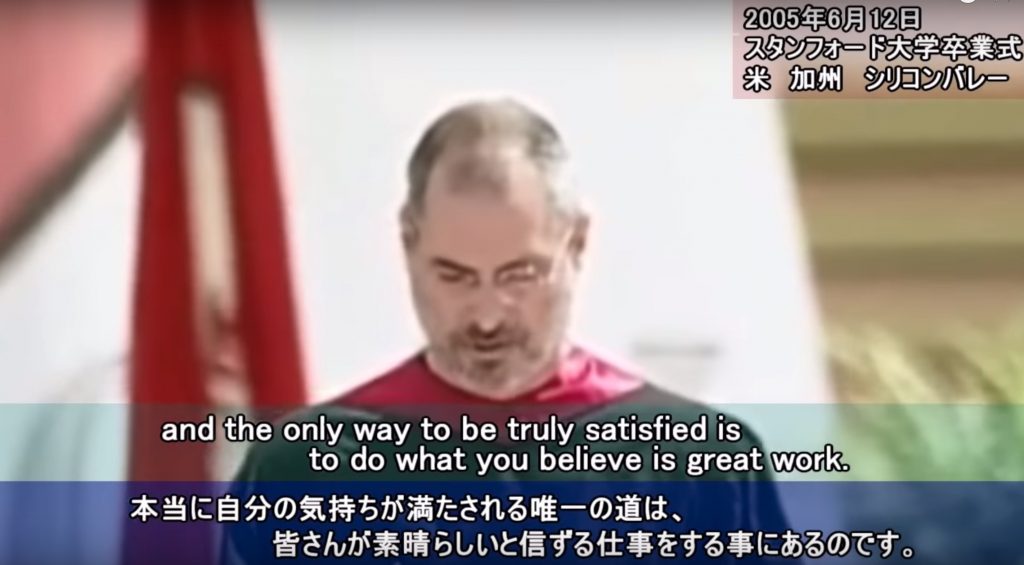
(出典:https://www.youtube.com/watch?v=VyzqHFdzBKg)
アメブロで20万人のフォロワーを抱える、心理カウンセラーの心屋仁之助さんは、「好きなことだけして生きていく」という本を2014年に出している。
Googleが、ヒカキンを使ってYoutubeで「好きなことで、生きていく」というプロモーションを打ったのも2014年だ。
この頃までは、「好きなことをしていい」は、「従来の枠組みからの開放」を表していた。
「従来の枠組みを外れてもいい」
「好きなことをして生きていい」
「疲れましたね、もう周りに合わせて頑張らなくても大丈夫ですよ、好きなことに忠実でいいんです」
そういった「癒し手」の言葉が、「好きなことをしよう」だった。
「ありのーままでー」という「アナと雪の女王」がヒットしたのも、2013年。
あなたは、あなたの好きなようにしていい、ありのままでいい、そういう「勇気」を与えることが、「好きを仕事に」といった言説のバックボーンだった。
こういった言葉に、救われたと感じた人は多かったのではないだろうか。
少なくとも、私はその一人だった。
*
ところが最近は様子が異なる。
堀江貴文さんは、「好きなことだけで生きていく」という全く同じようなタイトルの本を2017年に出しているが、内容は上の本と大きく異なる。
何が異なるのか。
それは「好きなことを仕事にしないと、豊かになれない」という警告が発せられていることだ。
本書は、いわば僕からの「最後通告」だと思ってもらいたい。既存のレールに乗って生きていくことは、これからの時代、通用しなくなる。
僕が言う1%の人にならなければ、本当の意味で仕事に没頭することはできなくなる。
「いやいや、ホリエモンが煽っているだけでは?」と思う方もいるかも知れない。
だが、そうではない。
この傾向が顕著に現れたのは、2016年にロンドン・ビジネススクール教授、リンダ・グラットンが「ライフ・シフト」を発表してからだ。
ライフ・シフトではまさに、「好きを仕事に」の具体的な中身が述べられている。
長寿という贈り物を手にする世代は、もっと選択肢が多く、もっと多様な人生を送ることができ、もっと多くの選択をする必要がある。
そのため、正しい道を選び取るために時間を費やすことの重要性が高まる。
未来を見据えて、自分の監視と情熱に沿った教育を受けること。
自分の価値観に適合し、やりがいを感じられ、自分のスキルと関心を反映していて、しかも袋小路にはまり込まないような仕事を見つけること。
自分の価値観を尊重してくれ、スキルと知識を伸ばせる環境がある就職先を探すこと。
長く一緒に過ごせて相性のいいパートナーを見つけること。
一緒に仕事ができて、自分のスキル及び働き方との相性がよく、できれば自分を補完してくれるビジネスパートナーと出会うこと。
具体的にはこうした事が必要になる。
繰り返すが、重要なのは「好きなことを仕事に」が「必要になった」と述べられている点だ。
最近では、「好きなことをする」「いや、仕事はそういうものではない」は議論の対象ですらない。
高度に専門化された社会では、好きなことをして、特定の分野を極めないと、豊かになれないのである。
「欧米で老後2000万不足が起こらない理由
なぜ日本人は「老後」を恐れるのか」がプレジデントオンラインにアップされました。 https://t.co/Hwu2HQTer9 「人生100年時代」の人生設計は「長く働く」以外になく、それには「好き(専門)を仕事にする」以外ないという話をしています。— 橘 玲 (@ak_tch) July 18, 2019
好きなことを仕事にして、目いっぱい楽しんで仕事をすると、本当にいい仕事ができる。
そして、それが売れるようになるのです。だって、お客さまはバカではありません。
嫌々やっているか、楽しんでやっているかは、必ず伝わるのです。#真理 #エクスマ #藤村正宏— 藤村正宏 (@exmascott) July 16, 2019
何度だって言いますよ。これからは好きなことを仕事にして、圧倒的なパフォーマンスを出せる人が勝てる時代。これは真実です。
これからどんどん加熱していきますよ。中途半端な人が勝てる世界はもう終わってます。— イケハヤ教授@仮想通貨 (@IHayato) July 18, 2019
“リポビタンD TREND NET” #スズコメ ③ #ワンモ
【声優・杉田智和さん、SNSで嫌味への対処法を明かす】色んな苦労もあると思うんですけど、変わらず常に思っていることをフィードバックしているので、本当に心強い仲間ですね。僕も、これからも好きなことを仕事にしたことを全うして頑張ります。
— TOKYOFM/JFN『ONE MORNING』 (@ONEMORNING_1) July 17, 2019
大好きなゲームの荒野行動。
好きなことが仕事になっていく🔥
こんな嬉しいことはないね。その中で一番好きなクラン”αD”
とこれからいろんなことをやっていける予感❗️— ✌️PEACE✌【αD】️👻ラップオバケ👻 (@peace_rock_on) July 12, 2019
好きなことをして楽しむ
これが趣味の基本
より深く探求することで
より深く楽しむことができる
好きなことを突き詰めた結果
それが人の役に立つようになれば
趣味が仕事になる
仕事の根本は
人の役に立つこと
これを忘れずにいたい pic.twitter.com/1zA7kQ22IY
— 鈴木サキソフォンスクール(サックス教室) (@SuzukiSax) July 9, 2019
私は今よりも沢山
ありえないくらい沢山
自分の好きなことを仕事に繋げられるように頑張るのさ☺️🧡— 井尻 晏菜はジュナオお迎えしました (@ijirianna0120) July 6, 2019
実務家、起業家、フリーランサー、投資家、芸術家、作家……あらゆる分野の人々が「好きを仕事に」という。
いや、内田樹のような「グローバル資本主義嫌い」の、保守的な思想家ですら、「好きなことをせよ」という。
内田樹が語る雇用問題――やりたいことをやりなさい 仕事なんて無数にある
人はやりたいことをやっている時に最もパフォーマンスが高くなります。難局に遭遇して、そこで適切な選択をするためには、他者の過去の成功事例を模倣することではなく、自分自身の臨機応変の判断力を高めた方がいい。
そして、自分の判断力が高まるのは、「好きなことをしている時」なんです。「自分はほんとうは何をしたいのか?」をいつも考えている人は「これはやりたくない」ということに対する感度が上がります。
そして、生物が「これはやりたくない」と直感することというのは、たいてい「その個体の生命力を減殺させるもの」なのです。自分の生きる力を高めるものだけを選択し、自分の生きる力を損なうものを回避する、そういうプリミティヴな能力を高めることがこの前代未聞の局面を生き延びるために一番たいせつなことだと僕は思います。
自分がしたいことがあったら、それをする。自分が身につけたい知識や技術があったら、それを身につける。自分が習熟したい職能があったら、それを学べばいい。
つまらない算盤をはじいてはいけません。「一時我慢して、それさえなんとか身につけておけば、あとは一生左うちわ」などというものにふらふらと迷い込んではいけません。弁護士や医師でさえ雇用の危機だという時代になるんですから。
これは明らかにこれまでとは異なる傾向で、私は密かに驚いていた。
*
もちろん、光があれば影がある。
「好きを仕事にしないと豊かになれない」世界は、「主体的に動く人だけが豊かになれる」という、残酷な世界だ。
自分で選びとらない限り、何も手に入らない世界。
「考えたくねえ」
「受け身でいいだろ」
「決められねえ」
「正解を教えろ」
「リスクを取りたくねえ」
が、貧しさの象徴になった世界。
これは、一片たりとも、人に優しくない。
「自由に生きられる」は、いつの間にか「自由に生きねばならない」に変わっていた。
もちろん「そんな世の中は間違っている」という方もいるかも知れない。
「言われたことだけやっていれば、それなりに豊かになれる世界が望ましい」という方もいるだろう。
そう言う人はちゃんと選挙に行って、政治を変えよう。
ただ、現在の世の中の趨勢はテクノロジーを中心とした「専門家」が必要とされる世の中であり、急には変わらないだろう。
経済的に豊かである、ということは、そういうことになってしまったのだ。
だから現代人にとって最も重要な教養は「自由の使い方」だ。
すなわち
自らの人生をどうマネジメントするか。
意思決定をどのように行うか。
どう試すか。
何を学習するか。
そういった「自由」の使い方こそが、長い人生を豊かに過ごすための鍵になる。
もちろん「自由」は軋轢を生む。
とくに「自由」を使いこなせる人々と、使いこなせない人々の断絶は、絶望的なほど広がる可能性がある。
何しろ、「自由」とは「他者から嫌われることだ」と、哲学者のアルフレッド・アドラーが言ったぐらいだ。
哲人:すなわち、「自由とは、他者から嫌われることである」と。
青年:な、なんですって?!
哲人:あなたが誰かに嫌われているということ。それはあなたが自由を行使し、自由に生きている証であり、自らの方針に従って生きていることの印なのです。
あるひとが「自由」を謳歌すればするほど、「嫌う」人が増える。
それは人間の宿命のようなものである。
*
余談だが「安達はどう思っているのよ」という方もいるだろう。
それに回答しておきたい。
個人的には、「好きを仕事に」というのは、若干ショートカットされた言い方だと感じている。
単に「好きなこと」をしているだけでは、仕事にならないからだ。
仕事はマーケットが必要で、マーケットを見る目のない人は、「好きを仕事に」は実現できない。
したがって、自由を謳歌するための条件は、マーケティング能力、すなわち
・市場に自らの能力やプロダクトを晒す
・市場とマッチしていない場合は、学習・修正を行う
の2点を獲得する必要がある。
その上で「自由の使い方」を教養として身につければ、まあ、一生困らないのではないだろうか、と思う。
ただ、このような生き方に適合できない方もたくさんいるだろう。
結果として、「自由を謳歌できた人々」は、そのような方に手を差し伸べる義務を負うと私は考える。
◯Twitterアカウント▶安達裕哉(人の能力について興味があります。企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働者と格差について発信。)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
◯Twitterアカウント▶安達裕哉
◯安達裕哉Facebookアカウント (安達の記事をフォローできます)
◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をフォローしたい方に)
◯ブログが本になりました。
(Photo by Grant Ritchie on Unsplash)












