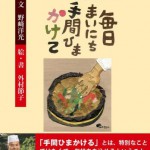日本人はサービスやソフト、アドバイスなど、無形のものにカネを払わないという話をかつてはよく聞いた。
私はコンサルティング業界にいたので、そのような話をする人々が何人もいた。そして、その話を聞いた時には「そんなものか」と思っていた。
例えば、紙の書籍と電子書籍があって、同じ価格で売られていたらどう思うか?調査によれば、「それはおかしい」と思う人のほうがはるかに多いそうだ。
電子書籍の価格「紙の半額以下が妥当」71%―電子書籍の利用調査
中身が同じなのに、電子書籍の方が安く売られて当然と皆思っている。
得られるサービスがほとんど同じなのに、払っても良いと思う金額が違う
と言うのは、なんとも面白い話だ。
なぜこのようなことが起きるのか?電子書籍が安くて当然、と思う人が多い理由の多くは、「材料費や手間がかかっていないのだから、安くて当然」という感覚だ。
「手間をかけた料理」や、「手間をかけた工芸品」であれば、高いお金を出して買っても良いと思う。逆に、「簡単に作られたもの」「大量生産されたもの」には、良いものであってもお金を出さない。
カレーや、ハンバーグ、シチューなどの加工食品のキャッチフレーズに、「手間ひまかけた」というフレーズが多いのも、頷ける。味が変わらなければ、人は「手間ひまかけた」モノのほうを好む。
実は、この「モノの「価値」は、必ずしもその有用性だけでは決まらない。」は、初期の経済学の難問だったという。
水は有用だが通常は安価であり、宝石はさほど有用とはいえないが、非常に高価である。これは「価値のパラドックス」と呼ばれ、これを説明することは、初期の経済学の難問であった。(wikipedia)
経済学は、当初この問題を「希少性」という概念を持ち込んで説明した。
近代経済学(限界効用学派)では、全部効用と限界効用の区別により二者を消費面から統一的に説明することでこの問題を解決した。
マルクス経済学では、商品としての水(たとえばボトルウォーター)および宝石に費やされた労働量を比較して、「ペットボトルの水の原料は、どこでも手に入るし製品化するのにさして労働力も必要としないため、価格は低い。」「宝石は原料が希少で、原料の探査・採掘に膨大な労働力がかかり、しかも研磨して加工し、商品にするためにも密度の高い労働力を必要とするから価格が高い。」
と投下された抽象的人間労働の大小で価値の大小を説明し、生産面からこの問題を解決した。
しかし、如何に「希少」であっても、「欲しい」と思う人が少なければそのものに価値はない。たとえばある人が「空き缶のコレクション」をしていたとする。世界中のありとあらゆる空き缶を集めてくれば、「希少性」は生まれる。
が、その空き缶がいくらで売れるか?というと、これは「ほしい人がたくさんいれば高くなる」「欲しい人がいなければゴミ」ということだ。
「希少性」だけでは説明の付かないこの話、決着を付けたのは、現代ではよく知られる「需要と供給」という話である。すなわち、需要>供給 では価格は上がり、需要<供給 では価格が下がるというごく当たり前の話だ。
お客さんが「お金を出さない」と言うのは、単に「似たようなものがたくさんある」だとか、「そんなことできる人たくさんいるよ」と思っているからだ。
電子書籍の価格が低く見られるのは、「供給」が紙の本に比べて極めて簡単に思えるからだ。
お店がブランド米や、ブランド肉などの「原材料の希少性」を訴えるのは、「供給が限られているので価値がある」ということを知ってほしいからだ。
どうやら、人は手間に価値を感じる、は本当のようだ。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。