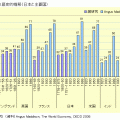山口栄一氏とお会いする機会を頂いたので、その時に頂いた著書を読んだ。
山口栄一氏とお会いする機会を頂いたので、その時に頂いた著書を読んだ。
この著書のキャッチフレーズは、「クリステンセンの気付かなかったイノベーション」ということだったので、クリステンセンの著作である「イノベーションのジレンマ」、「イノベーションへの解」、「教育×破壊的イノベーション」の3冊を読んでいた私は、非常に楽しく読ませていただいた。
クリステンセンは、イノベーションを2種類に分けている。「持続的イノベーション」と「破壊的イノベーション」である。
持続的イノベーションは、要は「今までの製品を、より高スペックにすることで得られるイノベーション」であり、「破壊的イノベーション」は、「より低スペックにすることで得られるイノベーション」である。
一般的に大企業はすべての商品を「より高スペックにすることで利益を高めよう」とする。しかし、ベンチャーや中小企業はその方法では大企業に勝つことはできないため、「より低スペック」にすることで、今までそれを使ってこなかった顧客を取り込み、イノベーションを起こす、という主張だ。
山口栄一氏はこの主張を認めつつも、「イノベーション」にはさらにもう1種類あると主張している。それは、「パラダイム破壊型イノベーション」と呼ばれるものだ。
いわゆる「科学技術」が「それまで誰もやれると思っていなかったことを実現する」ことで得られるイノベーションのことを彼はこのように名づけている。彼はトランジスタや、青色発光ダイオードによるイノベーションは、この「パラダイム破壊型イノベーション」であると主張している。
事例が非常に綿密に研究されており、イノベーションの過程を知ることが出来る本としては秀逸である。
しかし、個人的には、イノベーションに関してはクリステンセンも、山口栄一氏もピーター・ドラッカーの主張した「7つのイノベーションの機会」の範疇を出ていないと取れる。
ドラッカーはイノベーションの機会を以下の7つに分類した。
1.予期せぬ事の生起
2.ギャップの存在
3.ニーズの存在
4.産業構造の変化
5.人口構造の変化
6.認識の変化
7.新しい知識の出現
クリステンセンや山口栄一氏の主張はいずれも統計的な調査に基づいており、科学的に信頼の置けるデータであるが、ドラッカーの分類したニーズの存在や、新しい知識の出現を言い換えているにすぎない。
私の認識が間違っていなければ、「イノベーション」を起こそうとする人々は、「現在自分たちが持っているものでどのようにイノベーションを行うか」に最も興味があり、その部分に焦点があたっていると更に良かったと感じる。これは、クリステンセンの「イノベーションへの解」という著作において考察がされており、山口栄一氏の著作とあわせて読むと、更に理解が深まるだろう。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。