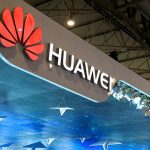メディアが報じる「世界」は、暗いものが多い。だが、現実はそうではない。
世界はますます豊かになっており、人類は繁栄を謳歌している。
特に「極度の貧困」は、解決しつつある。その撲滅は、遠い将来の話ではないかもしれない。
米コラムニストのモイセス・ナイムは著作の中で次のような事実を紹介している。
二一世紀の最初の一〇年は、人類がもっとも成功を収めた期間だったとは言えないだろうか?アナリストのチャールズ・ケニーが述べたように、人類の「これまでで最高の一〇年間」であったのだと。
この主張は、データによって裏づけられている。世界銀行によれば、二〇〇五年から二〇〇八年にかけて、サハラ以南のアフリカからラテンアメリカにかけて、そしてアジアから東ヨーロッパにかけて、極度の貧困の中で暮らす人々(一日一・二五ドル未満で生活する人々)の割合が急速に下がったという。
これは、世界の貧困に関する統計が利用できるようになって以来、初めてのことだ。先に述べた一〇年の間に、一九二九年の世界大恐慌以来最大の経済危機が到来したことを考えれば、この数字の急落はさらに驚くべきものとなる。
例えば中国においては、1981年以降、6億6千万人が、貧困から抜け出している。
これは実に喜ばしいことだ。
さらに、アジアでは「極度の貧困」に暮らす人の割合が1980年には77%であったが、1998年にはたったの14%に減っている。そしてこれはアフリカに於いても同様の傾向が見られるという。
経済学者のマクシム・ピンコフスキーとザヴィエル・サラ・イ・マーティンによれば、一九七〇年から二〇〇六年にかけて、アフリカの貧困は一般に認識されている以上のスピードで減少しているという。
ふたりが厳密な統計的分析に基づいて導き出した結論は、次のようなものだった。(中略)
鉱物資源の豊かな国でも、乏しい国でも、農業に適した国でも、そうでない国でも、植民地であった国かどうかにかかわらず。そして、アフリカで奴隷貿易がおこなわれていた間、奴隷獲得率が高かった国でも、低かった国でも同じだった。
一九九八年、データが利用できるようになってから初めて、貧困ラインより上で暮らすアフリカ人の数が、下で暮らすアフリカ人の数を上回ったのである
つまり、世界的に見れば「分厚い中間層」ができつつあり、「世界の人々の平等」は進行している。
「世界中で格差が広がっている」ような書き方をしているメディアも多いが、実際には豊かに暮らすことができる人々が世界中で増えている。
多くの貧困諸国の急激な経済成長と、その結果生じる貧困の減少は、「グローバル中間層」の増加も後押ししている。世界銀行によれば、二〇〇六年以降、二八カ国のかつての「低所得国」が、いわゆる「中所得国」の仲間入りを果たしたという。
こうした新しい中間層は、先進国の中間層ほど繁栄していないかもしれないが、かつてなく高い生活水準を享受している。現在、世界でもっとも急速に成長している人口動態カテゴリーは、この新しい中間層だ。
途上国の貧困層は「グローバル化」により、世界経済に参加することで中間層に上がることができ、大きく生活水準を向上させることができた。
こういった、喜ばしい状況が出現する一方で、唯一、「負け組」となっているのが、先進国の中間層である。
彼らは自分たちの地位を低下させた、グローバル化を憎んでいる。
「反グローバリズム」を標榜するトランプ大統領の支持者。
「ブレグジット」に票を投じた移民に反対する人々。
実は彼らこそ、真の「負け組」である。
さて、ここで我々は立ち止まって考えなければならない。
「世界中の人々が同胞であるのだから、世界がどんどん豊かになっているのはとてもいいことだ」
と考える人と、
「先進国の中間層が貧しくなったのは、グローバル化のせいだ。この状況には我慢ができない」
と考える人の断絶について。
日本においても、一般的な傾向としてグローバル企業に勤める人や、起業家、富裕層、知識人たちは「グローバリゼーション」を歓迎しているようにみえる。
大企業の売上構成を見てみれば、極めてこれは当たり前だ。例えば、トヨタの売上構成比は、もはや8割が海外である。(参考:トヨタIR情報)
任天堂の売上構成比をみても、すでに海外の割合が75%以上(参考:任天堂IR情報)である。「日本の会社」臭が強い日本電産ですら、すでに海外売上比率8割近い。(参考:日本電産IR情報)
彼らにとって「日本人」は優先して救う対象なのだろうか?
彼らは「日本人の既得権」を守るべきと考えているのだろうか?
残念ながら、そうはならないかもしれない。
もちろん「配慮」はするだろうが、それは「客」である限りにおいて、である。
グローバル企業は、生存するために株主の論理と、市場の論理に従うだけであり、「日本人である」というだけで救済したりはしない。
もちろん、その従業員たち、株主たちも同様に考えるだろう。
*****
これは何も「資本主義だから」という話ではない
「親近感」の問題でもある。
つまり、日本人同士の連帯も、薄くなりつつあるのだ。
例えば、東京の大企業に勤めている人が、田舎の見知らぬヤンキーと、会社で隣の席にいる中国人、どちらに親近感を覚えるだろう。
アメリカに留学していた研究者が、日本の限界集落の高齢者と、同じ研究室にいるインド人、どちらに親近感を覚えるだろう。
悲しいことかも知れないが、もはや、同じ国に住んでいる、というだけで「同胞」と呼ぶことはできないと、グローバリゼーションを支持する人々は考えている。
そして、負け組はそれを知っているからこそ、トランプ大統領は「負け組」に支持され、大統領となることができた。
幾つかの政治的混乱を経て、この状況が収束するのか。
それとも負け組の怨嗟が革命を起こすのか。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者プロフィール】
・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)
・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント
・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ
・ブログが本になりました。
・「「仕事ができるやつ」になる最短の道」のオーディオブックもできました。
(Photo:Chanze photo a r t)