コミュニケーションについて書かれた記事に、2つ、個人的に面白かったものがある。
いずれも大変にバズった記事なので、覚えている方も多いだろう。
一つ目は、電通の人たちのカラオケが、恐ろしく洗練されており、「ただ行為のみ」に目的が置かれたコミュニケーションの極地を見た話。
電通の女性の1人は、AKB48の『大声ダイヤモンド』の「大好きだ! 君が 大好きだ!」の「君が」を「仕事」におきかえた替え歌を披露していた。照れの一切ない、一体こうなるまでに何度こなしてきたんだという洗練されたものだった。
普通なら振り付けをこなすだけでじゅうぶん盛り上げ役の責務を果たしたと考えてしまうところなのに。ハードワークなサラリーマンに広く刺さるよう、絶妙なモジリをほどこすなんて。
すげえという眼差しで傍観していたが、ほかの電通の人たちは彼女の完璧な振り付けや替え歌には反応を示さず、当たり前のことのように、オーソドックスに盛り上がるばかり。替え歌の女性も、自分の気の利かせっぷりに誰も言及してないことなどお構いなく、曲中のすべての「君が」を「仕事」におきかえて歌いおおせていた。
すごい。ウケるとかスベるとかそういうものを超越した、ただ行為のみの世界だ。
電通というエンタメの長みたいなところにいる人たちが、ただただ空気の流れに身をゆだねる形のコミュニケーションをとっているのには、単なる体育会系のノリという以上に意識的なものがあると思う。
(雑記)
そしてもう1つは、「内容のないコミュニケーションの重要性」について語られた記事だ。
内容の無いコミュニケーションを馬鹿にしている人は、何もわかっていない
人間同士のコミュニケーションのなかで、「コミュニケーションの内容」が本当に問われる場面はそんなに多くない。
もちろん、業務上の指示やディベートの際には、内容こそが重要になる。しかし、日常会話の大半は、コミュニケーションの内容よりも、コミュニケーションをしていることのほうが重要だ。(中略)日和や季節についての会話や、女子高生同士のサイダーのような会話も、しばしば「内容のない会話」の例として槍玉に挙げられる。しかし、交わされる言葉の内容そのものにはあまり意味が無くても、言葉を交換しあい、話題をシェアっているということ自体に、大きな意味がある。
(シロクマの屑籠)
内容のないコミュニケーションを極めた人たちの話と、内容のないコミュニケーションであっても、大事にしたほうが良い、という話。
この2つの話は、研修やビジネス書などに書かれている「テクニカルなコミュニケーション」とは異なる。
「空気読めよ」「仲間だったらノリを合わせろよ」「言わなくてもわかるだろ」という、感覚を優先したハイコンテクストなコミュニケーションだ。
しかし、こういった「ハイコンテクストなコミュニケーション」が優先されることに対して、それを嫌悪する人もまた、多い。
極めつけは、たとえばビジネスとかで、「みんなで協力して新しいマーケットなりサービスなりを創造しよう」と言って集まるときに、マーケット自体、サービス自体を創造することよりも、創造されたマーケットにおいて、自社がおいしいポジションを獲得することばかりに力を入れる人たちの醜悪さ。
やたらと根回しして、飲みニケーションして、こそこそ耳打ちして、目配せして、言外に微妙なニュアンスをにおわせて。。。。そんなことばかり。自分の分け前を少しでも大きくすることばかりにエネルギーを費やすものだから、肝心のパイがちっとも焼き上がらない。
(分裂勘違い君劇場)
これらの言説を対比してみたとき、ようやく気づくことができた。
つまり、これらのスレ違いが、コミュニケーションに起因するトラブルの大体の原因であると。
例えば、
要件を伝える際の「電話派」と「メール派」との対立。
電話は雰囲気を共有できるので、要件が曖昧な状態でも、なんとか相手に意図を伝える事ができる(ような気がする)が、メールは要件をはっきりさせてからでないと、書くことができない。
また、
「結論から言う」という状況と、「単刀直入に言ってはいけない」という状況の使い分け。
人事評価などでは、結論だけ伝えても納得感が生まれないが、質問は結論から言うべきである。
さらに、
「会社の飲み会は大事」という人々と、「飲み会は嫌い」という人々との対立。
空気を共有することの重要性については、相当の認識の差がある。
以上のように、世の中のコミュニケーションに関するトラブルの多くは
「空気を読め」の度合いに関する、ズレが原因だ。
以前、こんな記事を書いた。
「察し」の文化が、徐々に後退してきている、という話だ。
コミュニケーションの要諦は察してくれに甘えないことなんだけど。
「コミュニケーションが不調で、お互いに不信感を持ったり、いがみ合ったりしているプロジェクトやスタートアップって、大抵「察してくれ」が多すぎるんだよ。」
「具体的には?」
「例えば、トップに対して「困ってたら助けてくれるだろ」と思って助けを自分から求めないケース。結果的に締め切り寸前に「すみません、納期を遅らせてもらえませんか」といって揉める。」
「ああ、そういうこと」
「「こっちは困ってんだから上司が察してくれよ」に甘えてる、というわけだ。」
「なるほど」
「ちなみに、このケースの場合はもちろん上司にも非がある」
「なぜ?」
「上司の側も同じく「困ったら相談しろって、言わなくてもわかるよな。察してくれよ」って思っているからさ。」
「ありがちだな。」
「でも、「常識だったらわかるだろ」は、これからどんどん通用しなくなる。なにせ、正社員は減る一方だし、必然的に社外の人や契約社員、場合によってクラウドソーシングを使ったりするからな。「察し」なんてものは過去のもの。」
現在、恐ろしいスピードで社会の多様性が高まるにつれ、「コミュニケーション」のルールは変化している。
控えめであることが美徳だったのに対し、自己アピールが重視されるようになった。
正社員同士であれば「あれ、うまくやっといて」で済んだものが、外注への依頼は「何を、どのように、どの程度」を明確にする必要がある。
職場に皆が集まって仕事しているときは仲間意識を持てたのに、リモートワークに移行して連帯感がなくなった。
冷泉彰彦氏は、ニューズウィークのコラムで、コミュニケーションのルール変化について、以下のように述べている。
問題は「コミュニケーション能力」というものへの誤解です。まず確認しておきたいのは、学校の世界などに見られる「仲間うちの空気を読んで同調し差異を押し殺す」ようなコミュニケーションというのは「高度」ではないということです。
会話の前提条件となる情報が共有化されていることで、省略表現や暗号などが頻繁に使われているスタイルであるだけであって、内容のほとんどは予定調和ですし、利害関係を受け止めて調整するスキルもなければ、転校生や外国人などの「異なった存在」の受け入れ能力にも欠けるわけで、コミュニケーションとしては非常に幼稚です。
物事を語るには事実を確認しなくてはいけないとか、因果関係を考えるとその結論は違うのではないか、といった思考法を持つ人には、確かに合わせるのにはバカバカしくて苦労するかもしれません。その苦労もあるレベルを越えているのであれば、笑い事ではないのは分かりますが、そもそも「場の空気」の「同調圧力」にタダ乗りしただけの会話のほうが高度だというのは間違っていると思います。
次に、企業社会の組織内コミュニケーションであるとか、接客や営業のトークなども「同じように同調圧力に屈する会話」であり、とても辛いものだというイメージがあるようですが、これも違うと思います。土下座して謝れば済んだり、人格を否定するようなパワハラに耐えるというのは過去のものになり、現代の社会は、そんなことをやっていては「成り立たない」世界になっているのです。
例えば、接客や営業では理不尽な「モンスター」的な客に対してひたすら耐えるようなコミュニケーションが求められるように錯覚しがちですが、現実の商取引というのは膨大で詳細な事実認識と法的な契約の枠組みの中で進むことがほとんどです。
職場で年配の方々の「空気を読め」に対応しつつ、増えた外注や派遣社員・外国人や若い優秀な人材が求めてくる「コミュニケーションの目的をはっきりさせてください」に応えるのは非常に大変なことだ。
だが、大変だからと言ってそれを怠れば、コミュニケーション自体が成立しなくなる。
ピーター・ドラッカーは、コミュニケーションを成立させるものは、受け手であり、コミュニケーションは受け手の言葉を使わなければ成立しない。受け手の経験に基づいた言葉を使わなければならない、と述べている。*1
したがって、受け手が多様化すればするほど、コミュニケーションも多様化せざるを得ない。
そういう意味で、「グローバル化」はコミュニケーションの多様化と直結する。それが、現代の人が悩む「コミュニケーションのトラブル」の本質的な原因である。
*****
「コミュニケーション能力」に悩む人が多い現状を踏まえ、webメディア上で数多くのコミュニケーションに関する記事を書いてきました。
それらの「コミュニケーション」について書かれた記事だけを編集し、加筆修正した書籍が8月24日に発売されます。
Amazonで予約を受け付けていますので、ご購入いただければ嬉しいです。
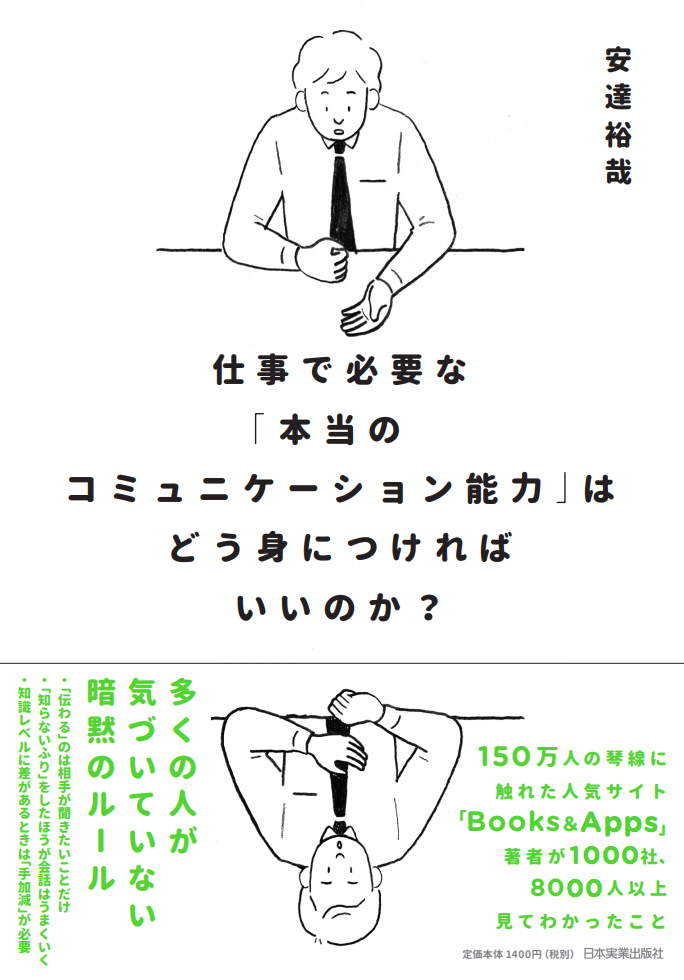
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者プロフィール】
・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)
・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント
・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ
・ブログが本になりました。
・「「仕事ができるやつ」になる最短の道」のオーディオブックもできました。
(Photo:Neil Carey)
*1














