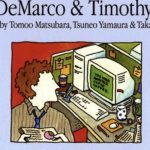所用があって、昔住んでいた町に立ち寄った。
その時にはもう、私が生まれ育った家はなくなっていたし、近所に住んでいた友人たちもほうぼう散って、そこは故郷でも、私のよく知る町でもなくなっている筈だった。
それでも見慣れた下町の風情や、昔はピカピカしていたマンションが、ベランダに干された洗濯物や布団といった生活に垢じみているのが目に入ると、ちょっとした郷愁が湧き起こって、私は昔よく遊びに通った神社に立ち寄ることにした。
もう日暮れ近い。玉砂利に夕日が差している他は、境内には誰もいなかった。
本殿の脇にある、小さな稲荷の祠の前で猫の親子がのんびりと毛づくろいをしている。
後ろで自転車が止まる音がした。
奇妙な予感にとらわれて振り返ると、少し離れた場所に、やせ細った骸骨のような老婆が自転車に乗ったままこちらを見ていた。
老婆は目を細めて私の顔を見ている。何かを言いたそうにサドルの上でもじもじとしていたが、私が黙礼すると、はっとしたように体を立てて自転車を神社の出口に走らせた。
私はあの老婆を知っていた。彼女は近所にあった駄菓子屋の婦人に違いなかった。
その駄菓子屋は、彼女とその夫が営んでいて、近所に住む私が訪れると、店主夫婦は嬉しそうに店の奥から顔を出して、私が100円の小遣いで駄菓子を迷い迷い買うのを、ニコニコと眺めていたものだ。
私にとっては、親切な近所の店であって、当然足繁く通っていた一方で、私の友人たちにはその店の評判はめっぽう悪かった。
店主の態度が悪い。
すぐに万引き犯扱いしてくる。
勘定を間違えられたので抗議しても悪びれるところがない云々。
そのどれも、私の印象とは全く違っていたので、そういう話を聞くたびに心にすっと冷たく重いものが入りこんで来るのを感じた。
私がその店主夫婦に依怙贔屓されているのだろうとは、気づいていた。
私の祖父が町内のごく狭い界隈で、名士と見なされていたことも関係していたであろう。
しかし、なにより、駄菓子屋の夫婦が私を見る視線に、別の、得体の知れない好意が含まれていることに気づいてもいた。
夫婦には子がいなかった。
祖父が昔語りに言ったところによると、昔苦心して産んだ子がいたが、幼くして亡くなったらしい。
あの夫婦にとって、毎日のように訪れてくれる私や、夫婦のお眼鏡にかなった子供は死んだ我が子の代わりでもあったのかもしれない。
私のほうも、礼儀正しく、明るく無邪気に振る舞うことで、その好意に報いてはいたと思う
それでも自分に故のない愛情を素直に喜ぶことができるほど、私は幼くもなかったし、全てをわかったうえで抱擁するほど天性の優しさを持っていたわけでもなかった。
やはりどこかで、まとわりつく、じっとりとした湿り気のような気味の悪さを感じていたようにも思う。
生家の近所には他にも酒屋のような店があって、私はよくそこに、みりんや醤油の一升瓶を買いにおつかいに行かされた。
スーパーはでき始めていたが、まだ家からは遠く、コンビニというものはまだなかった。
だから、酒の他は乾物ばかりを扱うその小さな商店も、下町の家々に挟まれて辛うじて商いが出来ていた時分だった。
店はだいたいにおいて無人であった。酒と缶詰やインスタントラーメンなどの食料品が、整然と並んでいる店内を、消えかけの蛍光灯が薄暗く照らしている。
私が目当ての商品を持って、すいませーん、と大声をあげると、ほとんど真っ暗になっている店の奥から、信じがたいほど腰の曲がった年老いた店主が出てきて、ヨタヨタと近づいてくる。
老人は商品を一瞥すると、○○円とぶっきら棒に言った。愛想がないと言うよりは、耳が遠いので、客とは何ら会話が成立しないと諦めている、氷のような孤独が感じられた。
その店に、30代後半ほどの女性がいた。噂好きの母によると、その老人の孫だったか、姪だったかで、結婚して家を出たが、結局離縁して出戻ったのだと言う。
彼女が老人のかわりに店番をつとめることがあった。
長い髪にうりざね顔で、若い時はさぞかし美人であったのだろう、と思わせる面立ちだった。
生活じみた垢抜けない服装と、諦観を示し続ける冷たい目の印象があって、彼女のまわりだけ光が失われていくような暗く冷たい印象をのこす女性であったのを覚えている。
彼女が店に出ている時は勘定の度に大声を上げずにすむので助かったが、彼女もまた老人と同じく固く表情を結んで、やはり無愛想で、何より、子供の私に何の興味も示さず、くれぐれも私のほうが彼女に親しみを表さないように、大人が生来もっている「隙」を、わざと作らないようにしている気がした。
私は、時々、腰の曲がった耳の遠い老人と二人だけで暮らす、その女性のことを想像した。
おそらく両者の間にほとんど会話はないのではないか。
彼女は暗闇の続く店の奥で、家事をする他は、あのどこか他の場所を夢見て現世を見ることのない瞳のまま、正座して静止している。
そんな不気味な絵を思い浮かべていた。
今になって思うと、子のいない家族や独身の女性について、幼い私は、随分と冷たい目線を持っていたものだと思う。
それは一番に、私や近所の住人が皆、家族や同じく暮らす一族というものに属しており、それらを総称する「家」の住人であったからだろう。
当時、「家」を持っていることはまさに「普通」の事であって、また人が生きている上で最低限に保証されてしかるべきものであった。
だから、その「家」を正しく持たない者は、口さがない町内で陰口を叩かれるし、当人もどこか後ろめたい、ぼんやりとした陰の中で暮らさねばならなかった。
さぞかし、生きづらい時代であったろうと思う。
*
時代が巡り、今では結婚をせず、または判断として子をもうけることのない人が増えた。社会全体の出生率は往時からは見る影もないほど落ち込んでいる。
人々が何故結婚しないのか、子をもうけようとしないのか、人によってはごく単純な答えが返ってくるだろし、様々な要因が複合的に重なったものだ、という見解もある。それらを包括した上手い言い回しもあるかもしれない。
私はその方面に詳しいわけでもないので、そのような論評を見る度に、いちいち納得はするのだが、さりとて、政府や社会がこれから取るべき方策についてこれといった名案を思いつくでも、ある主張に飛びつくでもない。
自分でも、私が家庭を持たない理由や、社会がどうしてくれればその気になるのか、明確に自信を持って答えることができないのである。
このような問題は「人それぞれ、色々だ」としか言いようがないという気もする。(その「色々」が存在することに社会の責任があることもまた、事実ではあろうが)
とにかく、多くの人にとって「家」を持つことも、「家」を繋いで次代に託すということが、容易ならざる時代になっている事は確かだろう。
しかし、同時に、「家」を持たない者が社会の中で異分子扱いされなくなって、毎日の食事は24時間営業のコンビニで調達でき、お盆や正月でも、マクドナルドが開いているという世の中は、私のような独身者には有り難いとも思う。
一方で、忘れがちだが、「家」が所与のもので、あって当然のものであるという気持ちが、まだ私たちの精神を縛り続けているのも事実だ。
ネットの掲示板などで、アラサー、アラフォー女子が800万円もの年収を男性に求めたり、40代のバツイチのおじさんが20代前半の女性を希望したりしていることが、滑稽な情景として語られることがある。
多くは「身の程知らず」であるという論調だが、かつてあった「家」という概念が彼らを縛り続けているのだとすれば、それもまた酷な見方だと思わないでもない。
アラフォー女子たちにすれば、高齢出産や子育てで、仕事のキャリアが継続できないであろうという前提のもとに、せめて親並みの結婚生活をしたいと思う、ただそれだけの「希望」を叶えることを、明確にはっきりとした「条件」として示すなら、現実離れした「年収」の数値としてそれを表現するよりない。
また、バツイチおじさんたちからすれば、今更ながら子供を生んで、年老いた両親にも可愛がれそうな嫁を持とうという、これまた「希望」を、結婚相手の「条件」として表現した結果が、結婚相手に不釣り合いな年齢を望むことになった、と見ることもできる。
彼らの婚活がおそらくは上手くいかないであろう事は、はっきりと「家」というものがこの社会で維持できなくなっていることを示している。
そしてそれは、きっと何か明確な悪者や過ちがあってのことかもしれないし、いつの時代も起きうる「変化」の一つに過ぎないのかもしれない。ただ、そうなってしまった。と言う他ない。
*
ある秋の日、母が一緒に父の墓参りに行こうと言い出した。
道すがら、母は隣のコンビニで店長をしているおばさんの息子が結婚したよ、と私に言って、店長との一連の会話の様子を話した。
母は「いいですねえ、うちは兄も弟も結婚できません。羨ましい限りです」みたいな事を店長にぼやいたのだが、店長の恰幅のよいおばさんは
「奥さん」と母の目を見据えて言った。
「結婚するだけなら誰でもできまっせ!」
母がその話をするのは、明らかに私に対する当てつけであったが、私も慣れたものだったので、鷹揚に聞き流すことにした。
そして結婚について考えた。
伴侶の当てもない。結婚できたとしても、子供ができた時の算段がつかない。金がない。ついでに言うと家もないのだ。
私にとって、結婚や家族を持つということは、一つの憧憬ではあった。
だが、それはステレオタイプな幸せのイメージにすぎなくて、まったく現実感を欠いていた。
父の墓に線香を上げた。墓前で二人、しばらく話をした。
母は、自分が死んだら父の墓に入る、あんたは次男だから、家族を持ったら新しく墓を作るだろうから、別の墓になるね、という事をしんみりした様子で言った。
私は母の楽天的な見方に半ば呆れて、
「オヤジの墓にオカンと、兄貴、俺。全部で4つ。みんな一緒に入る、思うけどな」
と言った。
「なんで誰も結婚せんねや!」母がさすがに怒って言った。
そしてその調子のまま「そんなことあるかいな」と言い捨てて、私を置き去りに歩き始めた。
山を削って作られたその霊園の小高い丘に、私たち「家」の墓はある。
そこからは大阪湾が望めた。青々とした水平線からよく晴れた秋の空が続いている。
海に向かって長い階段が伸びていて、母がそれをブリブリとした様子で下っていくのが見えた。
沖に作られた人工島から豆粒ほどの飛行機が飛び立つ。
私たちは、ここでなら、相変わらず家族でいられるのかもしれなかった。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【プロフィール】
著者名:megamouth
文学、音楽活動、大学中退を経て、流れ流れてWeb業界に至った流浪のプログラマ。
ブログ:megamouthの葬列
(Photo:Wyatt Fisher)