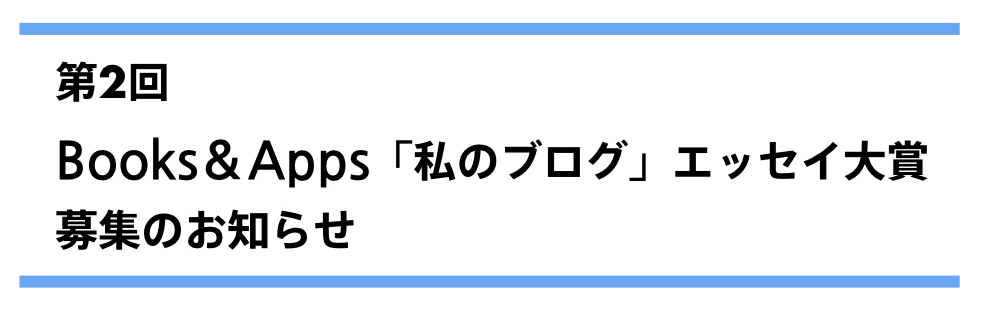3月といえば、卒業や異動・転勤の月ですね。
僕もこれまでの人生で、かれこれ10か所近くの病院で働いてきました。
最近は、3月31日まできっちり働いて、翌日には次の職場、ということは少なくなってきましたが、以前は、3月の最終日も定時まで働いて、翌日は朝いちばんで次の職場で仕事、ということも多かったのです。
外科の医師は、3月31日の夜に緊急手術、というのも何度かみてきました。
内科の場合も、出勤最終日の時間ギリギリに、ずっと診ていた患者さんが紹介されてきて……ということは少なくありません。
医局に属していれば、1〜2年での転勤が日常茶飯事の医療業界でも、やはり、転勤前というのは慌ただしくなります。
入院中および外来の患者さん全員に、簡単な経過と治療方針のサマリーを書くなどの、引き継ぎをしなければならないし、いろんな部署からの送別会が続きます。
何年間かでも、苦楽を共にした職場であれば、寂しい気持ちにもなります。
ある病院に勤務していたとき、同じ科に、少し年上の「すごく良い先生(以下、先輩)」がいたのです。
先輩は人から頼まれたことをほとんど断らず、自分の専門外の患者、あるいは、「救急外来に運ばれてきたけれど、どの科も引き取りたがらないような『老衰』のような患者さん」も、いつも笑顔で受け入れていました。
穏やかな人で、どんなに忙しいときでも、声を荒げたり、他のスタッフにきつくあたるようなこともなかったのです。
しかしながら、仕事というのは「できる人」「断らない人」に集ってくるものでもあります。
他所の科からの相談は「話しやすくて、なんでも引き受けてくれる」先輩に集中し、その先生は、同じ科のなかでも図抜けて大勢の担当患者を抱えて、いつも夜遅くまで仕事をしていたのです。
病院というのは、「その場にいる」だけで、「ついでにちょっと御相談なのですが……」という状況になることもあり、先輩の仕事はさらに増えていきました。
ある上司は、「あいつは立派なヤツだけど、あんな働き方をしていたら、いつか壊れるんじゃないか」と心配していたのです。
「専門外の患者まで抱え込んで、何かトラブルが起こったら、自分の首を締めることになる」とも。
僕も内心、「あんな働き方はできないし、この病院では、どんなに仕事をしても給料が上がるわけじゃないのになあ。家庭のことはどうなっているのだろう」なんて、思っていたものです。
その年の3月31日、先輩は転勤することになりました。
正確には、転勤ではなく、地元の病院に戻ることになったのです。
その日、先輩がいつものように仕事をして、同僚の医者たちにお別れの挨拶をし、病院を出ようとしたときのことでした。
「先生、ちょっと待って!」
ひとりのベテラン看護師が、彼に玄関ホールで声をかけました。
すると、四方八方から、看護師や事務の人などが集ってきて並び、先輩のための「花道」をつくったのです。
大勢の人が、そのために先輩の帰りを待っていたのです。
みんなが手をつないでつくったアーチを通り抜けながら、先生は少し泣いているように見えました。
僕が見た、その長い花道も、少し潤んでいたのです。
しばしの別れの場面のあと、先輩は大きな花束をたくさん抱えて、病院を出ていきました。
途切れない、拍手の中で。
僕は基本的に「賞罰なし」の人間だし、いつも「働いた分は給料をもらいたい。生活もあるしね」とか「プライベートな時間がたくさんほしい」と思っています。
転勤するときは、盛大に送別会をしてもらえることもあれば、めんどくさいから誰にも会わないように、と、ひっそり職場を出ていったこともありました。
この先輩のときのような、熱い「見送り」は、僕自身が体験したことがないのはもちろん、それまで見たことがなかったし、その後もありません。
その病院を僕が去るときも、儀礼的なお別れのやりとりだった。
いや、当時の僕の働きぶりで、あんな盛大なお別れをされたら、かえって恥ずかしくて消えてしまいたくなったでしょうけど。
僕は、あのとき、そんなふうにみんなに惜しまれて送られていく先輩をみて、すごく羨ましかったのです。
あの時間は、彼自身が、これまで自分のいろんなものを犠牲にしてやってきたことの、ささやかな見返りだったのでしょう。
そのために、あそこまでの仕事ができるか?と問われたら、やっぱり僕にはできない。
僕には、日常でのささやかな「ラク」の積み重ねのほうが、たぶん優先順位が高いのです。
因果応報、には違いありません。
先輩には、たしかに、あれだけのことをしてもらう「資格」があったと思います。
そして、医者としての日常と現実に直面する前の自分が「医者とは、こうあるべきだ」と思っていた姿が、あの場面にはあったのです。
僕は現実のめんどくささや身体のきつさに負けてしまった。
僕のなかには、あの先輩の働き方は「セルフブラック労働化」だ、という気持ちもあったのです。
そこまでやって、自分を追い詰めて、壊れてしまったらどうするんだ、という。
医者という仕事は、自分からやることを見つけようと思えば、底なし沼のように仕事が尽きない。
仕方ない、僕にはこれが限界だったんだ……。
今の世の中では、「身を削って仕事をする」ような働き方は、時代遅れとか、自分を大事にしていない、なんて言われがちです。
僕には、「そうだよなあ」という気持ちと、「それは、きちんとやらない(できない)自分への言い訳ではないか」という後ろめたさが、ずっとあるのです。
先輩が見送られていた光景は、僕にとって、なんだかとても崇高なものとして、いまでも胸に刻まれています。
「立派に生きる」ことを、いつのまにか放棄したことに気づいた、自分への苦みとともに。
その一方で、「それで給料が上がったわけでもないし、あの一瞬の祝祭のために、先輩は、あれだけの仕事を請け負う価値があったのだろうか?」とも考え続けているのです。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者プロフィール】
著者:fujipon
読書感想ブログ『琥珀色の戯言』、瞑想・迷走しつづけている雑記『いつか電池がきれるまで』を書きつづけている、「人生の折り返し点を過ぎたことにようやく気づいてしまった」ネット中毒の40代内科医です。
ブログ:琥珀色の戯言 / いつか電池がきれるまで
Twitter:@fujipon2
(Photo:Matt Madd)