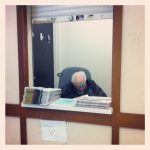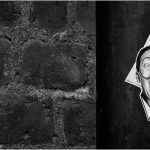勢いのある会社は、人を積極的に採用する。
そんな会社の一つでの話だ。
「経験者がほしいねー」と、目の前の経営者が言った。
だが、腹心の人事担当役員がそれを諌める。
「いや、経験者ってだけでは、大したことないですよ。むしろ広く未経験者にも目を向けるべきです。」
「未経験者を育成するのは大変だろう。」と社長。
「そんなことはないです。むしろ下手な経験者よりも、未経験でも学習能力の高い人を採用するほうが、圧倒的にコスパが良いです。」と役員。
なぜこんな食い違いが生じるのか。
実は、当然だ。
お互いに「パフォーマンスの源泉」を、別の場所に見ているのだから。
*
例えば、次のような話がある。
営業職を募集している会社があり、AさんとBさん、2名の応募があったとする。
経験年数は、Aさんは5年。一方のBさんは未経験だ。
Aさんは営業の現場が長く、即戦力として使えるが、適性検査と面接の結果、「保守的で、ルール通りやることは得意だが、新しい試みは苦手」という結果が出た。
Bさんは営業の経験はないが、「新しいものへ意欲的であり、学習力が高いが、前例を踏襲することやルール遵守は苦手」という、Aさんと逆の結果が出た。
Aさんを採用するか、Bさんを採用するかは、採用側が何を重視するかによって、大きく変わるだろう。
冒頭の社長は、Aさんを採用するだろう。
社長は「ルールを知っていること」「ルールを教えなくて済むこと」を重視しているからだ。
一方で人事担当役員は、Bさんのような人物を積極的に採用したいと考えている。
この役員は、長い人事の経験で、人材のパフォーマンスは「学習能力」に大きく依存していると考えているからだ。
*
もちろん「経験者」かつ「学習能力が高い」が最高なのだが、そんな人は母数が少ない。
話は必然的に「どちらを優先するか」になる。
では「経験」と「学習能力」のどちらを優先するか。
最近の採用の傾向を見ると、どうやら人事担当役員の着目している「学習能力」に軍配が上がるようである。
例えば、Aさんの長所である「経験」は、顧客が変化したり、商慣習の違うところでは通用しないかもしれない。
特に現在は、商品のライフサイクルが短くなり続けているので、「去年のやり方」ですら陳腐化してしまっていることも数多くある。
だが、Bさんの長所である「学習力」は、顧客が変化したり、商慣習が異なっても、それに対応できる蓋然性が高い。
学習能力が高ければ、ほとんどすべての経験から「学び」を引き出すことが出来る。
例えば、個人的に「学びの鬼」と思っている方の一人が、勝間和代さんなのだが、こんな記事を見かけた。
京都で車道を片道2キロ、合計4キロ走ったら、クラクション4回鳴らされました。けっこうびっくり。そして、ググってみたら、理由がちょっとだけわかりました
今日、京都でほんの片道2キロずつ走っただけで、行きに3回、帰りに1回、クラクションを鳴らされて、ほんとうに驚きました。
別に、ふらついているわけでもなく、ピクトグラムの上をちゃんと時速25キロから28キロ位で走っています。
もちろん、自転車が走っているのを相手が道路交通法を守っているのに、どかそうとしたり、遅いとあるいはじゃまだと威嚇するため、車がクラクションを鳴らすのは、道路交通法違反です。
そしてちょっとググってみたら、こういうことでした。大阪と京都は、クラクションを鳴らす率が高い都道府県、1位と2位だそうです。
「クラクションを鳴らされた」という些細な経験だけで、このように調べていたら、日常の「学びの回数」は、一般人とは桁違いになるだろう。
さらに、立教大の中原氏は、「未来は、働きながら、学ぶこと、学びながら、働くことがより「常態化」してくるのではないか。」と述べている。
(「学生」と「社会人」という言葉が「死滅」する将来!? : 働きながら学び、学びながら働く「未来」!?)
ともあれ、この「些細な事象からでも、知見を引き出し、学習することができる人」こそ、雇うべき人材なのだ。
*
「私は経験◯年以上です」と、経験を語る人がいる。
だが本質的には、その長さにはほとんど意味はない。
単に言われるがまま、業務を反復しているだけの時間は「経験」ではないからだ。
例えば、こんな研究がある。
ハーバード・メディカルスクールの研究チームは、医師が提供する治療の質と、医師の経験年数の関係を調べた。
すると、年長の医師のほうが遥かに経験年数の少ない医師と比べて知識も乏しく、適切な治療の提供能力も低いことがわかった。
経験を積むほど医師の能力が高まっているという結果が出たのは、62本の研究のうちわずか2本だった。
これは、看護師も同様で、極めて経験豊富な看護師でも、平均してみると看護学校を出てほんの数年の看護師と治療の質は全く変わらないことが示されている。
単純に言えば、仕事のパフォーマンスの源泉は、経験の長さ<<<<<<<学習能力 であることが、科学的に検証されている、ということだ。
だから、「何かをこなしてきた」=「経験」というのは、間違いであり、その体験を「経験」と言えるのは、そこから学びが得られている場合だけである。
その種類の経験は、意図的に行動しなければ、手に入らない。
そう考えれば、大半の体験は、「経験」とは呼べない代物である。
だから、採用では 「経験そのもの」よりも「経験を通じて、どのような学びを得たか」を調べたほうが、良い人が採用できる。
*
余談だが、私が「経験」について読んだ中で、最もしっくり来る知見を与えてくれたのは、以下の文章だ。
単にある職業につき、反復的な仕事をしているだけではフーピンガーナー教授が言った〝経験〟にはならない。
経験とはなにか新しいことを発見し、学び、能力の成長と蓄積をもたらすプロセスである。
そのために出て行って、そういった種類の経験を意識的にさがし求めなくてはならない。手を伸ばしてつかみ取らなくてはならない。
必要ならあらん限りの知能をしぼって、なにかより良いもの、なにか新奇なもの、従来の物事のやり方とはどこか違ったものをつかんでこなくてはならない。それが創造的経験というものだ。
やることが創造的ならば、失敗すら経験という宝をひとつ増やしたことになる。だれかがずっと昔、私に言った言葉を借りれば、「予期しなかったものを獲得した時に得るもの──それが経験だ」。
「予期しなかったものを獲得した時に得るもの」が経験だとすれば、漫然とこなしている仕事の殆どは「経験」ではない。
私はこの文章を読んで以来「経験者」の定義を大きく書き換えた。
それは、あらゆる仕事の根幹に関わる、大きなインパクトがあったことは、言うまでもない。
◯Twitterアカウント▶安達裕哉(人の能力について興味があります。企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働者と格差について発信。)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
◯Twitterアカウント▶安達裕哉
◯安達裕哉Facebookアカウント (安達の記事をフォローできます)
◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をフォローしたい方に)
◯Eightアカウント(本記事の読者の方であれば、どなたでも、名刺交換リクエストを受け入れます。)
◯ブログが本になりました。
(Photo:reader of the pack)