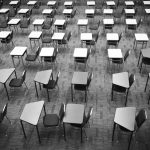パフォーマンスは努力や意志力ではなく「環境」が決める
年収は、働き手の資質ではなく、住むところで決まるという事実がある。
職務経験、教育レベル、IQ(知能指数)の違いを考慮に入れて比較をおこなっても、年収の格差は同じように存在する。
要するに、働き手の資質自体にはあまり大きな違いがない。違うのは、その人が働いている地域の経済のあり方、とくにその地域の高技能の働き手の数なのだ。
一見、直観に反する事実だが、
「地域の住民が受け取る収入は、その地域の産業の生産性の高さで決まる」
と言われれば、ごく当たり前の話かもしれない。
極めて生産性の高い(≒収益性の高い)産業は、周囲にお金をばらまくので、高技能な人材から、純粋な肉体労働者まで、住民が就くことのできる仕事の種類を増やす。
その結果、労働者全体の手にする収入も向上する。高学歴の働き手だけでなく、学歴の低い人の給料も高くなるのだ。
実際、全米でウェイターの収入が一番高いのは、巨大な収益を生み出すラスベガスで、トップクラスの高級レストランでは年収は1000万円をゆうに超え、平均でも時給は2000円を超えている。
また、現在のカリフォルニアにあるような巨大なハイテク産業は世界中から金を吸い上げ、一部を地域に還元する。
だから、「年収は住むところで決まる」と言っても差支えがない。
高い年収が欲しければまず、スキルを云々する前に、生産性の高い産業が存在する地域に住むこと。
これが正解となる。
自分だけを見ていては、カネは稼げない。
*
親は、子供の性格の形成に重要かつ長期的な影響は”及ぼさない”、という事実がある。
今日では人間の特徴の多くが行動遺伝学の観点から研究されるようになった。その結果は明白で一貫性がある。
総じて、被験者間の違いのほぼ五〇パーセントは遺伝によるもので、残り五〇パーセントが環境の作用であるというのだ。
この研究が示すのはむしろ、「育ち(親・家庭の影響)」より「環境(置かれた社会的な場所)」の影響力の強さだ。
実際、子どもたちは「両親に対する性格」と「クラスメイトに対する性格」を状況に応じてうまく使いこなす。
人間の適応力は凄まじいものがあり、環境、つまり現代では「社会的な規範」にしたがって、人はコロコロその性格を変えるのだ。
例えば家庭内では、妹に対して横暴であり親の言うことを全く聞かない姉が、クラスメイトに対しては全く異なる性質を見せる、ということはよくある。
これは、猫をかぶっているのではなく、実際にはその2つともが彼女の性格なのである。
したがって、本質的に重要なのは親の関与、つまり「育ち」ではない。
「遺伝」と「環境」なのだ。
つまり、遺伝はコントロール不可能だが、自分の性格を変えようと思えば、付き合う人を変える。住む場所を変える。環境を変えることが何よりの近道なのだ。
*
「幸福度」や「体型」は、知らないうちに友人知人に伝播するという事実がある。
ある人の幸福が別の人の幸福に与える因果効果によって、クラスタリングが起こることもわかった。
ネットワークの数学的分析から、直接つながっている人(一次の隔たりにある人)が幸福だと、本人も約一五%幸福になるらしいことが示されている。
しかも、幸福の広がりはそこで止まらない。二次の隔たりのある人(友人の友人)に対する幸福の効果は約一〇%、三次の隔たりのある人(友人の友人の友人)に対する効果は約六%あるのだ。(中略)
たがいに認め合う友人が肥満になると、自分が肥満になるリスクも三倍近くになる。しかも、たがいに認め合う友人の持つ影響力は、友人だと思われている(だが自分は相手を友人だと思っていない)人の二倍になる
幸福になりたいなら、幸福な人のネットワークに入っていくこと。
体型を維持したいなら、健康的な体型を維持している人々のネットワークに入っていくこと。
これらも、知っている人にとっては当たり前の事実だ。
環境に働きかければ、卓越した成果が得られる
つまり、何が言いたいのか。
それは、ある人が「どのような能力を持ち」「何を感じ」「どのくらい得るのか」という話は、環境の影響が甚大、という話だ。
自助努力も結構だが、たいていの場合、スキルや意思力といった個人的なパワーは、強大パワーである環境の前には無力である。
言ってしまえば「環境」は戦略レベル。「努力・意志力・スキル」は、戦術レベルの話である。
戦略の失敗を戦術では取り返せない。
「朱に交われば赤くなる」という諺があるが、数々の研究はそれが事実であることを示唆している。
逆に言えば、環境に働きかかけることに成功できれば、個人の力を超えたアウトプットを出すことが可能だ。
スポーツの世界ではそれが顕著で、新技や世界記録が出ると、大きく競争環境が変わり、選手全体のレベルを引き上げる。
例えば、モーターサイクルのバックフリップ(後ろ宙返り)だ。
今では当たり前の技だが、1980年代後半から1990年代前半には、バックフリップは「不可能」だと言われていたという。
ところが1998年、バックフリップにチャレンジをする一本のビデオが広がったことで、突然「バックフリップはできるのではないか」と思われ始め、2015年には、ついにジョシュ・シーハンがトリプル・バックフリップを成功させた。
こうした事実を踏まえると、「仕事のでき、不出来」も当然、環境に大きく依存していると考えるのは自然だろう。
私もまさにコンサルティングの現場で人事異動により
「環境が変わると、人は性格もスキルも能力も変わる」
を実感してきたため、「何をやらせても無能な人物などいない」との個人的な確信は、ここからきている。
個人のパフォーマンスを高める「環境づくり」とは
ところで、この「環境」の話。
大きな話だけではなく、個人ですぐに役立つネタはあるのだろうか。
実はある。
個人のパフォーマンスを高めるうえでも、「環境」をコントロールするという考え方を持っていることはとても有利だ。
まず大前提として、個人のパフォーマンスを高めるのは、何よりも「集中」だということは昔から知られている。
ピーター・ドラッカーは次のように述べている。
成果をあげるための秘訣を一つだけあげるならば、それは集中である。成果をあげる人は、もっとも重要なことから始め、しかも、一度に一つのことしかしない。
集中が必要なのは、仕事の本質と人間の本質による。(中略)
自らの強みを生かそうとすれば、その強みを重要な機会に集中する必要を認識する。事実、それ以外に成果をあげる方法はない。
二つはおろか、一つでさえ、よい仕事をすることはむずかしいという現実が、集中を要求する。人には驚くほど多様な能力がある。人はよろず屋である。
だが、その多様性を生産的に使うためには、それらの多様な能力を一つの仕事に集中することが不可欠である。あらゆる能力を一つの成果に向けるには集中するしかない。
また、卑近な事例ではあるが、知人で、「困ったことに、休日が一番、仕事がはかどってしまう」と語る方がいる。
私も「早朝・深夜」に最も仕事が捗る事が多い。
要するにこれは、「人が仕事をしない時間帯に行う仕事がいちばん進みが良い」という経験則だ。
一体なぜ、このようなことが起きるのかといえば、
「割り込みが入らないから」に尽きる。
休日も、深夜早朝も、即レスを求めるメール・メッセージ、緊急の電話などから開放される。
質問のある社員からも、在宅で夕ご飯の相談をしてくる妻からも、話しかけられることはない。
重要なことに対して「阻害要因」をすべて、環境から取り除いた状態で仕事ができれば、成果が出るのは当然だ。
そう言う意味で、個人レベルですぐに効果がありそうなのは、環境をコントロールして、仕事を「シングルタスク化する」ことだ。
気の散るものを遠ざけ、割り込みを拒否し、一度に一つのことをとことん集中して行うのが、仕事における環境づくりの基本である。
実際、前述したドラッカーは「時間をまとめて使うことこと」を強く推奨している。
報告書の作成に六時間から八時間を要するとする。しかし一日に二回、一五分ずつを三週間充てても無駄である。得られるものは、いたずら書きにすぎない。
ドアにカギをかけ、電話線を抜き、まとめて数時間取り組んで初めて、下書きの手前のもの、つまりゼロ号案が得られる。
その後、ようやく、比較的短い時間の単位に分けて、章ごとあるいは節ごと、センテンスごとに書き直し、訂正し、編集して、筆を進めることができる。
実験についても同じことが言える。装置をそろえ、ひととおりの実験を行うには、五時間あるいは一二時間を一度に使わなければならない。中断すると、初めからやり直さなければならない。
シングルタスク環境を作る。
だから、高いパフォーマンスのためには、割り込みを排除し、まとまった時間を作り出すために、
「考えない」「自動」「かんたん」「消耗しない」
で、仕事に没頭できる仕組みをいれるとよい。
以下には私が実際に試してみて、簡単な割に極めて効果が高かった施策を掲載しておく。
1.携帯電話を絶対に卓上に置かない
便利さに負けて、携帯電話を卓上に置いている人が多いと思うが、気が散る原因のNo.1は携帯である。
だから基本私は、携帯電話を机におかず、できるだけ遠ざけて仕事をしている。
鞄の中や、手の届かない棚などに置き、近くに寄せないのはシングルタスク化の施策としてはかなり有効だ。
2.「通知」を全て切る
基本的に携帯電話、およびメッセンジャーなどのの通知はすべて切っている。
「こちらからあえて見に行かないと、メッセージが見えない」
状態に置くことで、割り込みを防ぎ、自分のタスクをコントロールできる。
3.次の予定を忘れるため、アラームを活用する
次の予定を気にするのは、注意力を使うので、消耗する。
だから、全く気にしなくて済むようにアラームを設定する。14時から会議なら、13時50分にアラームを鳴らす。
「次の予定を忘れていい」というのは、本当に気が楽だ。
なお、自宅ではスマートフォンに触れたくないので、Amazonのスマートスピーカーの音声操作によるアラームを利用している。
4.徹底的に、スケジュールに書いたことしかやらない
朝一番に今日のスケジュールを設定し、スケジュールに載っている仕事のみやる。
絶対に他のことをしない。
どうしても緊急でやらなければならない仕事は、スケジュールに入れてから始める。
スケジュールに載せられないものはどうせできない。だから、それ以外のことは、一切手を付けず、一切気にしない。
5.重要な仕事からスケジュールに入れる
スケジューリングする際には、重要な仕事から埋めていく。
すると、重要な仕事だけで埋まってしまうことがほとんどだ。
いかに自分が些末なことをやっていたかが、よくわかる。
6.メール、メッセージは見てよい時間を決めて、まとめて処理する
これはやっている人も多いだろう。
朝、昼、夕方の3回、30分程度ずつ時間を取ってメールを見ており、それ以外の時間は目の前の仕事しか見ないようにしている。
だから「即レス」は原則としてない。
7.やる気が起きない時はタイマーをセットして「3分だけ」やってみる。絶対に他の「簡単におわりそうなこと」をしない。
タイマーをセットして「3分でいいのでとにかく始める」は、大抵の場合有効だ。
ここで注意したいのは、「絶対に他の仕事をしない」ということだ。
楽な仕事に逃げても、何も解決しない。どうしてもダメなら寝たほうが良い。ただし椅子で仮眠にとどめること。
8.電話に出ない・電話を使わない
割り込みを防ぐため、電話には基本的に出ない。折り返す価値のある電話だけ、メールを処理するタイミングであとから折り返す。
なお、かかってきた電話番号はwebで調べれば迷惑電話かどうかだいたい分かるので、迷惑電話は着信拒否に設定しておくと二度と煩わされない。
また、相手が不在だと、電話をかけた時間まるまる損をするので、こちらから電話を使うことはない。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
◯Twitterアカウント▶安達裕哉
元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。
◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)
◯安達裕哉Facebookアカウント (他社への寄稿も含めて、安達の記事をフォローできます)
◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をすべてフォローしたい方に)
◯ブログが本になりました。
Photo by Luis Villasmil