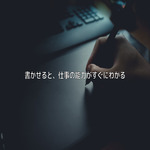まだ私がコンサルティング会社にいたころ、徹底的に訓練されたために、よく記憶に残っている項目が2つある。
1つは、「結論から言う」こと。これは別の記事に書いたので、詳細は割愛する。
そして2つ目が、今回のテーマである、「中学生にもわかるように書け」だった。
だが、これは、習得が極めて難しかった。
「中学生にも」と言うだけなら簡単だが、実践の指針がなく、上司などのレビューに頼っていたからだ。
実際、私は上司に資料を提出すると、しばしば「分かりにくい」と指摘をもらい、赤入れされた。
ただ、いつも気になっていた。
書き直すのはいい。私が未熟なのもわかる。
だが、「中学生にも」というのは、いくらなんでもお客さんを馬鹿にし過ぎではないか、と。
相手はいい大人だ。
しかし、私が一人でお客さんのところへ行くようになると、上司が「中学生にもわかるように」と言った意味がよくわかった。
なぜなら、誤解を恐れず言うと、仕事ができる/できないにかかわらず、「読んで、わかる」能力をもつ人はきわめて少数だったからだ。
少しでもわかりにくい文章、長い文章は、そもそもまず「読んでもらえない」し、それ以上に「読みたくない」と言われる。
仮に読んでもらえたとしても「誤解されて伝わる」か「うまく意図が伝わらない」のだ。
だから「読んだらわかる」能力は「面白い話ができる」とか「誰とでも友だちになれる」とか「人の心を読める」とか、そういった希少な能力と同じくらい、持っているひとが少ない能力だった。
上司は、経験的にそれを知っていた。
*
少し前に、「7回読み勉強法」というのが話題になっていたと記憶している。
文字通り、「基本書(教科書など)について、30分の流し読みを、7回する勉強法」ということで、その珍しさから様々な場所で紹介されていた。
成績優秀者として「東京大学総長賞」をいただいたのですが、その選考時に「どんな勉強をすれば、ここまで『優』を多く取れるのか」と聞かれ、「7回読めばだいたい覚えるもので……」と答えたのが、そもそものきっかけです。
もちろん、この勉強法は稀有な能力の持ち主のためのものだ。
本には「誰でもできる」と書いてあるが、実際に試してみると「7回」も同じ文章を読むこと自体が苦痛で、まず常人にはできない。
そして何より「7回読んだら理解できる」ということ自体が、異常なのだと、すぐに気づく。
そう。
普通の人は「何回読んでも理解できない」のが当たり前なのだ。
「読んだらわかる」のは、特殊な才能。
「AI vs 教科書が読めない子どもたち」の著者である新井紀子氏は、AIの研究を行う途上で、「多くの子供は教科書すら読めていないのではないか」という仮説をたて、「実際に読めていないこと」を確かめた。
そして、そこから新井紀子氏は「有名中高一貫校の教育方針は、教育改革に何の参考にもならない」と結論づけている。
「御三家」と呼ばれるような超有名私立中高一貫校の教育方針は、教育改革をする上で何の参考にもならないという結論に達しました。
理由がわかりますか?そのような学校では、12歳の段階で、公立進学校の高校3年生程度の読解能力値がある生徒を入試でふるいにかけています。実際にそのような中学の入試問題を見ればわかります。(中略)
そのような入試をパスできるような能力があれば、後の指導は楽です。高校2年まで部活に明け暮れて、赤点ぎりぎりでも、教科書や問題集を「読めばわかる」のですから、1年間受験勉強に勤しめば、旧帝大クラスに入学できてしまうのです。
そしてここに出てくるのが「教科書や問題集を読めばわかる人は、1年間受験勉強に勤しめば、旧帝大クラスに入学できてしまう」というフレーズだ。
「7回読み勉強法」の著者の主張と、よく似ている。
ここから類推すると、「読めばわかる人」の割合は、偏差値60以上。
つまり、多くとも15%程度ではないかと予想できる。7人に1人だ。
だから、上司は「中学生にもわかるように書け」と強調したのだろう。
*
ただ、勘違いしていただきたくないのは、「読めばわかる能力」は、能力の1つではあるが、ビジネスで求められる多様な能力の、ほんの一部に過ぎないという点だ。
手先の器用さ、お客さんに気に入られる力、優れた味覚、運動神経、巧みなスピーチ……
「読めばわかる能力」がなくとも、金儲けはできるし、卓越した仕事も可能だ。
以前にも書いたが、ピーター・ドラッカーは、世の中には「読む人」と「書く人」の2種類がいるとした。
読む人に対しては口で話しても時間の無駄である。彼らは、読んだあとでなければ聞くことができない。逆に、聞く人に分厚い報告書を渡しても紙の無駄である。耳で聞かなければ何のことか理解できない。
要は、組織におけるビジネスは「役割分担」なので、読めない人に無理やり読ませようとしないことだ。
また、「読める人」は、できうる限り「中学生でも読める文章」を心掛け、読めないことが意思疎通の妨げにならないようにしなければならないのだろう。
*
とはいえ、最近では「知識労働」が増加し、気を配って作られたわけではない(中学生では読めない)文献や資料を「読めない」ことが、仕事においてしばしば致命的な要因になってしまうことがある。
また、大学などが「無償で公開」しているノウハウも、読めない人にとっては存在しないのと同じだ。
特にテクノロジーの分野ではそれが顕著で、それが、「読める人」と「読めない人」の、差を生み出しているのかもしれない。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
安達裕哉
元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)
image:Anne Nygård