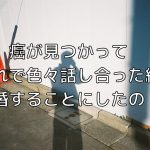コンサルティング会社で管理職をしていたとき、一人、悩ましい人がいた。
彼は能力的には高かったが、今ひとつ仕事では飛び抜けた成果を出せていなかった。
なぜか。
それは、彼が「難しい仕事」を嫌がっていたからだ。
「皆がいつもやっている、通常の仕事」は滞りなく終わらせる。
しかし、少しイレギュラーな仕事や、やり方がまだ生み出されていない「動きながらサービスを作り上げる仕事」を彼は嫌がったし、実際そういう仕事をふると、小さい仕事であっても、彼はほとんどいつも拒否した。
だから彼にはいつも、標準化がすでにされている「定型的な仕事」しか渡せなかった。
だから、必然的に成果は「量」の競争になる。
標準化されている仕事は、ある意味新人でも少し訓練すればできるので、彼の価値としては、「新人よりも、そこそこたくさん仕事を回してくれる」というくらいしかない。
必然的に、彼の給与の伸びもストップした。
*
彼に不足していたのは一体何だったのか。
能力ではない。
仕事のやる気でもない。
私の考えでは、それは「勇気」と呼ぶべきものだったと思う。
ただ、誤解があると良くないので、きちんと説明したいのだが、ここでいう勇気とは、悪に立ち向かうとか、弱きを助けるとか、いわゆるRPGの「勇者」のような存在がもつ特性ではない。
また、◯◯チャレンジといった企画のように、「周りの人の目を気にしない」とか、「無謀なことにチャレンジする」とか、そういうものでもない。
あえて言語化すれば、組織やビジネスにおける「勇気」とは、言ってみれば「未知を扱うマインド」と言えるだろう。
言い方を変えると、「勇気がある」とは、「できないかもしれない」「努力が無駄になってしまうかもしれない」というおそれに対して、耐性が高いということだ。
彼は「未知のもの」に対して、徹底的に弱かった。
「できないかもしれない」
「失敗するかもしれない」
「怒られるかもしれない」
そんなふうに、いつも恐れていたように思う。
例えるなら、この低金利の時代に「元本保証ではないから投資はしない。預貯金しか信じない。」と言っているようなものだ。
しかし、実際には財産は、インフレに寄って目減りしている。
そうして「未知のこと」を拒否し続けた人間の行き着く先は、「先細り」である。
「勇気」を教えるにはどうしたら良いだろう
もちろん「先細り」を受け入れるのであれば、そういう生き方もある。
むしろ、そういうひとに「未知への対処」無理強いをするのは無粋だ。
しかし、彼は給料が上がらないことに対して、不満を持っていた。
「更に上を目指すなら、新しい責任と、未知の仕事を引き受けない限り、手に入らない」と何度も説明していたにも関わらずだ。
でも、彼にしてみればおそらく「こんなに働いているのに、なぜ給料を上げてくれないんだ」と思っていたのだろう。
しかし、彼が仕事を引き受けないのは、彼のスキルによるものではなく、彼のマインドによるものであったから、こちらとしては彼に何もできることはあまりない。
こうなると、お互い不幸である。
*
そういった事態を自社だけではなく、様々な会社で見るにつけ、私は「勇気」を持つことの必要性を感じた。
また、果たして「勇気」は後天的に獲得できるものなのか、ということが気になった。
ビジネスというのは、未知への対処がうまいほど、大きな成功をしやすいからだ。
いや、ビジネスだけではない。
人を助けたり、皆が困っている問題を解決したり、子供を育てたりすることなどもすべて、未知を扱う以上、「勇気」に関わる問題だと感じる。
結局、勇気の欠如の最大の問題は「自分の見える範囲でしか考えられない」ということなのだ。
他者と関わる場合、必ず未知の問題が発生する。それを恐れて何もしないのであれば、得られるものがないのも当然の結果だ。
「システム思考」で知られるビーター・センゲと、「EQ」で知られるダニエル・ゴールドマンの共著「21世紀の教育」では、未知への対処が、非常に重要な教育の項目となっている。
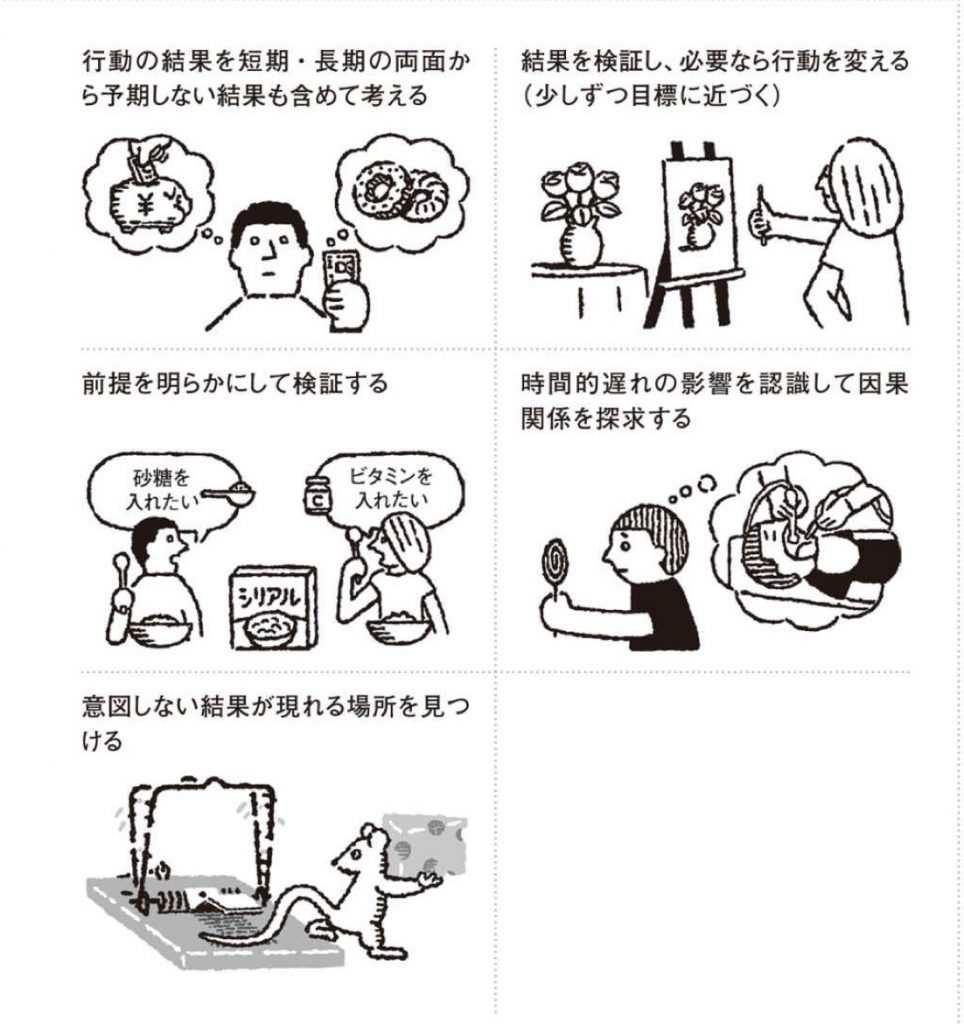
そして、こうした能力は、「やるべき範囲」や「出題傾向」が決まっている、学校の「受験」では身につきにくい。
学校教育は本質的には、予期しないことを嫌い、ランダムを遠ざけ、失敗をさせまいとするからだ。
しかし、上のような「未知への対処」は世界の各地で教育として取り入れられ始めているし、後天的に獲得できるものだとピーター・センゲらは確信しているようだ。
私もそれを信じたい。
文明は日常生活からリスクを排除し、快適さを提供し続けた。
しかし、どこまでいっても「リスク」をゼロにすることはできないし、他人と関わったり、未知に挑戦するリスクを取らなければ、貧しくなる一方である。
必要なのは「リスクを取らない」ことではなく、「リスクをうまく取るにはどうしたら良いのか」という知恵であり、実践的なノウハウなのだと、つくづく思う。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
安達裕哉
元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)
image:Michael Shannon