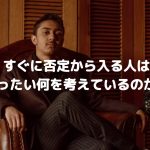まず最初に、この記事の結論を書いてしまおう。
それは、「社員の離職を防ぎたいなら社員の成長を求めるな」だ。
最近は「ひとつの企業にしがみついていては先がない!」という主張が広まり、副業や兼業が推進され、リスキリングという言葉もよく聞くようになった。
個人個人が自分のキャリアに向き合い、企業はそれを支援すべしーー。
そんななかで「社員の離職を防ぎたいなら社員を成長を求めるな」というのは逆張り甚だしいが、それにはちゃんと理由がある。
「よく働く層」を雇い続けるのはむずかしい
働きアリの法則をご存じだろうか。
集団のなかには、よく働くアリが2割、普通に働くアリが6割、働かないアリが2割いる。
たとえ100匹のアリのなかからよく働くアリのみを20匹集めたとしても、そのなかでも結局4匹はよく働き、12匹は普通に働き、4匹は働かなくなるという法則だ。
企業のなかでいえば、モチベが高くより大きな成功を求める野心家で、キャリアアップに積極的な人たちが「よく働く層」といえるだろう。
でもそれはせいぜい2割ほどで、実際は「普通に働く層」、毎日それなりに仕事をしてそこそこの生活ができればいい、という人が6割。
そしてその下には「働かない層」、ミスが多いのに改善する努力もせず指摘もアドバイスもどこ吹く風、俗にいう無能が2割いるというわけだ。
この分類でいえば、企業が重視するのは「よく働く層」だろう。
だから、成功を求める「よく働く層」をリスキリング支援や副業推進などで応援しよう、となる。
でも「よく働く層」は、成長に応じてよりよい待遇を求めるし、さらに成長できる環境を求めて独立したり転職したりしてしまう。
「雇い続ける」という観点から考えると、「よく働く層」は結構扱いづらい。
一方、「普通に働く層」は特に不満がなければわざわざ面倒な転職はしないし、日々の業務を平和にこなせればそれで満足。
「働かない層」は他では勤まらないので、かんたんには辞めない。
そう考えると、上位2割の「よく働く層」をより成長させるよりも、残りの8割である「普通に働く層」「働かない層」が働き続ける環境のほうが大事じゃないか?と思うのだ。
離職防止のため、だれもが安定して結果を出せる仕組みを考案
こう考えるようになったのは、『たった4年で100店舗の美容室を作った僕の考え方』という本がきっかけだった。
筆者の北原さんは2015年にディアーズ1号店を開業、4年で100店舗以上に事業を拡大している。
経営者の中には「社員の成長」=「会社の成長」という考え方が根強くあります。
しかし、ここでよく考えてみてください。
社員が成長しなければ、会社は成長できないものなのでしょうか?
「社員の成長」=「会社の成長」という考え方は、本当に正しいのでしょうか?
実際、僕がディアーズの社員に伝えているのは、「今のままのあなたでいいよ」ということです。
僕は社員に対して、成長を求めません。
のちほど説明しますが、僕は社員を成長させてあげようとは考えていませんし、社員が今のままでも成果が出るシステムを設計しています。
北原さんがとある美容室の店長を勤めていた際、やる気が空回りして、部下が何人も「ついていけない」と辞めてしまったらしい。
美容室は、美容師が1人減ればそのぶん業績が下がる。だから、美容師が辞めない店にすることがなによりも大切だと学んだそう。
ではどうするか?
そこで作り出したのが、「だれでも安定して結果を出せる仕組み」だった。
・センスによって評価が別れるカットではなく、だれがみても「きれいになった!」とわかる髪質改善に特化
・集客を個人に任せるとマーケティング知識の有無で差ができてしまうので、集客は自社のホームページメイン。美容師がマーケティングを学ぶ必要なし
・一番高いフルコース前提で集客するので、従業員はシャンプーやマッサージなどのオプション追加の売り込みをしなくていい
・単価が高い上位顧客を獲得できるかは、社員のプレゼンスキルに依存してしまう。そうならないよう、みんなが継続予約を90%以上とれるマニュアルを作成
・余計な雑談によるトラブル回避のため、美容師にはマニュアル以外の会話を求めない
こういった環境にすることで、お客様との雑談が苦手な人や売り込みがヘタな人でも結果を出せるようにしたのだ。
離職率0%!「よく働く層」をターゲットから外した求人
ここで大事なのは、「よく働く層」「普通に働く層」「働かない層」で、結果に差がつかないこと。
美容室で辞めていくのは、成長を求めて独立や移籍する月100万円を超える売上げの人と、給料をとれない月30万円前後の売上の人らしい。
つまり従業員が辞めないためには、上も下もなく、「みんなある程度できる」という状況が理想。
その理想を作るのが、「これだけやってればそれでいいよ」という、だれでも安定して結果を出せる仕組みなわけだ。
その仕組みに従ってマニュアルどおりやるだけだから、できる人・できない人の差は生まれない。能力による上下関係やモチベの差による軋轢もない。
でもそれでは、「よく働く層」にとっては物足りないんじゃ?と思うかもしれないが、そこも問題なし。
そもそもディアーズでは、キャリアアップを目指す「よく働く層」をターゲットにしてはいない。
上昇志向タイプは最終的に独立していなくなってしまうし、自分と同じ熱量をまわりに求めてトラブルを起こすし、自分の能力を発揮したいという自己顕示欲で多くのものを求めてくるから。
雇いたいのは、キャリアアップよりも働きやすさを望む人。そういう人は、労働環境が悪くならない限りは辞めない。
結果、ディアーズへの応募者はほとんどが女性になった。
だから女性が働きやすいよう、病児お迎えサービスの利用をサポートしたり、土日に学校行事に参加できるよう週休3日を採用。そして、驚異の離職率0%を達成したそうだ。
個人の能力に依存しないもの作りの世界
とはいっても、「だれもが安定して成果を出せる仕組み」なんて作れるものだろうか……とも思う。
しかし、たとえばトヨタのようなもの作りの現場では、むしろそれが当たり前なのだ。
個人のスキルやモチベによって質がバラけてはいけないし、ちょっとしたミスが取り返しのつかない大事故につながる可能性があるから。
トヨタでは、失敗の責任を個人に押しつけず、失敗しないしくみをつくることによって問題を解決します。
すなわち、新人でもベテランでも、誰がやっても失敗しないようなしくみを考えるのです。(……)
標準を決めて、それを丁寧に教えれば、ミスは激減します。
しかし、特にオフィスワークのような仕事は、「標準」といえるものが定められていないことがほとんどです。個人の裁量に任される仕事も多いため、アウトプットのスピードや質もバラバラになってしまいがちです。
しかし、どんな仕事でも、「標準」といえるものがあるはずです。標準を意識することで仕事のやり方は劇的に変わり、失敗も減ります。
たとえば、企画書や報告書といったものはフォーマットを決めれば、ある程度「標準化」が図れます。押さえるべきポイントが抜けていた、といった辞退は防ぐことができます。
また、提出期限の3日前に上司に企画書や報告書の下書きを確認してもらうといったことを職場の標準とすれば、書類の質を担保できますし、提出期限を過ぎるおそれも少なくなります。
出典:『トヨタの失敗学 「ミス」を「成果」に変える仕事術』
「ヒューマンエラーを減らす仕組み」はある意味、「だれでも安定して成果を出せる仕組み」ともいえる。
個人差がつかない、能力に依存しないというのは、そういうことなのだ。
社員が成長せずとも安定した結果を出せる仕組み作りが大事
最後にもう一度、美容室ディアーズを展開した北原さんの言葉を引用させていただこう。
そうして一周回って気付いたのは、結局のところ、人を育てることはできないということです。
根底として、人は変わらない生き物だし、価値観だって、そうそう変わるものではありません。
人が育つのは、その人が勝手に育つのであって、僕らにできることがあるとすれば、成長を後押ししてあげることだけです。
そう、成長なんて、やりたい人は勝手にやるものなのだ。期待するようなもんじゃない。
毎日塾に行っても赤点を取る子がいる一方で、一度も塾に行かなくとも自分で勉強してオール5の子がいるのと同じ。
いくら勉強する環境を整えてもやらない人はやらないし、多少環境が悪くてもやる人はやるのだ。
「成長したい」「育てよう」というのはかんたんだが、それには優秀なリーダーや先生、本人自身のやる気や能力、ポテンシャルなど、多くの要素が必要になる。
社員の成長=会社の成長なら、社員が成長しなければ会社は成長しないし、社員のモチベが下がれば業績も下がる。期待ほどの成果を出せなければ、投資損。成長しても、独立や転職しちゃうし。
これでは不確定要素が多すぎて、ちょっと不安だと思わないだろうか。
もちろん、スキルアップ支援をしたり多様な働き方を可能にしたりすることは、多くの人にいい影響を与える。それも大切だ。
でもよく働く2割に成長を期待するよりも、だれでも安定して結果が出せるほうが、従業員はムリしなくていいし企業は離職を防げるし、合理的でwin-winなんじゃないかなーと思うのだ。
というわけで、「社員の離職を防ぎたいなら社員の成長を求めるな」という結論に至ったのである。
正確にいえば、「社員が成長せずとも安定した結果を出せる仕組み作りが大事」。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
名前:雨宮紫苑
91年生まれ、ドイツ在住のフリーライター。小説執筆&
ハロプロとアニメが好きだけど、
著書:『日本人とドイツ人 比べてみたらどっちもどっち』(新潮新書)
ブログ:『雨宮の迷走ニュース』
Twitter:amamiya9901
Photo by :Pietro Zuco