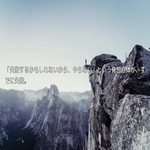最近、SNSで「生存者バイアス」という言葉をやたらと見かけます。
生存者バイアスだろ https://t.co/PYLeKHa8Nj
— 宇宙医ヌ (@QBotud) May 31, 2024
生存者バイアスとは「うまくいった例だけに着目して、失敗に注意を払わないこと」に対して使われる言葉です。
「厳しい環境においたら成長できる」←無数の死体(精神疾患になった人)を無視してるだけの生存バイアスなのだ。
生き残れる人は元々メンタルが強いってだけのオチなのだ。— 沼ずんだもん (@nuoo15gjwdg) May 17, 2024
確かに、彼らの言う通りです。
ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンは、成功例しか見ずに一般論を語る人間の傾向を、「自分の見たものがすべて」(WYSIATI)と紹介しています。
限られた手元情報に基づいて結論に飛びつく傾向は、直感思考を理解するうえで非常に重要であり、これから本書にも何度も登場する。この傾向は、自分の見たものがすべてだと決めてかかり、見えないものは存在しないとばかり、探そうともしないことに由来する。
生存バイアスを指摘する人々は、「成功の保証なんてないだろ」と叫んでいるのです。
ここで俺も欲しくなかったけど〜のお気持ち表明いらんのよ。生存者バイアスでしかないんよ。お前ら責任とれるんか? https://t.co/93szOzQ4T2
— 正論パンチ (@iloveqoo2024) June 1, 2024
なるほど。
彼らの言いたいことはよーく、わかります。
しかし、私は逆に思いました。
「成功の保証がされている行為なんてあるのか?」と。
一生懸命勉強したほうがいいよ
→ 勉強しても、希望の学校に入れないかもしれない。
一生懸命働いたほうがいいよ
→ 一生懸命働いても、給料が上がるかはわからない。
踏ん張りどころだよ
→ メンタルをやられるかもしれない。
起業して夢をつかもう
→ 起業して路頭に迷うかもしれない。
結婚はいいぞ
→ 結婚しても離婚に至るかもしれない。
子供はかわいいよ
→ 子供を持っても、関係がうまく構築できないかもしれない。
知られているとおり、「絶対にうまくいく」「確実にもうかる」という言葉は詐欺です。
むしろ、「失敗」がついて回らないほうがおかしいのです。
だから「絶対に失敗しない」ようにするには、「何もしない」と言う選択肢しかありません。
*
しかし、本当にそれでいいのでしょうか。
失敗のリスクを取って、何かを実行することこそ、人生の本質ではないでしょうか。
ナシーム・ニコラス・タレブは著書「身銭を切れ」で、次のように言っています。
しつこいようだが、人生とは犠牲とリスク・テイクだからだ。リスクを引き受けるという条件のもと、一定の犠牲を払わないかぎり、それを人生とは呼べない。取り返しが利くかどうかにかかわらず、実害をこうむるリスクを背負わない冒険は、冒険とは呼べない。
本物の人生にはリスク・テイクが欠かせないという本書の主張は、心身問題に関する微妙な話題へと結びつく。
「意識たけー」と思うかもしれません。
しかし、勘違いしてはなりません。
彼は無条件にリスクを引き受けろ、と言っているわけではないのです。
むしろ合理的に、慎重にリスクを取るべきだ、と言っています。
ではどのようにリスクを取ればいいのでしょうか。
タレブの主張は、「確率」ではなく、「脆さ」に基くリスク・テイクです。
確率ではなく脆さに基づく意思決定を
私たちは、飛行機の搭乗前に乗客が武器を持っていないかをチェックする。それは、乗客をテロリストだと思っているからだろうか? 違う。乗客がテロリストだということは、まずない(微小な確率だ)。それでもいちおうチェックするのは、私たちがテロに対して脆いからだ。ここに非対称性が存在する。私たちはペイオフに着目する。さっきの命題が「正しい」(乗客が本当にテロリストである)場合の影響、つまりペイオフはとんでもなく大きいが、チェックする費用はごく小さい。
原子炉は来年爆発するだろうか? ノーだ。でも、「イエス」という仮定で行動し、安全の強化に数百万ドルを費やす。私たちは原子力の事故に対して脆いからだ。
三つ目の例。ここに適当に買ってきた薬がある。身体に害を及ぼすだろうか? ノー。じゃあ、飲んでみるかい? とんでもない。
机に座って、ここ 1週間(できれば今までの生涯)で下した決定をすべて書き出してみてほしい。そのほとんどに、非対称的なペイオフが潜んでいるだろう。たいていは、一方の決定の影響のほうが、もう一方よりも大きいはずだ。人は確率の大小ではなく脆さに基づいて決定を下している。言い換えれば、「正しい」「正しくない」ではなく、脆さに基づいて主に意思決定をしている。
この概念は少し分かりづらいですが、単純に言ってしまえば
「人生は確率に基づいて行動すべきではない。結果の大きさに応じて行動すべきだ」
というものです。
言い換えれば、賢い選択とは
「大儲けできる可能性があるなら、あれこれ試しながら、確率が低くても賭けておく。」
「一撃死する可能性があるなら、どんなに大儲けできる可能性があっても、やめておく。」
なのです。
これを体現したのが、タレブの主張する「バーベル戦略」です。
左側の脆弱のカテゴリーの場合、間違いはめったに起こらないが、起こるときは巨大なので、取り返しがつかない。右側の反脆弱のカテゴリーの場合、間違いは小さく穏やかなので、取り返しがつくし、すぐに克服できる。また、情報も豊富だ。
したがって、ある種のいじくり回しや試行錯誤のシステムには、反脆さという性質が備わっているはずだ。
反脆くなりたいなら、「間違いを嫌う」状況ではなく、右側の「間違いを愛する」状況に身を置くべきだ。そのためには、間違いはしょっちゅう起こるが、一つひとつの害は小さいという状況を作ればいい。本書ではこのプロセスやアプローチを「バーベル」戦略と呼んでいる。
まだわかりにくいかもしれませんので、例を出しましょう。
「賭博黙示録カイジ」で、主人公のカイジは2000万円をかけて、「落ちれば死」というギャンブル「鉄骨わたり」をします。

しかし鉄骨わたりはずいぶんと割の悪い賭けと言わざるを得ません。
なぜなら「一撃死」の可能性がある鉄骨わたりは、失敗した時の影響が大きすぎるからです。
「バーベル戦略」を採用するならば、普通のサラリーマンとして手堅く稼ぎつつ、一方で、副業や小商いをしながら、失敗を繰り返しつつ生き延びて、大儲けを狙うほうがずっと良い賭けです。
成長したい時には、まずは厳しい環境に身を置いてみて、失敗したと思ったら、手堅くすぐに身を引けばいい。
ひとまず結婚してみて、合わなかったらすぐに別れればいい。
そういうことです。

だから鉄骨渡りや、大きなギャンブルは回避すべきですが、「精一杯勉強しておけ」「仕事は頑張ったほうがいい」というのは、一種の真理です。
もちろん人間には「損失回避」の性向があるから、失うことに対して、大きな痛みを感じるでしょう。
が、あらゆるリスクを過大評価をするのも、またバイアスで目が曇っており、明らかに人生で損をします。
だから「失敗するかもしれないから、やらない」という発想自体が、すでに失敗なのです。
適切にリスクを取り、一撃死を避けながら、生き延びてチャンスをうかがいましょう。
そして、これは一言で言えば、「なりふり構わず生き延びろ」という事なのです。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
安達裕哉
生成AI活用支援のワークワンダースCEO(https://workwonders.jp)|元Deloitteのコンサルタント|オウンドメディア支援のティネクト代表(http://tinect.jp)|著書「頭のいい人が話す前に考えていること」60万部(https://amzn.to/49Tivyi)|
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯note:(生成AI時代の「ライターとマーケティング」の、実践的教科書)
Photo:Cristofer Maximilian