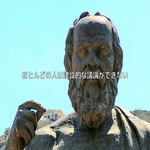最近、管理職になりたくない、昇進したくない人が増えているらしい。
主な理由は、「損をするから」。
責任が大きくなるし、仕事が増えるし、ストレスも感じるし、とにかく割に合わない。それなら言われたことをやってる平社員のほうが楽、というわけだ。
たしかに「中間管理職」は上にも下にも気を遣う損なポジション、というイメージは強い。
とはいえ、なんでここまで人気がないのだろう。なんで最近になって「昇進したくない」という話をよく耳にするようになったんだろう。
そもそも管理職って、なにをする仕事なんだ?
管理職が割に合わないのは、未経験の「人材管理」のせい?
管理職の仕事は、マネージメント。
具体的にいうと、「仕事の管理」と「人材の管理」を通じて、担当部署を運営していくことだ。
仕事の管理というのはその名のとおり、さまざまなタスクを割り振り、期限内に終わらせるように段取りを組むこと。
営業成績がよかったAさんが営業部門の課長になれば、部下たちの営業成績を見て担当の割り振りを決めなおして、各チームの方針を修正できる。
経理での経験が豊富なBさんが経理部部長になれば、提出された書類に間違いがないかチェックして、手続きの進捗を適宜確認できる。
仕事の管理であれば、これまでの経験や知識で、ある程度指揮できるのだ。
しかし「人材の管理」となると話が変わる。
先輩としてアドバイスする、ノウハウを教える、くらいならまだいい。多くの人がすでにやったことがあるだろうから。
しかし部下の「自律キャリア支援」「心理的安全性の確保」「1on1の面接でメンタルケア」なんて話になると、お手上げの人は多いだろう。
だってそんなこと、いままでやってこなかったんだから。
Aさんは営業成績がいいから課長になったし、Bさんは経理の経験が豊富だから部長になった。
それなのにいきなり「心理カウンセラー」「担任の先生」の役割を求められても、困るにちがいない。
管理職が「割に合わない」といわれるのは、主にこの「人材の管理」のせいなんじゃないかと思う。
上司は心理カウンセラーでも担任の先生でもない
少し前、こんなポストが話題になり、3.7万いいねを獲得した。
メンタルを病んでしまう社員がいる
=良い職場を作れていない
ってことなんだから、メンタル不調者が多発したらそこの管理職がペナルティを受けるシステムにしろよ何で涼しい顔で
「また休職か。最近の子は甘いな」
みたいなこと言ってんだ甘いのはお前への処分だろうが。たわけ者
— 定時で帰るの大好きさん (@nannotoriemomai) July 30, 2024
大前提としてこれは「多くの人がメンタルを病むのなら」という仮定の話ではあるが、こういうポストを見ると、「たしかに管理職ってわりに合わないなぁ」と思う。
「多くの人」が病むのなら、職場に問題がある可能性が高い。でもそれは、かならずしも管理職が対処できることとはかぎらない。
たとえば、過度なストレスによる教師のメンタルヘルス問題、なんてのはよくニュースになっている。たとえ教師を束ねる校長が人格者だったとしても、ムリなものはムリだ。
ほかにも、救命救急や消防に携わっている友人が、「うつ病で辞める人が多い」と言っているのを聞いたことがある。キツイノルマがある生命保険や金融系でもそういう傾向があるらしい。夜勤がある仕事も、例外ではないだろう。
職業柄、もしくは勤務体系などで、メンタルをやられやすい分野は存在する。でもそれは、管理職ひとりがどうこうできる問題ではない。
いくらメンタルをケアしても、どうしようもならないことはあるのだ。
これらは極端な例だとしても、たとえばこんな状況はどうだろう。
若手にもどんどん挑戦させることを社風とした、IT系ベンチャー企業。経験がなくとも、「やって覚えればいい」とどんどん仕事を任せていくスタイル。
その結果、10人のうち3人の社員が、「プレッシャーに耐えられない」「どうしたらいいかわからずつらい」「失敗続きでやる気がなくなった」と辞めてしまったとする。
これも、部下のキャパシティや性格を把握してコントロールできなかった、管理職のマネージメント不足なんだろうか?
……いやいや、それを管理職のせいにするなら、管理職なんてだれもやりたくなくなるよ。そういう企業だから若手にもチャンスがあるっていうのがウリなのに。
上司は心理カウンセラーでも、担任の先生でもない。それなのに、そういう役割を求められる。
これまでの知識や経験を一切活かせない人材管理の分野で、赤の他人のケアの全責任を負わされるなんて、あまりに酷じゃないか?
もちろん、部下を意図的に潰す腐った人間は論外だけど。
人材管理を学んでいない人が管理職になるのが問題
海外、とひとくくりにするのは大雑把だが、多くのジョブ型の国では、「管理職」に必要なことを学べる環境がある。
たとえばアメリカには、ヒューマンリソースの学士を取得できる大学は200校以上。ドイツにはいくつか職業教育のレベルがあり、そのなかには管理職向けのコースもある。
管理職ポジションの募集要項には、そういったコースの履修や経営・人事に関する学位が必須になっていることが多い。
現場ですでに仕事の管理は学んでいるから、次は人材の管理を学んでね。両方できるようになったら「管理職」になれるよ。こういうルートがあるわけだ。
(余談だが、こういう教育があるからこそ、現場のことをたいして知らない「人材管理特化型」がいきなり管理職になり、仕事の管理をめぐって現場とトラブルになることがある)
でも日本では年功序列の影響か、「仕事の管理」がある程度できるようになったら、そのまま管理職に昇進することが多い。そしていきなり、「人材の管理」も任される。
いままではそれでも、根性論と年功序列意識でどうにかなった。
人材管理、なんてむずかしい言葉を持ち出さなくとも、「人望」があれば下はついてきたのだ。
しかしいまはそうじゃない。
自由奔放な部下を御せなけばマネージメント不足と言われ、部下が病んでしまったら加害者になる。
いくら管理職である本人が頑張っても、人材管理の成果は他人に依存するから、他人をコントロールできない以上「がんばれば結果がでる」ものでもない。それでも、管理職としての成果を求められる。
でもド素人に心理カウンセラーの真似事をしろといっても、向き不向きがあるのは当然なわけで。
そう考えると、管理職になるのってやっぱり割に合わないよなぁ~と思う。
管理職にはちゃんと「マネージメント」を学ばせてあげてほしい
なんて言いつつ、わたしもこれまで、さまざまな記事で「しっかりマネージメントしろ」と書いてきた。管理職はマネージメントのプロなんだから、仕事も人間もしっかり管理しろ、と。
でも改めて考えると、「マネージメントのプロ」といえるレベルで人材管理を学んだ管理職って、どれくらいいるんだろう。
管理職に必要な知識を学んでいないのならできなくても当然だよな、とも思う。
いやだって、これまでライターとしてたくさんの記事を書いてきたからって、いきなり「ライター30人をマネージメントしてください」って言われても無理だし。
クライアントとうまくいってないライターの仲裁に入れ、仕事と育児の両立に悩んでいる部下の相談に乗れ、いいチームになるように円滑な人間関係を構築しろ、なんて求められてもさ。やったことないし。
学ぶ機会がないのに成果だけ求めるのは、都合がよすぎるよ。
そんなの、できなくて当然だもの。
「ちゃんと教えないくせにいろいろ要求してくる上司」というのはいつの世でも嫌われる存在だが、「マネージメントを学んでいない管理職にマネージメントで成果を上げろ」っていうのも、同じくらい理不尽だよなぁ。
最近ジョブ型だのリスキリングだの、そういう言葉が流行ってるけどさ。
それなら全国津々浦々、いままで学んだことのない人材管理を突然任され、部下のメンタル状態の責任を負わされて先に本人の胃に穴があきそうな管理職に、もうちょっとちゃんと人材管理を勉強させてあげたほうがいいんじゃないかと思う。
それは人材管理をする管理職本人はもちろん、管理される側である部下にとっても、大事なことだから。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
ネクセラファーマ株式会社 IT & Digital部 ディレクター。外資系・グローバル企業で業務改革とDX推進を担当。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所出身。複数企業でのプロダクト開発を経て現職。生成AI導入支援・開発支援の最前線に立つリーダー。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
名前:雨宮紫苑
91年生まれ、ドイツ在住のフリーライター。小説執筆&
ハロプロとアニメが好きだけど、
著書:『日本人とドイツ人 比べてみたらどっちもどっち』(新潮新書)
ブログ:『雨宮の迷走ニュース』
Twitter:amamiya9901
Photo:Michael Pointner