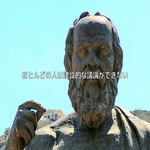議論とは何か。
日本国語大辞典によれば、「互いに、自己の意見を述べ、論じ合うこと。意見を戦わせること。」
と定義されている。
ビジネスにおいては、もう少し拡張してもいいかもしれない。
意見を戦わせる目的は2つある。
一つは
「意見を戦わせることで、どの意見が優れているか(正しいか)、判定すること」
そしてもう一つは
「意見を戦わせることで、よりよい意見を生み出すこと」
この2つを目的とした議論を、「建設的な議論」と呼ぶことにする。
ほとんどの人は建設的な議論ができない
しかし。
私は様々な会社で議論を見聞きしてきたが、「建設的な議論」ができる人はそれほど多くない。
組織内における議論のほとんどは、「自分の地位を上げること」と、「相手を貶めること」に使われてしまうからだ。
議論の目的が「意見」を出したり、質を高めることではなく、人の評判を操作するだけに使われる状況。
これが「不毛な議論」だ。
例えば、こんな具合だ。
まず、A案を支持するベテランの鈴木さんが説明をした。
「A案のメリットは、コストが抑えられる点です。既存のリソースを最大限に活用できるので、予算内で実行可能です。また、導入に必要な時間も短縮できると思います。以上の説明について、なにかご質問、ご意見はございますか?」
他のメンバーがうなずきながら資料を見返す。
気鋭の新人である佐藤さんは、部長も見ているこの場で「目立つ意見」を出さねばと思い、発言した。
「確かにA案はコスト面では有利ですが、予測を見ると、長期的に見た場合の成長性が乏しいと思います。初期コストが高くても、今後の拡張性や市場への影響力を考え、より大きなリターンが期待できる代案を用意すべきではないでしょうか?」
鈴木さんは、部長の手前、このまま生意気な新人に面子を潰されるわけには行かない、と思った。
「佐藤さん、あなたが言うことは分かりますが、現実をもっと見た方がいい。理想論を語るのは簡単ですけど、私たちは成果を出さなければならないんです。リスクを取ることが必要だと言いますが、失敗したらどう責任を取るつもりですか?」
佐藤さんは顔をしかめた。
彼には、ベテランの鈴木さんをやり込めて能力をアピールしたい、という欲求が芽生えていた。何がリスクだ。そうやっていつも、ベテランたちはリスクばかりを強調する。
「鈴木さん、それは分かります。しかし今年の事業計画にも「積極的に市場を取りに行く」とありました。その姿勢が積極的だとは思えません。経営陣にも理解を得られにくいのではないでしょうか。」
何を言うか、オレのほうが役員に顔が利く、と鈴木さんは思った。どうせ代案も大したこと考えてないんだろう、佐藤は。生意気な新人だ、詰めてやれ。
「では、佐藤さんから、経営陣が納得し、より多くのリターンを期待できる代案を代わりに出してもらいたいですが。」
そんなすぐに案なんて出るわけ無いだろう。と佐藤さんは思った。そもそも、求められたから「意見」を出しただけだろうが。
「すいません、そんなにすぐに代案は出せません。ただ、意見を求められたので述べたまでです。」
上のようなやり取りはまさに不毛というほかない。
目的が意見に対するもの、つまり「A案」の効果予測や、更に良い代案の検討ではなく、鈴木さんと佐藤さんの権力闘争になっている。
どうすれば不毛な議論を回避できるか?
上に挙げた、鈴木さんと佐藤さんは、決して良い議論はできない。
なぜか。
根本的な信頼関係がないからだ。
実は、議論というものは、互いの信頼関係がないと、不毛に終わることが多い。
「意見」「反論」「指摘」
などがすべて、「人格攻撃」と捉えられてしまうと、意見の正しさや、より良い案を作ろう、という意欲はどうあっても出てこない。
そのため、議論をする場合は、双方に「議論の技能」が備わっていないと、議論にならない。
その技能とは3つ。
・信頼関係の構築ができること
・意見を「地位」だけで判断しないこと
・相手の言ったことをいったん受け止めること
実際、コンサルティング会社では、基本的に「顧客と議論をしてはならない」と教わっていた。
要は、「不毛な議論は極力、回避しろ」というわけだ。
しかし、中には「わざと政治的な議論をふっかけてくる人」もいる。
例えば、会議中に本筋とは全く関係なく、
「あの管理職の能力についてどう思いますか?」
などと、答えにくいことを聞いてくる。
こういう質問は「要注意」で、我々コンサルタントは「プロジェクトに関係のない意見を表明してはならない」と、きつく上司から言われていた。
外部のコンサルタントに、政治的な意見を言わせ、それを利用したい人も多いからだ。
そんなとき、我々が教わっていた対処の方法があった。
それは、「矛先を他の人にそらしてしまう」やり方だ。
具体的には「そうですね……●●さんはどう思いますか?」と、そこにいる別の人に振ってしまうのだ。
そうすれば、我々が意見を表明することなく、不毛な議論をそらすことができる。
質問によっては、出た意見を順番にホワイトボードに書き留めていき、最後に「その場にいる一番偉い人」に意見を求めて決着させる。
政治や好き嫌いの話をしたい人には、同様の政治権力を使って対処するほうが簡単だ。
「社長はこうおっしゃっていますが、あなたの意見は?」と聞き返すだけで良い。
*
この「政治的な議論をしない」「政治は好きな人同士にやらせておけばいい」
という態度は、とても重要で、時に自分の身を守ることにつながる。
古代ギリシャの哲学者「ソクラテス」は、若者をかどわかした罪で、告発されたとき、告発者のあらゆる「言いがかり」に対して、議論で勝利している。
実際、議論を追いかけると、ソクラテスには何一つ非はなく、告発者の無理筋な主張ばかりが目に付く。
しかし、議論で勝ったにもかかわらず、最後は有罪判決を受け、満場一致で罰金刑ではなく「死罪」となった。
それについて、ソクラテスは次のように言っている。
「とんでもない。私はたしかにある種の不足のために有罪判決を受けましたが、その不足とは言葉の不足ではなく、臆面のなさと、無恥と、皆さんが聞いたら喜ぶようなことを皆さんに対して言う、そういう意思の不足なのです。皆さんが喜ぶのは、私が悲嘆にくれたり、嘆いたり、他にもたくさんの私にふさわしくないこと(私はそう主張します)を私が行ったり、口に出したりすることでしょう。そういうことこそ、皆さんが他の人たちから聞き慣れていることでもありますしね。」
つまり、議論の勝ち負けは、権力や人の好き嫌いに対して、ほぼ無力である。
であれば、そこに力と時間を使う理由は、何一つない。
議論は決して無意味ではないが、それができるのは、信頼関係のある相手だけ。
愚か者、あるいは見知らぬ人とやるような性質のものではないことは、間違いない。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者プロフィール】
安達裕哉
生成AI活用支援のワークワンダースCEO(https://workwonders.jp)|元Deloitteのコンサルタント|オウンドメディア支援のティネクト代表(http://tinect.jp)|著書「頭のいい人が話す前に考えていること」60万部(https://amzn.to/49Tivyi)|
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯note:(生成AI時代の「ライターとマーケティング」の、実践的教科書)
Photo:Felipe Pérez Lamana