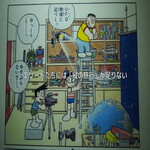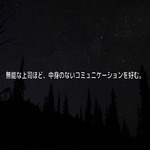先日、アメリカ大統領選挙で民主党のハリス候補が負け、共和党のトランプ候補が勝った頃、インターネットでは「エリートは縦の旅行をしろ」「エリートたちには縦の旅行が足りない」といったメンションを少なからず見かけた。
「縦の旅行」「横の旅行」とは、ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロ氏が言った言葉だ。
「エリートには縦の旅行が足りない」とは、エリートはしばしば世界じゅうを移動するが、どこでも同族のエリート同士・ブルジョワ同士としか交流していない、つまり広く世界を見聞しているつもりでも階級・階層的にはフラットな「横の旅行」しかできておらず、近隣に住んでいる非エリートについてはまったく知らずに済ませている、といった意味になる。
これは本当にそうだと思う。資本主義や個人主義をしっかりと内面化し、ポリティカルコレクトネスにも妥当するエリートは、東京でもニューヨークでもパリでも似たような価値観を持ち、似たような生活環境に暮らし、似たような多様性を奉じている。
彼らの思想信条はおおむねリベラルで、(アメリカ大統領選挙でいうなら)民主党寄りだろう。
しかし、彼らはどこに行っても同族としかつるまない。肌の色や目の色、ジェンダーなどはさまざまかもしれないが、ポリシーやライフスタイルの面では大同小異だ。どれだけ航空会社のマイルが貯まろうとも、それで知ることのできる世界は知れている。
そうした「横の旅行」に終始するエリートたちが、自分たちの視野の狭さを自覚しているならまだいいが、「自分たちは世界じゅうを旅するグローバルな人間で、多様な価値観に触れているコスモポリタンな人間だ」と勘違いしていたら深刻である。
だから「エリートはたちには縦の旅行が足りない」というメンションは事実の認識としてはそうだろうなと思う。
昔は「縦の旅行」などするまでもなかった
では、どうすれば「縦の旅行」が成立するのか?
それって、「さまざまな階級や階層の者同士でコミュニケーションせよ」というわけだが、これは今、どこでどれだけ可能だろうか?
そもそも昭和時代後半の日本においては、「縦の旅行」は意識するまでもなく成立可能だった。
そのことを象徴しているのは『ドラえもん』の主要キャラクターたちである。庶民的なサラリーマンの家の子であるのび太、小売業の家の子のジャイアン、金持ちの家の子のスネ夫がいた。しずかちゃんや出木杉君はプチブルジョワの家の子だろうか。
『ちびまる子ちゃん』の描写もそれに近い。花輪くんや城ケ崎さんのような子がいて、たまちゃんや丸尾くんのような子もいて、まる子や永沢くんのような子もいて、教室は多様だった。
これらは子供向け漫画だが、それだけに、昭和時代後半の公立校の描写としては最大公約数的だった。さまざまな家庭のさまざまな子が学校や遊び場で出会うものだった。
当時言われていた“一億総中流”という言葉のうちには、こうした「縦の旅行」をするまでもない学校環境、ひいては地域共同体があったことを思い出しておいてもいいように思う。
ところが事態が変わっていく。
東京を中心に、いつしか中学受験なるものが流行するようになり、やがて、小学受験さえ意識されるようになった。
エリートの子弟が早い段階から受験に流れれば流れるほど、有名受験校にエリートが集中し、公立校からはエリートがいなくなる。
エリートたちが子弟を幼少期から受験させればさせるほど、『ドラえもん』や『ちびまる子ちゃん』のような社会環境、社会関係は体験できなくなってしまう。
はじめにスネ夫や花輪くんが有名受験校に進学して公立校からいなくなり、やがて、しずかちゃんやたまちゃんも公立校からいなくなってしまうだろう。
と同時に、公立校を去った子どもたちはジャイアンやのび太やまる子のような子と知り合う機会を失い、ブルジョワ的~プチブルジョワ的な価値観の子と知り合う機会ばかり増大する。
それは、ある面では付き合いやすいことかもしれないし、コネクションを作るという観点からみても望ましいかもしれない。そのかわり、異なる階級、異なるライフスタイル、異なる価値観の同世代に触れる機会はなくなってしまう。
階級社会がきわまっている国々では、エリートと庶民は通う学校やライフスタイルが違うだけでなく、読む新聞、楽しむ娯楽、話す言葉すら違うといわれる。
しかし戦後からそう遠くない時期の日本ではそうではなかった。歴史的にみれば例外的状況だったかもしれないが、ともあれ「縦の旅行」を熱心に説く必然性は乏しかった。なぜなら学校に通い、多様なクラスメートと付き合っていれば、自動的に「縦の旅行」に近似したことが起こったからだ。
のみならず、地域共同体も「縦の旅行」を後押しした。古い街だけがそうだったのではなく、ニュータウンでも同様である。
原武史『団地の空間政治学』によれば、団地やニュータウンがプライベート化し、核家族に引きこもっていくのは70年代以降である(その頃から、プライベート化した生活空間を前提とする“団地妻”というジャンルが人気になった、ともいわれている)。
地域共同体は大人になってからも人と人とを結び付け、「縦の旅行」を自動的に提供……というより押し付けていた。
だから、「縦の旅行」論が日本でも説得力を持つようになったのは、エリートの子弟がそうでない子弟が学校で交わらないようになったため、地域の付き合いが希薄化しプライベート化したためでもある。
今日では、土地の値段による選別も意識されてしかるべきだろう。たとえば東京都心ではエリートの子息が集まる公立校があったりする。土地の値段が高すぎて、庶民がどう頑張っても住めないエリアができあがってしまっているからだ。
「縦の旅行」の谷底も深くなってないか?
もうひとつ、問題だなと思うのは「縦の旅行をしろ」と言ったとしても、階級・階層・ライフスタイルなりの縦の広がりって、果てしなく広がってないか? というものだ。
エリートのなかのエリート、縦の旅行の上方を垣間見ることについては置いておく。戦後に緩和されたとはいえ、全容のみえない上流家庭はいつの時代にも存在したものだ。では、縦の旅行の下方についてはどうだろう。
“一億総中流”の時代において、庶民の暮らしは比較的同質的だった。電化製品の普及、マイカーやマイホームを持つこと、といった次元では世帯間の差異は比較的見えにくく、大半の人が経済的・技術的発展の恩恵に浴していると感じていた。
その“一億総中流”が意識の問題でしかなく、実際には格差が存在し、その格差が世代を経るにつれて蓄積していたのはいうまでもない。さきほど触れた、有名受験校へのエリートの集中なども、そうした格差蓄積のあらわれの一つと数えられるだろう。
格差蓄積は平成時代に進行し、やがて顕在化し、今日では広く知られるに至っている。しかし富裕層がどこまでも上昇していくのと軌を一にして、貧困層はどこまでも下降していったのではないか? もし、その最底辺の領域まで「縦の旅行」をしろと言われても、エリートはもちろん、ほとんどの非エリートですら知り得ない領域が、あったりするのではないだろうか。
昨今、「闇バイト」や「ホワイト案件」といった俗語とともに、「あんな危うい仕事を請け負うのはいったいどんな人間なんだ」といった言説が流通している。しかし、実際にはそうした人間は存在している。
経済的にも、文化的にも、精神的にも貧困をきわめた人々は、危うい仕事に対してストップをかけることが困難だったりする。
あるいはSNS上のフェイクやオンライン課金の罠に簡単に取り込まれたりする。現代社会に張り巡らされた罠という罠に引っかかり、地雷という地雷を踏み抜いてしまう人々。そうした人々のなかには、エリートはもちろん、非エリートの大多数とも隔絶した状況を生きている人が珍しくない。
しかし、そこもまた世間の一部、世界の一部であることは否定できない。上も下も、世界は縦に伸びきっている。
SNSは「縦の旅行」を可能にしない
こう書くと、「SNSが上下の見晴らしを提供してくれる」と反論する人がいるかもしれない。でも私はSNSには期待できない、と感じている。なぜならSNSは声の大きな人の声の大きなメンションがこだまする空間だからだ。
たとえばSNSにはリッチでゴージャスな生活をしている人のメンションらしきものが目に飛び込んでくる。
だが、そこにはフェイクが溢れていて、到底あてにできる情報源とは思えない。たとえ本物の富裕層のメンションが混じっている場合でも、メンションはいつもSNSに投稿するのに適したかたちで整形・編集されている。
これはエリート全般についても言えることで、エリートの大半にはSNSで手の内を曝すインセンティブがない。
インセンティブがあり、手の内を曝すのが得意なエリートもいるだろうが、それは少数派で、なおかつ整形・編集されたメンションの得意なエリートだろう。
そのことを念頭に置けば、SNSごしに見かけるエリートの姿は相当に偏っていると考えざるを得ない。しかも、エリートを詐称する偽物も混じっている。
困窮のきわみにある人についても、おそらくそうだ。困窮のきわみにある人のほとんど全員はSNSを通して自己主張する能力と意志を持ち合わせていない、もの言わぬ民(サバルタン)である。
もし、SNSで多くのフォロワー数を抱えている困窮者を見かけたら、それは貧困層としては例外的存在とみるべきで、そうした言語化能力・プレゼンテーション能力のない貧困層はSNSでは文字通り不可視である。
SNSも含めたメディアは、情報発信者をとおしてしか情報が伝わらないため、発信する側・メンションする側の能力や意図によって伝えられるものが偏る。その性質は、エリートのエリート像を歪ませると同時に、物言えぬ人々の像をも歪ませる。
だからSNSを通して私たちが目にするものは、エリートを称するものであれ、困窮者を称するものであれ、「声をあげる意志と能力と動機を持った者のメンションでしかない」と心得ておく必要がある。それらは事実という氷山の一角でしかなく、フェイクや誇張と区別するのはとても難しくもある。
まとめ
こうして振り返ると、「縦の旅行」は難しい、と言わざるを得ない。難しいことと必要か否かは別問題で、難しくてもエリートは縦の旅行をすべき、いやエリート以外も見識を広げるべきと主張するのは間違っていないだろう。
しかし学校生活の分裂や地域共同体の消失、格差拡大などから「縦の旅行」の難易度は高くなっていて、エリートはエリート同士でつるんだほうが気楽かつコネクションに開かれていると想定される。
そしてSNSは声の大きな人間の声だけを目立たせ、声なき人の声を拾い上げはしない、そもそもSNSに流れる情報の真贋については、私にはまったくわからない。
世間全体、社会全体が今どうなっているのかを知るヒントになるのは、統計的なデータになるが、その統計的なデータも、しばしば集計方法が変わったりするので単純な読み取りを許してはくれない。なにより、統計的なデータは人間の顔つきをしていないのである。
「縦の旅行をしろ」というのはもっともだが、そもそも私たちは今、縦も横も前も後ろも右も左も自分自身をも見失っているのではないか? というのが昨今の私の所感である。あなたはどうですか?
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【プロフィール】
著者:熊代亨
精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。
通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(イースト・プレス)など。
twitter:@twit_shirokuma
ブログ:『シロクマの屑籠』

Photo:othree