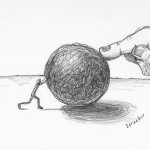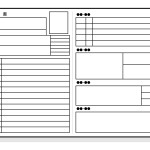生成AIの仕事をしていると、「DXの一環ですね」という言葉をいただくことがある。
私は、なるほど、そうかもしれませんね、とその時にはうなづくのだが、実はあまりよくわかっていない。
「DX」、つまりデジタルトランスフォーメーションの定義を詳しく知らなかったからだ。
ところがつい先日、繰り返し「DX」の話題が、生成AIのプロジェクトの途上で持ち上がった。
そこで改めて調べてみると、一つの面白いジャンルを築いていることが分かった。
今回はそれについて、拙い理解を書いてみたい。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは何か?
DXとは、今から20年前の2004年。
エリック・ストルターマン氏によって提唱された概念で、「ICTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」とされている。(総務省)
なるほど。
わかったようなわからないような定義だ。
結局、だから何なんだ、「デジタル化」と何が違うんだ、という話になる。
ただ、これは総務省が解説を加えている。
言い換えると、会社内の特定の工程における効率化のためにデジタルツールを導入するのが「デジタイゼーション」、自社内だけでなく外部環境やビジネス戦略も含めたプロセス全体をデジタル化するのが「デジタライゼーション」である。
それに対し、デジタル・トランスフォーメーションは、デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネスモデルの開発を通して、社会制度や組織文化なども変革していくような取組を指す概念である
ポイントは「新しい商品/サービス・ビジネスモデル」を生み出す、というところだろうか。
要は、
デジタル技術を使って、新しい商売立ち上げようぜ!
という話なのだと、私は理解した。それがDX。
これならば、理解はたやすい。
GoogleやAmazonのような会社を創れってこと?
しかし、そうなると実践はかなり、ハードルが上がってくる。
つまり、DXとは、結局のところ、GoogleやAmazonのような会社を創れ、という話なのではないか。
総務省のページにも、以下のような話があり、大変だな……という気分になる。
社会の根本的な変化に対して、既成概念の破壊を伴いながら新たな価値を創出するための改革がデジタル・トランスフォーメーションである。
したがって、あらゆる会社に「DXを推進せよ」というのは、あまりにも無理筋だという事になり
「ちょっと……ウチは勘弁」
と思う会社も多いのではないだろうかと推測する。
それについて、世間はどのような解釈をしているのだろうか、ちょっと書籍をあたってみた。
上の本では、どちらかといえば、総務省の言う「デジタル化」の部分を推している。
ペーパーレスや、小さく速い成功をめざせ、といった論調だ。
これなら中小企業もある程度取り組めるだろうが、「DX」と呼んでよいかは疑問が残る。
東大の先生が書き、コンサルタントの冨山和彦氏が解説をする以下の本では、「日本経済復活」を掲げている。
ただ、結局言わんとしているところは、「サービスを抽象化して、大きく広げるという思考を持て」。
デジタルサービスの作り方の教本、といった具合。
また、マッキンゼーが書いた本は、「企業文化変革」に焦点を当てて、単なるシステムの刷新やIT化に対して批判的な論を展開している。
そのため、後半では「DXの推進手順」が示されているが、まあこれは「だからマッキンゼーを雇いなさい」というPRだろう。
経産省の「DXレポート」
と、まあいろいろな人が、これを商売のネタにすべく、様々なことを言っている。
これが、DXという分野だという事はよくわかった。
そして、コンサルティング会社がDXというネタで儲かる、という図式があることも良く分かった。
しかし、これで終わらせてしまってはまとまりがない。
DXというテーマで、もう少し突っ込んだ、「結論」はないのか。
そう思うと、結局、経済産業省が作った「DXレポート」というドキュメントに行き当たる。(経済産業省)
読んでみると、DXレポートの趣旨はシンプルだ。
日本でDXを推進できなければ、2025年から2030年までに、最大年間12兆円の損失が生じる、というものだ。
そして、レポートはその原因を「レガシーシステム」の存在に見出している。
レガシーシステムの存在によって起きる損失は、貴重なIT人材の浪費であり、DXの足かせでもあり、新しいIT投資を抑制する元凶でもある。
だが、8割の企業は、いまもなおレガシーシステムに依存している。
その理由は「ユーザ企業」と「ベンダー企業」の低位安定だという。
●既存産業の業界構造は、ユーザー企業は委託による「コストの削減」を、ベンダー企業は受託による「低リスク・長期安定ビジネスの享受」というWin-Winの関係にも見える。
●しかし、両者はデジタル時代において必要な能力を獲得できず、デジタル競争を勝ち抜いていくことが困難な「低位安定」の関係に固定されてしまっている。
DXレポートでは、「ユーザ企業」も「ベンダー企業」も、デジタル時代にリスクを取らず、必要な能力を獲得できないまま、少しずつ沈んでいく。
そうしたある意味では癒着した構造が問題だと指摘されている。
なるほど。
つまり、ユーザ企業がベンダーにシステムを外注し、あくまで
「コスト削減のためのIT化」
「オペレーションのためのIT化」
から脱却できていない状態を何とかするのがDX、という事のようだ。
DXは日本のシステム開発業界の構造の問題をなんとかしよう、という動きだったのだ。
「DX」は本当に必要か
であるから、どの書籍を見ても、政府のレポートを見ても、日本企業はDXについて、散々ダメだしされている状況である。
そうかもしれない。
デジタル分野で米国や中国などに大きく後れを取った結果、日本企業はすっかり世界の中での存在感を失ってしまったのは事実だ。
現在、世界の時価総額ランキングにおいて、50位までに日本企業はトヨタが45位にいるだけ。
代わりに存在しているのは、アメリカ、台湾、中国、韓国、ドイツ、オランダ、スイスなどのデジタル事業を主とする企業だ。
これがいかに、危機的な状況であるかは、いくら私でもわかる。
そして、これからのビジネスは、デジタル抜きにはありえない。
だからDXなどという名前を付けるかどうかに関わらず、議論の余地なく、DXは必要だという判断になるのだろう。
野心を持った、社内外の起業家によってDXは成し遂げられる
ではどうするか。
DXレポートでは、デジタル産業指標の策定や、DXの成功パターンの策定などを目論んでいるようだが、まあ、それだけでは大したことはできないだろう。
結局、DXの目的である、デジタル事業創出は、起業家精神によってのみ、成し遂げられることだからだ。
したがって、野心を持った、多くの起業家が育つ土壌が必要である。
ごまかさずに言えば、「DX人材」とは、デジタルに詳しい人材ではなく、社内外の起業家の事だ。
無論、これはスタートアップに限らない。
大企業の内部でも、中小企業においても、DXのできる起業家、つまりDX人材を育てていく必要がある。
だが最近、少しずつではあるが、「DX人材」にお金を使っていこうという風潮が、大企業を中心に生まれているように感じる。
日本が沈み切ってしまう前に、何とか世界で戦える企業が生まれてくれれば、と思う。
そして、「まだ日本は捨てたものではない」と皆が思うようになった時、初めてDXは実現したことになるのだろう。
2030年に間に合えばよいが。
【著者プロフィール】
安達裕哉
生成AI活用支援のワークワンダースCEO(https://workwonders.jp)|元Deloitteのコンサルタント|オウンドメディア支援のティネクト代表(http://tinect.jp)|著書「頭のいい人が話す前に考えていること」65万部(https://amzn.to/49Tivyi)|
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯note:(生成AI時代の「ライターとマーケティング」の、実践的教科書)
Photo:Pedro Gabriel Miziara