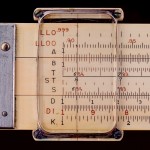「私たちはどう年を取るのが望ましいか?」
いつの時代にもこうした問いはあっただろうし、私もずっと問い続けている。
これからの世の中、どう年を取っていけばいいのかわかった気がしない。
そうしたなか、最近、気になる本に出会った。それを紹介しながら、高度な資本主義と高度な高齢化社会の組み合わせについて書いてみる。
100年時代の人生戦略を語った『ライフシフト』
まず、本を紹介しよう。
今回出会った本はリンダ・グラットン/アンドリュー・スコットという二人のロンドンビジネススクール教授が著した『LIFE SHIFT 100年時代の人生戦略』という本だ。
本書はまず、従来までのエイジングを教育のステージ・仕事のステージ・引退のステージの3ステージ構成とみなし、それが時代遅れになっていると指摘する。
確かに。寿命が延びて就労期間も延びたのだから、若い頃に教育を受けたきり何も学ばなければ、働き口は狭くなり、給料も安くなっていくだろう。
本書はそのような境地を「オンディーヌの呪い」と呼び、避けたいものとみなす。
既存の3ステージの人生のモデルのまま、寿命が長くなれば、私たちを待っているのは「オンディーヌの呪い」だろう。永遠に動き続ける運命を背負わされたパレモンと同じように、私たちはそれこそ永遠に働き続けなくてはならなくなる。どんなに疲れ切っていても、立ち止まれば生きていけないのだから。人生は不快で残酷で短いという、17世紀の政治思想家トーマス・ホッブズの言葉は有名だ。これよりひどい人生は一つしかない。不快で残酷で長い人生である。それは厄災以外の何物でもない。休む間もなく働き続け、退屈な日々を過ごし、エネルギーを消耗し、機会を生かせず、そして最後には貧困と後悔の老後が待っているのだ。
こう警告したうえで、「しかし、長寿を厄災にしない方法はある」と読者に向かってささやきかけるわけである。
うんうん、じゃあ、新しい時代のライフモデルを教えていただこうじゃないですか、と私は胸を高鳴らせてページをめくった。
……なるほど。
確かにこれは正解かもしれない──ただし、その正解をやってのけられるならの話だが。
『ライフシフト』の著者たちは、学び続けていくこと・変わり続けていくことを読者に薦める。若い読者層には人生の重要な決定を先送りし、シェアエコノミーに乗れるところは乗っておいて、たとえばマイホームの購入や子育ては延ばせるなら延ばすよう薦めてもいる。
流動性が高く、必要なスキルも雇用情勢もどんどん変わっていく現代社会に追従するうえで、それは巧い社会適応の方法であるように……思える。
こうした変わり続けていくスタンスは思春期に限定されるものではない。
中年期以降も職を変え、キャリアを磨き、転居も厭わず、それらの必然としてアイデンティティをも変えていくことを本書は薦めている。
こうした変更にはリスクが伴うから、慎重な見極めが必要である、とも付記される。
またキャリアを磨くといっても、年収を増やす、そればかり意識するべきではない。
今日日の人生は長いのだから、たとえば40代の年収を最大化することに拘泥する人は、それ以降の人生を衰えさせてしまうかもしれない。
そこで、狭い意味の資産だけでなく、さまざまな無形資産に目配りすることを本書は薦める。
無形資産として挙げられているものには、
1.生産性資産:スキルや知識、評判など、直接収入に関わるリソース
2.活力資産:肉体的健康や精神的健康、心理的幸福など、活動を維持するリソース
3.変身資産:流動性の高まった社会のなかで、人間関係や職場などを変えければならない、そういった新しいことをスタートしなければならない時にやってのける意志や能力
が挙げられ、これら1.2.3.を意識しながら、長く働ける立ち回りが求められる。
いやまったく。
これらをやってのけられる人は確かに生き延びられるのだろう。そして70代や80代になってもいきいきとした、やりがいのある、それでいて経済的収入の面でもバランスのとれた退屈しない日々が実現できるのかもしれない。
アイデンティティを宙ぶらりんにしたまま生きるのは難しい
だが、こんな人生をいったい何人がやってのけられるのだろう?
こういうライフスタイルを生ききれる人間が最強なのは間違いとしても、これが簡単じゃないから難しいよねって話じゃなかっただろうか?
流動性が高まり、テクノロジーが日進月歩の社会では、アイデンティティを固定化せず、思春期がずっと続くかのようにフレキシブルな人間が望ましい──こういう話は今になって出てきたわけではない。
アメリカの精神科医であるロバート・リフトンが記した『誰が生き残るか──プロテウス的人間』には、まさにフレキシビリティが高いままの人間が将来の社会では有利になる、といったことが書かれている。
1969年に記された本だが、その内容は『ライフシフト』にも似ており、時代を先回りしていたと言えるだろう。
だが、人間のアイデンティティは、そう簡単に変化させられるものではない。
さきほど無形資産のリストのなかに変身資産という項目があった。
人間関係や住まいや仕事の変更にはストレスを伴うことがあるし、相性が合わないリスクだってある。
だからこそ、それを容易にする変身資産なる特質が期待されるのはわかるのだけど、アイデンティティのとっかえひっかえは結構な負担になる。
慣れた仕事・慣れた人間関係・慣れた住まいにはアイデンティティが伴い、アイデンティティは人間の心理的な安定性や満足感にも影響を及ぼす。
自分が何者かになった手ごたえ、自分ってこういう人間だよねという自分自身の心理的な輪郭、そういったものを成り立たせる構成要素になってくれる。
ところが仕事も人間関係も住まいもコロコロと変えてしまうと、それらがアイデンティティとして定まらなくなり、自分の構成要素として体感されなくなる。
自分がどういう人間なのかを規定する要素、自分自身の心理的な輪郭を構成するものがあやふやになってしまう。
この点において、長く続く思春期も良いことづくめではない。
アイデンティティが浮動的であればフレキシビリティが高い反面、そうである限り、自分自身の輪郭はあやふやなままで、心理的な安定性をアイデンティティから充当しづらい状態が続いてしまう。
長すぎる思春期を過ごした人、自分とは何者かについて考え、苦しんだことのある人なら、このアイデンティティの根無し草的境遇がしんどいこと、先の無形資産の話でいうなら活力資産を脅かすほどの問題であることが直感できるだろう。
そういう風に悩まない人間こそが変身資産の高い人間だと言われてしまえばそれまでだが、実際には、そういう風に悩まない人間ばかりではない。
他方、現代のエリートにそうしたライフスタイルとアイデンティティのあり方が期待されていて、エリートならできなきゃいけない一面はわからなくもない。
同じくイギリスの社会学者であるアンソニー・ギデンズは、『モダニティと自己アイデンティティ──後期近代における自己と社会』のなかで、やはり、フレキシビリティの高い、従来までのアイデンティティのあり方とは異なった人間像を提唱している。
ギデンズは社会学者だから、そうした人間像を社会情勢を踏まえながら解説していく。
その人間像やアイデンティティのあり方は『ライフシフト』のものに似ているし、実際、本書のなかでギデンズは何度か引用されてもいる。
そうしたわけで、現代社会において『ライフシフト』に書いてあるとおりに生きられたらうまくいく、ということ自体はたぶん間違ってないし、だいぶ昔から言われていたことなのだ。
だが実際には、人間にとってアイデンティティを浮動的であり続けさせるのは難しく、へたをすれば活力資産に影をおとしてしまうかもしれない──。
何者にもなれるとは、何者でもないということでもある。
その苦しみを苦しみとも感じない人間がこれから勝者になる……というのは理解できるが、万人がそうなれるとは考えづらい。
もしなれるようなら、今頃、ロバート・リフトンは神のように扱われているだろう。
そもそも、キャリアってそんなにうまく転がるものなのか
それともうひとつ。
そうやって自己判断でキャリア転がしをやっていって、いったいどれだけの人が望みどおりのキャリアと年収を獲得し、無形資産をメンテナンスし続けられるものだろうか?
『ライフシフト』には、世代別に幾つかのモデルが例示されているが、どのモデルも転職のたび年収が上がったり、首尾よく新しいスキルを獲得したりしている。人生の危機も記されるが、かわしているほうだと言えるだろう。
うつ病などの精神疾患に罹患し、休職するモデルは登場しない。全体としては、勝っている時の『人生ゲーム』の賽の目のようだ。
もちろんそういう人生もあるし、それが正解だと言われてしまえばにべもない。
くだんのアンソニー・ギデンズはイギリスの新自由主義的政策にも参与していて、本書においても、個々人が事業主となって働くことが(ギグエコノミーなどを例示しながら)肯定的に記されているから、なにごとも自己判断で(そして一言も書かれていないが自己責任で)人生の賽の目を振り、勝っていかなければならないのがイギリス社会なのだろう。
だからこそ、賽の目を振るに際して無形資産というバックボーンを大切にすべきである、と。
そう理解してもなお、私には、本書で例示されていた人生のキャリア転がしが成功裏に描かれ過ぎているようにみえ、誇大妄想とまでは言わないまでも、難しいだろうなと思った。
イギリスのジャーナリストであるオーウェン・ジョーンズは、著書『チャヴ』や『エスタブリッシュメント』のなかで、ひとりひとりが起業的マインドセットを持たなければならないイギリス社会の現状を厳しく批判している。
この、オーウェンという人の書籍は論敵をやりこめる調子が強すぎて好きになれないのだが、新自由主義に染まったイギリス社会のなかで、経済資産にも無形資産にも恵まれない者までもが起業家的マインドセットを内面化して生きていかなければならず、その社会風潮に乗れない人間がクズ扱いされる現状を告発する筆致には迫力があった。
『ライフシフト』は、そうした社会風潮のなかで成功裏に生きる者には説得力のある本である。
しかし、成功裏に生きられなかった者にはなんの慰めにも、なんのロールモデルにもならないのではないだろうか?
昔はそれでも良かったのかもしれない。
すなわち、『ライフシフト』に記されるライフスタイルを期待されるのがエリートだけで、エリートのなり損ないだけがアイデンティティを浮動的に取り扱いきれず、ときどき文学作品を生み出したりしながら苦しんでいる──そんな社会状況だったら、エリートだけが本書を読んでいれば良かったのだろう。
しかし労働者階級までが(それこそギグエコノミー的なかたちで)起業家的マインドセットを持たなければならない社会において、これはむごいのではないだろうか。
無形資産にも経済資産にも恵まれた子息が100年時代の人生戦略を薦められるのと、無形資産にも経済資産にも恵まれない子息が同じものを薦められるのでは、うまくやっていける確率はかなり違うだろう。
いちおう本書も格差や政府による再分配に言及はしているが、本気度が感じられるものではない。
あるいはイギリス社会では、本書のような本は今でもエリートしか手に取らないのかもしれず、たいして問題にならないのかもしれない。
だが日本はそうではない。実家ガチャなどが取り沙汰されるなかで『ライフシフト』が読まれていくのだろう。
それにしてもだ。
どうあれ本書のように生きてゆくほかなく、さもなくば、不快で残酷で長い人生が待っているとしたら、大半の人において、不快で残酷で長い人生が待っていそうである。
生きがいのある、退屈ではない長寿を人々が求めるのは理解できる。当然だろう。
だがそうでない長寿が巷に溢れ、不快で残酷で長い人生に陥る確率がすごく高い状況が当然とみなされ、そのような高齢者が過半数を占める社会になっていくとしたら、それは個々人のライフスタイルの間違いである以上に、社会が間違っている、と私たちは言わなければならないのではないだろうか。
社会が間違っている、だなんて言っても仕方のないことではある。
それに比べれば、自分が間違っている・自分は敗北者だと認めるのはたやすい。あの人が間違っている・あの人は敗北者だと指さすのはもっとたやすい。
そうやって自他を間違っている・敗北者だとみなす人間が増えたほうが為政者には都合良かろう。
だけど、そうやって庶民にまで起業家的マインドセットで競争をさせておき、それが当然だと思いこませて、たくさんの敗者に不快で残酷で長い人生を自己責任的だと思わせているとしたら、せっかく実現した長寿も含め、なにかとてつもない間違いがあるはずで、きっと本書の筆者やアンソニー・ギデンズほどの俊英ならそこのところ本当はわかっているのではないだろうか。
『ライフシフト』は、グローバル資本主義社会でおおむね勝ち続ける人には文句なしで推薦できる本だ。
では、勝てなかった人やエリートから遠い人はこれからどう年を取っていけばいいのかは……結局わからなかった。
かといって、途中で人生を棄権する権利や手続きを認めればいいのかといったら、これもわからないし拙速に決めて良いものでもないだろう。
イギリス社会に限らず、結局人類は、ほとんどの人が長寿という新しい状況を持て余してしまっているのだろう。そういう読後感の残る本だった。
AUTOMAGICは、webブラウザ上で商品情報を入力するだけで、
・ターゲット分析
・キャッチコピー
・ネーミング
・キャンペーン企画案
・商品紹介LPの文章
を自動で出力します。
登録すると月間40,000トークン(約2記事程度)までは無料でご利用できます。
↓
無料登録は こちら(AUTOMAGICサイト)へ
詳しい説明や資料が欲しい方は下記フォームからお問合わせください。
↓
AUTOMAGIC お問合せ・資料ダウンロードフォーム

【プロフィール】
著者:熊代亨
精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。
通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(イースト・プレス)など。
twitter:@twit_shirokuma
ブログ:『シロクマの屑籠』

Photo by Girl with red hat