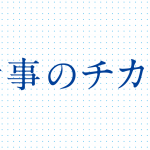チャレンジする風土を会社に創りだす時、もっとも重要な考え方は何か?と聞かれれば、迷わずそれを挙げることができる。すなわち、「人は優れているほど多くの間違いをする」という考え方だ。
チャレンジする風土を会社に創りだす時、もっとも重要な考え方は何か?と聞かれれば、迷わずそれを挙げることができる。すなわち、「人は優れているほど多くの間違いをする」という考え方だ。
これはピーター・ドラッカーが著書※1の中で述べた言葉である。彼はこう述べている。
成果とは長期のものである。すなわち、まちがいや失敗をしない者を信用してはならないということである。
それは、見せかけか、無難なこと、下らないことにしか手をつけない者である。成果とは打率である。弱みがないことを評価してはならない。
そのようなことでは、意欲を失わせ、士気を損なう。人は、優れているほど多くのまちがいをおかす。
優れているほど新しいことを試みる
チャレンジと失敗をたくさんしている人間こそ、最も評価すべき人間であり、上司が部下に「こうあるべき」と指導すべき姿だ。
しかし、仕事の中での「チャレンジ」とは一体何なのだろうか。一言で言えば、「野心的な目標を立て、それを達成すべく動くこと」としてよい。
逆に言えば、「できそうなこと」をうまくやったとしても、それはチャレンジとはいえない。
さて人事評価の季節になると、「部下がチャレンジしない」という嘆きを経営者や管理職の方から数多く聞く。このような会社であっても「チャレンジする風土」を創り出せるのだろうか。
順を追って実行すれば恐らく可能だ。 この場合、原因として考えられるのは
・部下がチャレンジすると損をすると考えている
成果が出なければ評価が下がる、という場合には、当たり前だがチャレンジしない人が増える。
本質的には成果が出るかどうかは「打率」である、従って評価は成果の有無に関わらず、その内容によって行われなければならない。
個人的な話だが、私は昔「目標は未達成だったが昇進させてもらった」経験がある。それは、活動の中身を評価されての事だった。それ以来、私は会社を信用し、野心的な目標を立てることを恐れなくなった。
・上司がチャレンジさせていない
上司はほぼ「成果」のみで評価される。幹部の宿命である。だから、部下に
「やれそうなこと」
「できそうなこと」
をやらせたほうが、成果の見通しがつきやすく、リスクヘッジできると考えている。そのような場合、チャレンジしている人間が部下にいない、ということはよくある。
それは部下が悪いのではない。上司が保身を図っているだけである。
では、何をすれば上の2つを解決できるのだろうか。
分析すると、多くの「チャレンジしない会社」は次のように回っている。
1.上司と部下で目標を設定(多くの場合、上司がチャレンジ目標を設定)
【条件】
・失敗してはならない(必達目標)
・会社の予算に合わせる
2.具体的な施策、作戦は部下に丸投げし、考えさせる
という状態になっている。これは全くの間違いである。これは逆にしなければならない。
つまり、
1.部下がチャレンジ目標を設定
【条件】
・失敗してもよい
・野心的でなければならない
2.具体的な施策、作戦は上司と部下で考える。
上のパターンは、部下は「やらされ感」しかない。また、部下の力量を超える目標は達成できない。だが、下のパターンは異なる。部下が設定した目標を上司が助ける義務があるからだ。
しかも、これであれば上司は部下がどの程度のチャレンジをしているか、肌で感じることができる上、知恵を出し合うことで連帯感が生まれる。
ポイントは、上司は「補佐」に徹することだ。あくまでも仕事のの主役は部下だ。
・部下が自らで野心的な目標を立てることを推奨し、
・部下が自らでそれを達成できるように知恵を貸し、
・部下が何かを達成して自信を持つよう仕向ける。
それが上司の役割だ。
上の3つが遂行されているのが、「チャレンジする風土」を持つ会社だ。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
・筆者Facebookアカウント https://www.facebook.com/yuya.adachi.58 (フォローしていただければ、最新の記事をタイムラインにお届けします))
・筆者Twitterアカウントhttps://twitter.com/Books_Apps
・大学・研究の楽しさを伝える、【大学探訪記】をはじめました。
【大学探訪記 Vol.21】人間は、なぜ1種しか地球上に存在しないのか?という疑問に迫る。
【大学探訪記 Vol.20】地球に隕石が飛んできているからそれ調べてるんですけど何か?
【大学探訪記 Vol.19】伊勢神宮のネットワークを駆使し、地域おこしを実現する。
・仕事の楽しさを伝える、【仕事のチカラ】をはじめました。
【仕事のチカラ Vol.7】月間170万PVのオウンドメディアを1年で作り上げた人はどんな人?
【仕事のチカラ Vol.6】27歳にして3社を渡り歩き、起業した人の話。
【仕事のチカラ Vol.5】データサイエンティストって、どんな人?どうやったらなれるの? という疑問に答えてもらいました。
・ブログが本になりました。
※1マネジメント (ダイヤモンド社)