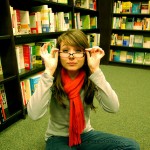話題作であるララランドをみてきた。
率直に言って、これはかなりとっつきにくい作品だ。正直作りは相当にマニアックだと思うし、これが一般向けにヒットしているってのはちょっと驚きである。
実際、あの映画をみても全然よくわからなかったって人も多いと思うので、今回はあの映画が何を描きたかったのかについて書いていこうかと思う。
古典は古臭くて見る気がおきない・・・を覆す
ララランドはミュージカルとジャズというちょっと古い娯楽を題材とした作品だ。これらは昔の娯楽が少なかった頃は、一大ジャンルとして成功していたが、現代ではどちらかというと好事家が好むタイプの娯楽である。
僕たちはちょっと古くさい娯楽を楽しむのが苦手だ。
ゲームだって今更ファミコンをやろうと思うような人はかなり少数派だろう。選べるのならばみんな、ニンテンドースイッチのゲームで遊ぶ。ファミコンのゲームに最新のゲームにない素晴らしいエッセンスがいくらあろうとも、それをわざわざ読み解きにいこうと思うような人はほぼ皆無といっても間違いではない。
本作で出て来るミュージカルとジャズもこの状況と非常に酷似している。
どちらも素晴らしい文化であり、そこには素晴らしいエッセンスが沢山詰まっている。だけど僕たちはそんなものには見向きもしない。というか何がいいのかよくわからないのだ。
けど、この映画を最後まで見切ると、その素晴らしさがどういうものかがちょっとだけわかるようになる。以下映画の構図を書きながらその事を追って説明しよう。
ララランドの構図
本作の男性主人公は、古き良きアメリカをこよなく愛するタイプの人間だ。こんな時代に古臭いアメ車に乗ってる。そしていまは死につつあるジャズという音楽をこよなく愛している。
彼は世間一般での成功よりも、自分をキチンと理解してくれるただ1人の女声の為に生きるのを選択するようなタイプの人間だ。
一方女性主人公の方はというと、男主人公とは結構対称的な存在だ。世界的な娯楽としてのし上がったハリウッドで働く事を夢としているし、乗ってる車はプリウスである。
男性主人公と比較して、アメリカという文化への執着はそこまで強くない。ただ本物を見る目を備えており、劇中で男主人公がレストランで弾いたジャズミュージックの素晴らしさを、ただ1人だけ見出すというキレイな感性の持ち主である。
気がついた人もいるかもしれないけど、男主人公はトランプ大統領が保護しようとしている”古き良きアメリカ人”を象徴している。
これに対して、女主人公はシリコンバレーやウォール街、ハリウッドといったグローバル的に成功した現在のアメリカを牽引している“アメリカの本当の上位層”を象徴している。
結局最終的に男主人公と女主人公はくっつかなかったのだけど、これはちょっと前まではこれら新旧2つのアメリカ人は、ほどよくよき隣人同士として上手く付き合えてきたけど、これからはお互いを尊重しつつ別々の道を歩むようになるのかもしれないという今後のアメリカの未来を描いているのかもしれない。
なんでジャズとミュージカルなのか
本作がたびたび劇中にジャズとミュージカルを入れるのは、これらが本当に凄くいいものを持っていると作品監督が心の底から思っており、それを何とかして人に説明したかったからだろう(構図的にはハリウッドや現代音楽がニンテンドースイッチに相当し、ミュージカルやジャズがファミコンに相当する)
さっきも言ったけど、僕たちは古臭い娯楽はどちらかというと好まない。そこに素晴らしいエッセンスがあろうが、それを読み解く労力がおきないのだ。
この映画が凄いのは、ジャズとミュージカルの素晴らしさをたったの2時間で観客にある程度理解させる事に成功している事にある。
この映画、はっきりいって初めの方は結構退屈だ。冒頭のミュージカルとか全然グッとこないし、ジャズも別になぁ・・・って思った人がほとんどだろう(劇中でもレストランで男主人公が弾いたピアノのジャズミュージックは、観客の心を全く打っていない。僕達の心もそんなに打たなかったはずだ)
それがラストシーンで一気にこの構図が覆される。一年前にレストランでやったときは見向きもされなかった男主人公のジャズミュージックは、2時間の映画という時間を通す事で、僕たち観客に全く違った感性を呼び起こす。
そしてそれを彩るのは古臭い芸術であるミュージカルだ。あんなにクソほどにもつまらなかったミュージカルなのに、この物語をみてしまった後で最後のあのミュージカルをみると、不思議な事にこちらの心を物凄くうつのである。
こうしてジャズとミュージカルという衰退しつつある2ジャンルの素晴らしいところを、たった2時間この映画を見ることで観客に理解させるという部分に監督の強烈な手腕がみてとれる。これはちょっと普通の才能では表現できない。
なおこの物語だけど、個人的には監督であるデミアン・チャゼルによるスコット・フィッツジェラルドのグレート・ギャツビーの21世紀における再解釈がベースになってるんじゃないかと思う(グレート・ギャツビーはアメリカを代表する文学作品だ。村上春樹をはじめとして、この作品に強烈な影響を受けた作家は結構多い)
ララランドに感銘を受けた人は、是非ともグレート・ギャツビーも読んで欲しい。
そこにはアメリカ人の持つ喪失に対する綺麗な感性が詰まっている。ララランドがアメリカで受けるのも、グレート・ギャツビー的な感性がアメリカ人の心を打つからだろう。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【プロフィール】
都内で勤務医としてまったり生活中。
趣味はおいしいレストラン開拓とワインと読書です。
twitter:takasuka_toki ブログ→ 珈琲をゴクゴク呑むように
noteで食事に関するコラム執筆と人生相談もやってます→ https://note.mu/takasuka_toki
(Photo:Pieter van Marion)