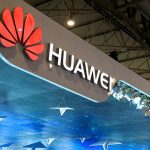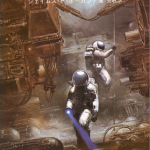編集者の方から、本を頂いた。
内容は……と言えば、要するにメルセデス・ベンツのマーケティング本である。
彼らが如何に苦心して「最高」を作ろうとしているかを克明に綴っている、きれいな話だ。
私は正直、あまり「きれいな話」に興味が無いので、自分でこの本を手にとることはなかったが、逆に「自分のスコープの範疇外」の本は貴重である。せっかく頂いたので、読ませていただいた。
そのなかで興味を惹かれた点は、彼らが「最高」をきちんと定義していることだ。
簡単に言えば、彼らが目指した「最高」は顧客とのタッチポイントを洗い出し、その全てにおいて「顧客の体験」を期待を上回ることと定義されている。
——————–
確かに、我々は「最高」が好きだ。
サービスやモノを使っていて、「これは最高である」という体験をしたことはあるだろうか。
企業における諸活動だけではなく、研究分野、芸術、スポーツなどの各分野において「最高である」と呼ばれるものは、人に多くの感動と満足を与える。
だが「最高」のものは少ない。
「最高は1つしか無いのだから、当たり前だろう」という方もいるだろうが、そういうことを言っているわけではない。
必ずしも、一番=最高ではない。
最高だと人が感じるものは「一番のもの」とは明らかに違う。
なぜならば「一番のもの」は結果として一番になっただけのものも多数含まれるが、「最高のもの」は、最初から「圧倒的にトップ」を目指さない限り、決してできないからだ。
この差は大きい。
—————
例えば、展示会か何かのイベントを企画してほしい、と上司から言われたとする。
多くの企業を集め、新製品を発表してもらうのだ。来場者には新製品に興味を持ってもらい、ビジネスマッチングや製品改善のアイデアに結びつけるイベントとする。
「わかりました」と言い、考える。
よく行われているイベントはどのように開催されているだろうか、どの程度の来場者数を見込んで、どの程度の会場を用意して、どのように出展者の管理をすればよいかを調べなければならない。
「ああ、けっこう大変だな」と、思うだろう。
そうして、粛々とイベントの開催に向けて動き始める。
会場を借り、出展者を募り、マーケティングを行って来場者を獲得する……。一生懸命動いた甲斐あって、イベントは無事に終わった。皆がねぎらいの言葉をかけてくれる。
しかし、来場者と出展者のアンケートを見て気づく。
「最高のイベントだった」とする人は少ない。良くも悪くも「それなり」のイベントであったと。
——————–
「最高を目指す人」はどうか。
展示会か何かのイベントを企画してほしい、と上司から言われた。
ところが彼は非常に悩む。
「出展者と、来場者に「最高」の展示会だった、と感じてもらうためには何が必要なのか」
彼は多くの展示会に足を運び、出展者と来場者の反応をリサーチする。
専門家を呼び、展示会の価値は何か、どのような課題を抱えており、ブレークスルーできる可能性はあるのか、彼は必死に考える。
最高の展示会を開催するには、まず出展者が最高でなくてはならないし、来場者の質も高くなければならないのだ。
予算と時間の制約の中で、もちろん、会場も行き届いてなければならない、マッチングが適切に行われなくてはならない……
その全てで「最高」を目指さなくてはならない。したがって、考えなければならないことはいくらでもある。
だが、「最高」を常に目指す彼は、妥協しない。
妥協した瞬間、「最高」は消えてなくなってしまう。彼は出展者一つ一つを廻り、ニーズを確認する。一方で、最高の来場者を獲得するため、様々なコミュニティにアクセスし、人を集めてもらうように依頼をかける。
ついに当日を迎えた。
彼は当日のトラブルに目を光らせる。最高のためには迅速なトラブル解決が必要だ。電源がない、来場者の情報が足りない、ブースが想定と違った出来になっている……
その一つ一つの解決に、彼は奔走する。
そして、イベントは最高の盛り上がりを見せる。
アンケート結果は驚異的だった。出展者、来場者の多くが「最高」という評価をしていた。
——————–
最高のものを作るのに必要なのは「才能」ではない。
かと言って「努力」でもない。普通の人であっても努力はしているのだ。
異なるのは「最高を作ろう」という意志である。偶然に「最高」ができることはほとんどない。
そのために必要なのは
まず、「最高にする」という意志が必要である。
そして、「最高とは何か」を定義できていなければならない。
さらに、「最高」を実現するために、骨身を惜しまず働かなければならない。
だからこそ、「最高」は尊いのである。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者プロフィール】
・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)
・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント
・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ
・ブログが本になりました。
・「「仕事ができるやつ」になる最短の道」のオーディオブックもできました!
(Photo:Luca Sartoni)